弱き愛の強み
男子高校生が親友を犠牲にして見知らぬ人間を救うオンライン小説です。
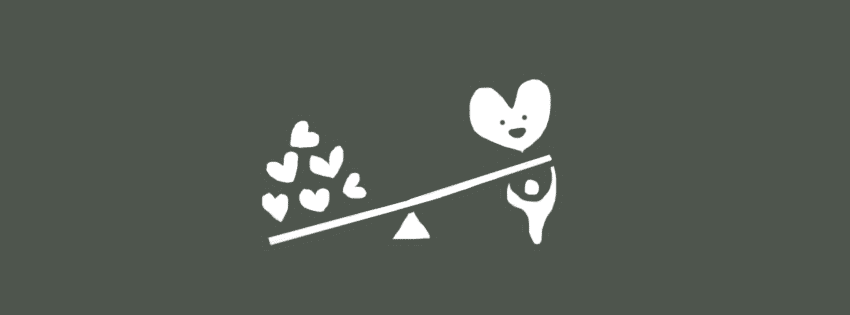
休日夕方自室。突如として正義に目覚めた俺は、猫の死骸とホームレスの垢と妹の髪の毛を煎じたものを友人に内緒で飲ませた。いつも気だるげで冴えない友はがたがたと震えて穴という穴から煙を出したと思うと、大きなため息とともにその煙幕を払う。現れたのは全身を黒で包んだ姿勢の正しい人型。身長百六十八センチだった友に変わらぬぐらいの背丈で、どこもかしこもすらりと伸びている。ケープが合わさったような半袖の黒ワンピース。まっ白な手足がはみでている。すね毛なんて飛んでいった。おっぱい。つやつやミディアムブラウンヘアー。なによりあのむくみ気味の陰惨な顔が、どこから見ても整った美少女のものに変わっている。
「キミはいったい誰だい?」
夕色の眼光が俺の背景まで捉えようとしている。それでも俺の魂までは貫けない。
「きっとこれから、だれかの味方」
「兄貴、だれなの? というか幹人さんは?」
「彼女が幹人だ」
「ボクはテレスだよ」
「彼女が元幹人現テレスだ」
「兄貴、とうとう頭が狂った?」
夕食。ダイニングテーブルを挟んで妹の真向かいに座る俺の隣にいる友人――を犠牲にして現れた彼女の名をテレスという。テレスはあらゆる問題を一息で解決してしまうプロフェッショナルであり、俗にいう悪魔の遠い親戚であった。
「悪魔ってあれでしょ。蛇みたいなやつで、甘言を振りまいてくるやつ。林檎を食べませんかって言ってくるの。で、その林檎は毒林檎で食べると眠りについてしまうんだけど、目覚めるとそこは樹の下で、この樹はマメから出来ているの」
だから努力をしている人の手には悪魔が宿るの、と妹はいう。
「テレス、可哀想だろう。妹はバカなんだ」
「兄妹なんだね」
「ああ。月と太陽で月哉と陽子なんだ」
ふむふむと頷くテレスと対照的に、陽子はテレスの眉毛から机の上でしきりに動くなめらかな指の先までを凝視していた。
「陽子。テレスは人を幸せにするためにやってきたんだ」
「そうなの?」
「そうだったの?」
「ああ。君は遠い親戚の恥を晴らすために世間でよい行いをし続けなければならない善の奴隷なんだ」
「ボクは奴隷だったのか」
テレスはがっくりときながらも夕食の湯気をじっと見つめている。
「食べてもいいのかい」
「食べたまえ。いくら奴隷でも食べる権利ぐらいはある」
「そうか。ボクは気づいていたんだよ。先ほどから何か釈然としない気がしたんだが、それはお腹がすいていたからなんだ!」
テレスはテーブルの上に並んだ皿を両手で大事そうに抱えて、そのまま丸のみした。次はその隣の皿を。またはその斜め上にあるものを。俺や妹の前にある皿まで。ぺろりと平らげて、机の上にはなにもなくなってしまった。もはや箸さえ残っていない。
「兄貴、この人は悪魔だよ!」
「そ、それはボクの親戚であってボクの罪じゃないよ」
「いいや、アナタハ罪ヲ犯シマシタ! 私たちのご飯、なくなっちゃったし皿もまっさらなの」
「皿が欲しいのかい?」
テレスが右手でばんと机を叩けばおや不思議。皿が落ちてくる。見上げれば天井からうにょうにょと皿が生成されていた。ばりんばりん。机にぶつかるごとに、いい音を立てて割れる皿。
「兄貴、この黒いの人外だよ!」
「そ、それはそうだけど差別はしないでほしいな」
「破片まで増やしてどうするの!」
怒られてテレスはしょんぼりと小さくなる。同時に天井から皿が落ちてくることもなくなったが、よくよく見ると皿になりかけのなにかが天井に張り付いていた。
「陽子、テレスに悪気はないんだ」
「悪気がないから許されるっていうのなら、熱核兵器はいらないの」
俺は妹をなんとかなだめて、テレスに囁いた。
「陽子はね、食い意地がはっているんだ。夕食を食べられなくて怒っているんだよ。だから君がご飯を出してくれたら、すぐに機嫌がよくなる」
テレスは俺を不安げに見てから、今度はおずおずと右手で机を撫でる。すると散らばっていた皿の破片はどろりと溶けて、その代わりに机からみょんみょんと皿ごと生成――たまご焼き、オムライス、オムレツ、スクランブルエッグ、生卵、ゆで卵、たまごかけご飯、そして特大の親子どんぶり。
「きゃー! 陽子、たまご大好き!」
いただきますと手を合わせてから、急いで飯にありつく妹から視線をそらし、隣で踏ん反り返るテレスを見る。
「どうだい。ボクのもてなしは」
「親子丼だけでよくね?」
テレスは俺の部屋で預かることになった。妹に頼んでみたものの、元が幹人であることから一緒に寝るのは耐えられないとのこと。風呂から出て部屋に戻ると、テレスの尻がつつましく俺を出迎えた。
「何をしているんだ」
「人間の男はベッドの下に禁断の書を隠しもっているとおばあ様に聞いたことがあってね」
テレスの尻がふりふりと答える。ベッドの下の奥深くまで覗いているらしい。
「ずっとやっていたんだろう。いつまで探しているんだ」
「じつはね、抜けられなくなっちゃって」
「君の能力でなんとかならないのか?」
なるほど、という声から派生する大きな爆発音。なるほど、俺のベッドを弾け飛ばしたらしい。壁や床に俺のベッドの残骸らしきものがじゅうじゅうと音を立ててこびりついている。
「キミのアドバイスで助かったよ」
「よかった、死んでくれ」
「それはできないな。生死をどうにかすることはボクにもできないんだ。どうにかしようとすると、それは生き物でなくなって無機物になるからね」
彼女は立ち上がり、ちょこんと首を傾げる。
「それよりボクはどこで眠ればいいんだ?」
「立って眠ったらどうだ」
「ひぎぃ! ボクは一応、女の子だぞ! 何もツイてないんだから」
そう言ってワンピースのひらひらを掴みあげたテレスを制止させる。
「俺は破廉恥のために君を呼んだんじゃない」
「……ツイてないよ?」
「それはどうでもいいから」
俺はテレスを床に座らせた。自分もその真向かいに座る。
「まあいいや。ちょうどよくベッドも吹き飛んだことだし、本題に入ろう」
大あくびとともにテレスは目を擦る。
「ウンウン」
「まず今は十時だ。そして俺の就寝時刻は十一時だ。そういうわけでこの間の一時間を十二時間程度に引き延ばしてほしい」
「ウンウン、なるほどね。生活リズムを崩さないことは大事だもんね」
テレスはうとうととしながら、右手を掲げたかとおもうと宙に向かって大きく時計回りに円を描く。と、急にはっとしてテレスは腕をおろした。
「ボクはいったい何を……」
「一時間を十二時間にしてもらった」
「キミ、ボクの眠たい間になんてことを! キミのせいで二十四時間が三十五時間だぞ」
それからテレスは俺のせいで天の国にいるヒッパルコスが心臓発作で二度目の死を迎えたであろうことを説いた。
「それにあらゆるものが緩慢になる。あくまで引き伸ばしだからね」
「時計の針がじわじわ動くだけじゃないだろうな」
「まさか! でも本当に大したことはないよ。女の子が歩くところを見れば分かる。スカートをめくりたくなるぐらい、ゆっくりと進むからね」
それでいい、と俺は立ち上がった。タンスから外着を取りだして軽く着替える。
「あうあう! キミの肉体美なんかにボクは七十五パーセントぐらいしか興味がないぞ!」
「今から人を救いに行こう」
駅近くの大通り。夜にもかかわらず、残業で今に燃え尽きようとしている命の灯で空はまだまだ明るい。人々はそこをナメクジのように行きかう。信号はまだまだ青が続く。車は微動しつつ、信号が赤になるまで延々と待ち続けているようだ。
「俺たちはこの人たちからどう見えているんだ?」
「かなり速い動きに見えているか、認識できないかもしれないね。ボクたちの一分は彼らの十二分に相当するから」
「つまり俺たちが一時間を過ごすころには、彼らも十二時間を過ごしているわけか」
「そのとおり! ……あれ? キミがそう決めたんだよね?」
すたこらさっさと道をゆき、街中の粗探しをする。テレスは静止オブジェクトとなった人々の顔をいちいち覗きこんで、まれに罪のないおじさんの頬を叩いた。
「ところでいったい、ここで何をするつもりなんだい?」
「これから起こる痛ましい悲劇を防ぐんだ」
見渡した先に、酔っ払いが道の真ん中で眠っていた。近づいてよく見てみる。腹が上下に膨れては萎み、唇が気持ちの良い波を作っている。
「このままでは轢かれるかもしれない。轢かれないとしても人類の邪魔だ」
「うん、通行のジャマだろうね」
「というわけでどかそう」
二人で寝ころんだ酔っ払いに近づき、テレスはおじさんの頭の方を、俺は尻の方をもってえっこらえっこらと道の脇に運ぶ。
「こういう感じでやっていこう」
近くにあったドーナッツショップの外壁におっさんを斜めに立てかけ、額の汗をぬぐう。隣ではテレスが「ぜいぜい」と口で言いながら息をつく。
「地道な作業だね」
「最初から飛ばしすぎると歯止めが利かなくなる気がする!」
「時間を引き延ばす時点でもうノンストップだよ」
今にも不良とぶつかりそうだった気の弱そうな顔の青年を安全な場所に動かしたり、歩道を走る自転車乗りを車道に戻したり。不合理な人間模様をうまく配列しきったところで、俺はぐるりと肩を回して息をつく。
「この街は俺の箱庭だ」
「ダークサイドに堕ちるのが早いよ」
テレスの腹時計によるとすでに五時間分は経過したらしい。夜空からメロンパンあんぱんクリームパンを召喚したテレスはぼくぼくとそれらを口の中に詰め込んで。
「もぎゅもぎゅ、もぎゅもぎゅもぎゅ?」
と立ち止まって宙を指差した。
汚いやつめ、とつぶやきながら示された方を見上げると――首が痛くなるほど高いビルの上だった。スカートが風を受けてつよく揺れながらも、じっと直立しているように見える。暗さと遠さでぼんやりしていたが、それでも俺とテレスは顔を見合わせた。
「行こう」
ビルのエントランスには人がまばらにいたが、俺たちのスピードについてゆけるものはいない。忍んで走ってぶつかって謝って転げてエレベーターと非常階段を駆使した俺たちは、屋上に繋がる厚い扉の前に立っていた。後ろで息切れをしているテレスを無視して扉に体当たりするが、びくともしない。それどころか、俺はぶつけた力を返される形でひょろっとその場を後退し、一段下にいたテレスを背で押しつぶす形で転げさせる。ごろごろと音を立てて階段の踊り場にまで転げ落ち壁にぶつかる間抜けなテレスを反面教師に体勢を整えた俺は、首だけ振りかえる。
「ひ、ひぃっ、ひどいじゃないか!」
ぼろぼろになりながらよたよたとテレスが階段をのぼってくる。哀愁すらただよう怨嗟の鼻息が硬い壁と床に跳ね返って大きく聞こえた。
「体当たりで扉を開けるの、やってみたくて」
「キミ、存分にお茶目だね」
改めてドアノブに力を掛けて、足音を響かせないようにおそるおそると屋上に侵入する。テレスもそれに合わせてそっと足を踏み入れたが、扉については思い切りに音を立てて閉めた。
「バレたらどうする! 屋上にだれがいるかわからないんだぞ」
「ボクに任せたまえ。たとえ相手が宇宙一般人でも宇宙大統領でも、この世界まるごとを爆破して宇宙のちりごみにしてあげよう」
「宇宙環境に悪い」
俺たちはぎゃいぎゃいとお互いにヒップアタックを繰り返しながらも、屋上のフェンスの向こう側に立っている女性らしき影に近づく。クレーンゲームの要領で、クレーンになった俺はアームであるテレスの腹をフェンスの上部に乗せる。テレスことアームはパカッと腕を開いて、背後から両脇にツメを引っ掛ける形で女性を持ち上げた。クレーンこと俺は掴んだテレスの足を引っこ抜くように引っ張って、女性をこちら側に引き戻す。女性を一ミリの歪みなく綺麗に直立させたテレスは、俺の隣にそよそよと戻ってきた。俺たちは並んでその女性を見てみる。その人は青白い顔をしていた。どのパーツにも神経質そうな細さと弱さが見受けられる。特にこちらをぼんやりと捉えるその目は、薄暗い鋭さを持っている。まだ死んでもいないのに、年季の入った幽霊のようだった。
「何か言っているようだね」
最初に気づいたのはテレスである。よくよく見てみると、女性の唇がぬわっと広がったり閉じたりしている。少し待って聞いてみたところ彼女は「ああああああああああああああああああああああ」と発声していることが分かった。
「だめだ。何を言っているのかさっぱり分からない」
「時間を元どおりにしてみよう」
部屋でやったのと同じようにテレスが右手を掲げる。宙に向かって小さく「二度も死んだら次も怖くないよねヒッパルコス」とつぶやきながら反時計回りに円を描いた。
突然に吹いた強い風に打ちつけられる。と同時に息遣いなるものが激しく耳を叩いた。うつろな目をした女性がこちらに向かって口を開く。
「あなたたち、だれなの?」
女にしては低いその声に答えたのは、俺の隣でぷらぷらと立っているテレスだ。
「だれかの味方と、悪魔の親戚!」
「意味が分からないわ」
「あうあう! 月哉、相手は言葉が通じないらしい」
そんなわけあるまい、俺はずるずると足を引きずって一歩だけ前進してみた。
「あのう、こんなところで何をされているんですか?」
「あなたたちには関係ないでしょっ! それ以上近づくと突き落すわよ!」
「すびばぜんっ!」
俺とテレスはずりずりと二歩だけ後退した。女性も睨みをきかせながらフェンス際に後ろ足で進んでゆく。
「でも考えてみてよう、月哉。ボクたちは今、二対一だ。どちらかといえばボクたちの方が彼女を突き落せるといえないかい?」
「恐怖で目的を違えるのはよせ!」
しかし念のために武器でも用意させた方がよいかもしれない。そう考えている間に、女がフェンスの方に走り出した。
「あっ、ちょっと!」
もしやまたフェンスを乗り越えるのではないか。勇気を振り絞って一歩を踏み――。
「こないで!」
「ばびっ!」
しゅんっと縮こまって、左足を一歩だけ出した状態で凍りついてしまう。おそらく俺と一緒に動いたのだろうテレスも女の声で先に止まった俺の背に勢い良くぶつかり、跳ね返され、尻もちをついたようだった。痛いところがあったのか、俺の後ろでひぎぃひぎぃと汚い呻き声を上げている。
一方、女性はフェンスを両手でがっちり掴み、顔だけこちらに向けて叫んだ。
「あなたたち、早く帰りなさい。邪魔よ!」
「ま、待ってください。もしかして、まさか、ひょっとすると、三パーセントぐらい、死ぬ気ですか?」
「もしかしなくてもっ、死ぬわよ! 私はどこにいるにも値しない人間だものっ! 私の就職先は地獄だって、さっき、決めたの!」
俺は驚愕した。どのくらい驚愕したかというと尻もちをついていたテレスが起き上がるばねの力でぴょーんと一瞬で女の前へと跳躍し女をフェンスから引き剥がして顔面を殴りつけたはいいが殴り飛ばした女の反対方向にテレスがおそろしい反動の力で跳ねゆきフェンスに体がぐきっとめりこんだのをこう片付けるぐらい驚愕した。
「こ、攻撃効率が死ぬほど悪い……」
「死んでないよ! 死んでないから詰る前にボクをフェンスからひっこぬくんだ!」
変な方向に曲がった足をぷらぷらとさせるテレス、生きるグロテスク。俺は爽やかな夜の空を見上げた。
「魔法でなんとかなるんじゃないか?」
なるほど、という声から派生する大きな爆発音。なるほど、フェンスをぶち飛ばしたらしい。床や宙にどろっとしたフェンス色の何かが飛び散り、テレスが屋上から落っこちた。
「テレスーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!」
かつてフェンスのあった場所にじわじわと近づいて、下を見る。街に出てきた時よりも闇はいっそう深まり、人通りも少なくなっている。ぱち、ぱち、と瞬いてから付く街灯を見つけた。酔っ払いと別の酔っ払いがぶつかって倒れるのを見た。何も入っていないと思われるコンビニの袋が風に流されて道路にまで飛び出し、何度か車に轢かれた。しかしテレスはいなかった。
「茶番はこれで終わりのようね」
女性の澄ました態度に、俺はついかっときてはり叫ぶ。
「こんな不謹慎なティーパーティーはないよ! 君のために消滅したんだよ!」
「勝手に爆発しただけじゃない」
何も言い返せない俺は就寝時間を思い出し、そのまま家に帰ろうとした。が、女性に背を向けたところで、屋上扉の前にバナナの皮を帽子に洒落た、俺の元友人が立っていた。
「ボクは自滅系美少女だから、なんでも蘇るんだ!」
「自称する暇があったら、自滅しないように対策した方がいいんじゃないか」
テレスはばたばたと歩いて、悪臭を漂わせながらも俺の隣に立った。
「ねえ、お姉さん。ボクのおばあ様はこう言っていたよ……人間の男はベッドの下に禁断の書を隠しもっているって」
「だから何なの?」
「本当に大切なものは、いつもベッドに下にあるんだよ」
つい気になって「だとすると俺はどうなんだ?」と囁けば「キミの心は空っぽなんだよ」と冷たい宣告をされて、テレスの腹肉をえぐるように掴む。
「ひぎい……痛いよ月哉……とにかくだね、お姉さん。こんな高いところで達観してわかった気になっていないで、たまには這いつくばって底を見てみるといいよ。キミが失くしてしまったと思ったものは、増えて乱雑になってしまったモノの中に紛れているだけに過ぎないから……ぎい、月哉ァ、痛い、千切れる、お腹のお肉ちぎれちゃうゥ」
虐待されるテレスの鳴き声の中で、自殺企図者が衝動に耐えるようにして息をのむ音だけが鮮明に徹った。彼女は細い手で腕を隠して――その拍子に着ていた長袖がめくれて、何度も走った線が見えた――俺たちの横を通り過ぎて、足早に去ってゆく。
「こんなの、興醒めよ……今日はもう止めておくわ」
屋上の扉が閉じる音だけがはっきりと聞こえた。俺とテレスは振り返って、誰もいない、殺風景な屋上扉を見やる。
「簡単に引き下がってもらえてよかったね」
「ああ。下手に話が長引くと睡眠時間に影響が出るところだった」
ぐうぐうと鳴るテレスの腹時計を音楽に、俺たちは歩き出す。
「しかし、今日はやめておくということは、明日や明後日には第二、第三の希死念慮が彼女に襲い掛かるだろう」
「大丈夫だよ。こっそり彼女の部屋に忍び込んで、ベッドの下に現金をふかふか敷いておいたから」
「現金」
晴れやかな休日。その夜には両親が帰ってきて、その翌朝には月曜日が始まる。敷布団代わりに敷いていた掛布団の下に潰されて口から異物を垂れ流しているテレスの背をバキバキと踏み歩きながら、考える。
時間は大切に使わなければならない。
パジャマ姿で海外に出向いて恵まれない子どもたちに芋と玉ねぎをぶつけてその帰りに季節風の影響で強風が騒がしい島の沿岸に隙間なくモアイを盛って殺風景な湖にブルーギルを放し人の庭にぽつんと寂しそうなナメクジを見かければ酒を一面に撒いて帰宅しパジャマのままダイニングテーブルを囲んで朝食を摂っている最中に陽子と牛乳早飲み競争をしていたテレスが噴出した牛乳を砂漠の中に咲いている一輪の花にぶちまけて電車の中で腹痛に困っている者あれば新しく生成した隔離車両を連結して思う存分にそこで脱糞してもらい暗殺を企てられている残忍な独裁者があれば仁王立ちしたテレスを適切に配置して銃弾を防ぎ吐血するテレスの首根っこを持って引きずりながら陽子の待つダイニングに帰る。
「ああ、お帰り。さっき明梨さんが来てね、一緒に昼食を作ったの」
椅子に腰を掛けてから、テーブルの上を見る。茶色の焦げ目がおいしそうな卵焼きの大盛り皿を取り囲むようにして、ケチャップとマヨネーズと塩としょうゆの掛かった優雅な目玉焼き、チーズと混ざって黄色がとろりと鮮やかなスクランブルエッグ、ほかほかと湯気の立っているかき玉スープが並んでいる。
「贅沢しすぎなんじゃないか」
「明梨さんも私も買い物上手なの」
「わあ、すごいよ月哉! ここは卵の地獄だ!」
「ここは卵の王国なの。卵の崇高さが分からないなら食べなくてもいいの」
ひぎいと悲鳴を上げて泣き出すテレスを無視して、盛られるあまり崩れかかっている卵焼きの山から卵焼きをそっと箸でつかんで食べる。確かに明梨と一緒に作ったらしい。いつもよりほくほくと甘い味付けになっている。
「ボクも今日から卵の王国民だから卵焼きを山盛り食べていいんだ! 食べるんだ!」
「いちいち許可を取らなくていいよ」
「そうだよ、テレスさん。私たちの分を残す程度に遠慮しながら遠慮しないで食べて」
わかってるようと言いながらテレスが山の側面から卵焼きを取ろうとしたところで、バランスを失った卵焼きたちが音もなく崩れおちて皿の縁にぼたぼたと落ちてゆく。陽子にギンッと強く睨みつけられテレスはおたおたしながら皿の縁に落ちた卵焼きを口に運んでゆく。
「だ、大丈夫。落ちたやつはボクが食べるから!」
「そうやって落としまくってすべて平らげる気じゃ?」
「もぎゅ?」
テレスはちょこんと首を傾げながら拳で握った箸を卵焼きの山に向かって刺した。突然横方向から与えられた力に、卵焼きの山が崩壊してゆく。
皿の縁どころか机にまで落ちた卵焼きを拾って、ほくほくとテレスは頷いた。
「山も崩せば塵となるっ!」
「陽子、フォークを持って席を立つな。一応、食事中だぞ」
「元幹人さんじゃなかったら出し巻き卵の材料にしてる」
「ひぎぃ!」
室内照明できらりと輝くフォークの先を見て、テレスは口に含んでいた卵焼きを魔法でリバースし、皿に戻そうとした――ぐさりと肉に鋭利なものが突き刺さる音を聴きながら、俺は優雅な気持ちでゆっくりと目をつむり、卵料理を噛み締めるように味わった。
洗面台の前で歯を磨いていたところで、背後の扉が開き、鏡の中にひょこっと妹の頭が見えた。
「あれ、テレスさんは?」
「歯磨きの時まで一緒というわけにはいかんさ。それにあいつは食べ過ぎで動けないと言って俺の部屋でごろごろとしている」
「ふうん……兄貴の部屋かあ」
口を漱いで陽子の方を振り向く。じとっと俺を見上げるその顔はいつも通りに見える。
「どうした?」
「最近兄貴の部屋に入ってないなと思ったの」
「俺だっておまえの部屋に入ってないだろ?」
「入ったらコロス」
誰も救わない会話だ。早く困っている人々を救いにいかないと。うんうんうんうんと高速で頷いてこの場を切り抜けようとしたところで、妹の表情が強張った。
「兄貴、なんか疲れてる? ご飯はきちんと食べに来るけど、家にいる気配がしないの」
「……俺の将来の姿かもしれないな」
「えー、兄貴に限って引きこもりはないの」
人は見かけによらないんだぞ――と答えてもさらに心配されるだけだろう。
「冗談だ。休みだと思ってはしゃぎすぎただけだよ。今日も出掛けるし」
「むう、兄貴ってば構ってくれないの」
「忙しいから」
用もなくなったので妹と共に洗面所を出る。先に出た妹が俺の前でぴょこぴょこと歩く。背が小さいので歩幅も小さく、追い抜かそうと思えばすぐに追い抜ける。急かそうとして妹の背に手を伸ばしたとき、陽子が少しだけ首をこちらに向けた。
「テレスさんと仲良し?」
習慣であるように妹の頭を小突こうとした。が、なんとなくやる気もなくて腕をおろしてしまう。
「そうなんだろうな。ああ、仲良しだよ」
「だったらいいや。兄貴が幸せならそれでいいよ」
「何だそれ」
陽子はたったっと廊下を駆けたと思うと、曲がり角のところで少し止まってべっと舌を出し、そのまま去っていった。立ち尽くしていると、ぬっと壁からテレスの尻がめりめり大きな音を立てながら飛び出てきた。全身が壁から離れてから、テレスは俺の顔を覗き込む。
「ボクと仲良くしている暇があれば、妹さんと肘を突きあったらどうだい?」
「関係ないだろ」
テレスは大あくびとともにぐりぐりと頭をひねりながらつぶやいた。
「関係あると、思うんだけどねえ」
生命の危機に瀕している人を探しに外を歩いていたところで、テレスが俺の腕をちょいちょいと引っ張った。勢いよく振り払って先に進もうとしたところで、テレスが再び俺の腕をつかんで汚い涙を流す。
「なんで無視するのさ。ボクは、ボクはこんなにかわいいのに!」
そう言われてしぶしぶとテレスの顔を眺める――鼻水で流れ出たと思われる鼻毛が顎についていた。
「おまえは汚いんだよ」
「どおおおおじてそんなぴどいごとびうのざあああああああああああ」
街中を歩いている途中でもらった無料のティッシュをポケットから取り出す。俺の行動に気づいたらしいテレスはぴたっと泣き止んで目を瞑り、つんと唇を上向きに尖らせた。
俺は広げたティッシュを十枚ほど重ねてそっと――テレスの顔面に押し付けた。
「んぐーーーーーーーーーー」
「少しは永遠に黙れ」
がぶっとテレスがティッシュ越しに俺の手を噛んだ。畜生、と空いた片手でテレスのおでこを掴みなんとか引き剥がす。テレスはむしゃむしゃとティッシュを食べながら、げえげえと鳴き声を漏らして地団太を踏んだ。
「ボクはただ、このテーマパークに入ってみたいと思っただけなのに!」
テレスの言葉に辺りを見渡す。道路を挟んですぐに小さな駅の入り口が見え、その両横に銀行やファストフード店がずらっと並んでいる。観覧車もシマウマもクラゲもいない穏やかな街並みのように見える。
「頭がテーマパークなんじゃないか」
「目の前! 目の前にあるじゃないか。ボクらの故郷が!」
やれやれと肩をすくめて、俺はテレスがピシッと指を突きつけたその方向を見る。
ちょうどその時、自動ドアが開いた。そこから二十歳を超えたぐらいの男がだらだらと出てくる。店内からド派手な電子音と硬い何かがぶつかってジャラジャラと溜まる騒音が聞こえた。男が俺たちの横にまで立ったのに少し遅れて自動ドアが閉まり、騒音は遠ざかる。
「ギラギラと何かがしきりに光っているし、床がぴかぴかで、さらにお金の匂いがするよ、月哉! これがテーマパークじゃないなら、いったい何なんだい?」
「さあ……サファリパークか何かじゃないか」
「ちょっとは野生にかえって休憩しようよ、月哉」
「土にかえりたい?」
「かえりたくない、かえりたくないよマッマーァアアアアアアアアアアアア」
騒ごうとするテレスの口に残りのティッシュを全て詰め込んで一息ついていたところで、先ほど店から出てきた男性がこちらに近づいてきた。
「君たち、さっきからずっとここにいるね。あっ、警戒しないで。オレは里原昭仁って言うんだけどね。君たちはなんて言うの?」
「ボクはテレスだよ!」
「田中太郎です」
首を九十度傾けてぶるぶると顔を痙攣させながらこちらを見るテレスの目を指で潰す。昭人さんといえばへらへらと笑いながら、馴れ馴れしく俺の肩を叩いた。
「そっかあ、テレスちゃんに田中君ねえ……ずっと店を見てたけど、ギャンブルとか興味あんの?」
「ないです」
「お金に困ってるとか? 少し貸してくれたらお兄さんがちょっくら増やしてあげるよ」
「ないです」
「ねえ、君たち。お金とか余ってない?」
「ないです」
肩を叩く力がどんどん強まってきたのを受けて、未だに痙攣しているテレスの頭を俺の肩に引きよせた――昭人さんの手がリズミカルにテレスの頭を叩きはじめたのを確認して、俺はそっと後ずさる。
「いや、本当に。お兄さんのことを信じてよ。ここで会ったのも運命だと思ってさ」
「ないです」
バンバン。
「マジで。オレ、人から借りた金で百年以内に返せなかったことないよ?」
「ないです」
バンバンバンバン。
「若いんでしょ。もし損したとしてもいいじゃんいいじゃん。金をむだにしてしまうのも青春の一つだって」
「ないです」
ガシッ、ボカッ、バキッ!
「さよならボクのサファリパーク!」
頭への度重なる強い衝撃に倒れたテレスを足蹴に、俺は昭人さんを睨みつけた。
「とにかく、ギャンブルに貸すようなお金はないですから」
「でも、オレは本当に困ってるんだよ! ここで、ここでお金を取りかえせなきゃ……」
「取り返せないと?」
「慰謝料が払えなくなってしまう!」
昭人さんは両手を合わせて、十度ぐらい頭を下げた。見た目は若いが、色々と背負っているものがあるらしい。俺は足蹴にしていたテレスをひっぱり起こして、詳しい話を聞くことにした。
「困っているのなら仕方ないですね……どれぐらい必要なんですか?」
「八万円! これだけあれば絶対に取りかえせるし、なんなら二倍で返す。八万円あったら十二万にして五万円を渡すから」
「テレス、どう思う?」
問いに対し、テレスはふらふらとしながらも胸を張って鼻息を荒くした。
「このボクをなめてもらったら困るね。ボクはだまされないぞっ。それじゃ一・五倍返しじゃないか」
「むちゃくちゃ騙されているよ、テレス」
まだ本調子でないらしい。俺の指摘にテレスはまだ口の周りについていたティッシュを舌で舐めとりながら「そんなことは出会った時から知っていたよ」と腕を組んだ。
「ボクが本当の倍返しというものを見せてあげよう。お兄さん、お金を一時的に貸してくれないか」
「あっ、そうやってお金を盗む気だな! オレもやったことがあるからわかるゾ」
「まあまあ、ボクみたいなか弱い女の子を信用しなくて、いったいだれを信じるのさ?」
「明日のオレ!」
「ニヒリストなんですね」
俺を睨みつけながら、昭人さんはぺっぺとつばを吐いて尻ポケットから財布を取り出した。ビリビリビリ。マジックテープの封印が解かれる音に、自然と背筋が伸びる。
「あー、じゃモジャ男ね。うん、モジャ男やるわ。ほい、モジャ男」
昭人さんはくしゃくしゃになった紙幣をテレスに差し出した。その手は震えていたが、テレスは堂々とそれを受け取った。
「今日は良い風が吹いているね。これならたくさんの紙幣が集まりそうだ」
「風と紙幣の何が関係あるんだ?」
「人間の座右の銘によくこうあるだろう? ――風が吹けば月哉が儲かる」
「ん、ツキヤって何? 桶屋の親戚?」
「さあ、分かりませんね。黒んぼの妄言でしょう」
俺たちの言葉を無視して、テレスは昭人さんから受け取った紙幣をぶんぶんと空気にさらしながらぶつぶつと唱え始める……「おまえら、おれ、ともだち」「かび、きらい」「ほこり、いや」「しっけ、しぬ」「におい、つく」そのうち、ごうごうと強まってきた風の音でさらにテレスの声は聞き取りづらくなった。が、隣から子どものように無邪気にはしゃぐ声が聞こえた。
「フォオオオオオオオオオオオ! 金だ! 風に乗ってお金が落ちてきた!」
昭人さんの言葉で顔を上げたところで、何かが頬に張り付いた。端をつまんで確かめてみると、おもちゃでも何でもない本物の紙幣がそこにある。
今に大量の紙幣がパチンコ屋の前に降り注いでいた。昭人さんはそれらのすべてを拾おうとぴょんぴょんと飛びながら手や足を伸ばし、時に寝転がり、紙幣にかじりつきさえした。
「テレス……」
「大丈夫、人避けはきちんとしているよ! ボクたちを吐瀉物に錯覚する魔法を掛けているからね」
アスファルトの地面に這いつくばりながら恍惚とした表情で紙幣を抱きしめる成人男性を見下ろす。確かに吐瀉物と言っても間違いではないだろう。
「その前に……この紙幣は安全なものなんだろうな?」
「安心したまえ月哉。これはこの世に現存する札を呼び寄せているだけなんだ。この世には雑誌やタンスの中で退屈をしている札たちがいるらしくてね。ボクはその札たちに向けて情報を発信したのさ! ここに金遣いの荒そうな男がいるぞ、とね」
風が止んだと同時に、昭人さんは落ちてきた紙幣をすべて拾い集めたらしかった。立ちあがった昭人さんは重ねた紙幣で俺とテレスの頬を三回ほどぶったあとで、紙幣に何度もキスの雨を降らせた。
「しゅごい。全部で八十枚……ぴったり八万円ある! わーい、やったーーーー! 何もせずに金が手に入ったーーー!!」
「あ、あの……」
「おっ、大丈夫。きちんとこの借りは返すからさ! うん。隣のファストフード店で時間を潰しててよ。俺はやれば出来る子だから、期待して待ってて」
そう言ってスキップしながらパチンコ店に向かう昭人さんの背を見送りながらつぶやく。
「テレス、俺は今、正義の味方になれているんだろうか?」
「ナメクジにビールをあげるより、人のためになることをしたと思うよ」
その後、俺たちは昭人さんがお金を返しに来るのを待ってファストフード店のテーブル席でひたすらに時間を潰していた。
くしゅくしゅと縮んだストローの袋に水滴を垂らしていた。
メニューを暗記して交互に言いあうゲームをした。
備え付けのペーパーで鶴やだまし船を折った。
昭人さんは来なかった。
「もうっ、信じられない! 外で食べてくるなんて!」
どすどすと大きな足音を立ててダイニングテーブルの周りをぐるぐると回る陽子に、テレスはびくびくとテーブルの下に隠れた。俺の座っている椅子の足にすがりつきながら、テレスが泣き叫ぶ。
「月哉が悪いんだよぉっ。ボクのことを盾にしたり足蹴にしたりするからぁっ」
「それは今、関係ないだろ」
「そうだよ、テレスさん。それは今関係ないよ」
ぴぎいとぴぎいと泣いているテレスを机の下で蹴っ飛ばして、俺は用意されたコップの水をぐいっと飲み干す。
「連絡はきちんと入れただろ」
「そういう問題ではなくて……とにかく、妹は怒り心頭なの」
夕食を一緒に摂れなかったぐらいでそこまで怒ることもないだろう。そう指摘すれば、陽子は一転、泣きそうな顔になって俺の対面に座る。
「お兄ちゃんたちが帰ってこないから……泥棒に入られた」
椅子が倒れたが、それどころではなかった。妹に近づいて震える肩を掴む。
「泥棒だって!? 大丈夫なのか!?」
「大丈夫じゃないよう……陽子が雑誌の中にこっそり隠していたお年玉がなくなっちゃったの……昨日までは確かにあったはずなのに……」
「ああ、それは大丈夫だ。気にするな」
机の下から這い出てきたテレスも、俺の隣について陽子の頭を撫でた。
「うん、大丈夫。本当に大切なものは、いつもベッドの下にあるからね!」
「どうしてそんなに息ぴったりなの……?」
「だいたいお金なんかあっても人を裏切りやすくなるだけだぞ」
「そうだよ。お金があっても儚いものに投資して、時間を無為に潰すだけだよ」
ぐずる陽子をテレスと取り囲んで小一時間ほど説得したところで、ようやく納得したらしい。陽子は唇をわずかに噛みながら固めた拳でテーブルをドンドンと叩きつけ、止めようとするテレスの髪をひっぱりながら。
「でも兄貴の帰宅時間が遅いのは話が別! アイスで詫びなきゃ許さない!」
と怒鳴りつけた。
蝉以外の虫が鳴いている。
早く帰って次は何をするか決めないと。三人分のアイスを入れた袋を突き進む膝でとんとんと蹴りながらに暗がりを歩いていく。「ツキヤーキイモー。オイモーツキヤキイモはいかがですかぁー」こうしている間にも恵まれない子どもたちがお芋に飢えて死んでいると思うと気が重くなる。どうか彼らがたくさんのお芋に恵まれますように――。
「月哉!」
斜め上後ろから声を掛けられて、俺はぎくりと立ちどまる。見上げると二階の窓からだらりと腕を垂らした何かがいる。見なかったことにしよう。
足早に去ろうとして、何かが頭に当たって落ちた。立ちどまってしぶしぶとそれを拾い上げる。兎のファンシーなカバーと裏腹にすべての角を使い切って丸くなった、夢も希望もない消しゴムに思わずため息が出る。カバーを外してみると、表面には黒のマジックペンで『つきや』と書いてあった。桶屋の間違いだろう。カバーを戻して、顔を上げる。
「ひどいよう、月哉。そこまで無視することないじゃんかよう」
俺は数歩戻って、項垂れる幼馴染の正面に立った。
「何してんだ」
叫んでみると、塔のお姫様は急に体を起こして無事に窓枠にぶつかった。
「月哉はひどい!」
「今のは自業自得だろ」
明梨は後頭部をさすりながら、今度はゆっくりと窓から顔を出す。
「本当にひどいんだもん。いくらご両親が旅行中だからってさ、月哉は自由にしすぎ」
「何のことだよ」
「女の子、連れ込んでいるでしょ」
俺はテレスの汚い顔を思い浮かべたあとでゆっくりと首を横に振った。
「大丈夫だ。あれは一応、元幹人だから」
「えっ、なにそれ。幹人くんのこと、女の子にしちゃったの?」
「女の子にしちゃったんだ」
明梨は口をぱくぱくと開けたあとで、顔を真っ赤にした。
「こ、これはもうお赤飯だね?」
「いや、元幹人と言っても今は普通に女の子だからな。今日の昼だって、陽子にこねこねされていたし」
「陽子ちゃんが元幹人くんをこねこね?」
「ああ」
明梨は顔を両手で隠してぶんぶん頭を振った。
「やっぱりお赤飯だーっ」
「お赤飯の大安売りはやめろ」
待ってて! その一言で幼馴染は窓から消えたと思うと、扉の開く音がした。
「おまたせ」
「早えよ」
明梨はぜいぜいとしながら俺に駆け寄る。さらさら梳かされた明るい茶髪が少し濡れていて、かすかに石鹸の匂いがした。
明梨は顔を紅くしてくねくねとしてから。
「やっぱりだめだよう、月哉。いくら自由だからって節操は守らないと」
「何もしてねえよ」
「何もしていないなら、どうしてあたしのとこに来ないのさ」
なるほど、そこが本題らしい。軽く咳払いをする。
「幼馴染だからっていつまでも女とつるんでられねえよ」
「そんな中学生みたいなことを言って! もう高校生でしょ! 性生活ではもう大人かもしれないけどね! ハレンチン!」
「下ネタ好きだよな、おまえ」
腕を組んでつーんと明梨はそっぽを向いた――と思いきや、ちら、ちらっと俺の方を見た。
「結局、ご近所づきあいってことだね。あんたのお父さんとお母さんがあたしのお父さんとお母さんと仲がいいから、その延長で仲良くしていただけ。だから両親が旅行に出かけたとたん、私と月哉との繋がりはぱっと消えちゃう」
明梨の声はどんどんとしぼんできてそのまま俯いてしまった。
「元幹人くんって言うけどさ。幹人くんだって月哉の大切な友達だよね。でも月哉は友達との繋がりよりミステリアスでキュートな新しい女の子を選んじゃうんだ」
これには事情があるんだ、と俺は言いかけた。だけどそうか? 理由は違ったかもしれないが、結果がそうであるなら何の言い訳もできないんじゃないか? 風が吹き、ぶるりと明梨が震える。今になってようやく気づいた。明梨は薄着でしかも裸足だった。
「明梨、ところで今日の昼食なんだけど――」
「いいよ、いいよ! 分かってる。幼馴染ってのはね、結局は置いて行かれるものなんだよ。だって幼馴染ってのは過去の象徴なんだから」
明梨はぱっと顔をあげた。笑っている、ように見える。
「でも幼馴染は変わらない! 安定性では、やっぱり幼馴染がナンバーワン! 殺傷率九十九パーセント!」
「何を殺した」
「えっと。それで、だからね月哉。月哉も変わらないでね。それはたぶん呪いだけど……せつない呪いだから許してね」
明梨はとたとったと駆けてゆく。玄関扉が閉まる音。俺はしばらく立ち尽くして二階の窓を見ていた。だけど明梨がふたたび顔を出すことはなかった。
「バカ兄貴。アイス、溶けてるじゃん」
包装の中でぶよぶよとしているアイスをちょんちょんと指でつつきながら、陽子は口を尖らせる。その隣に座ってウインクの練習をしているテレスに、俺は三人分のアイスを差し出した。
「テレス、復元してくれ」
「あまり美味しくないなにかになるけどいい?」
「ちゃんと食べ物なんだろうな?」
テレスは何も答えないで、ばちっとウインクをした。俺と明梨はアイコンタクトをして、テレスを羽交い絞めにした後、どろどろに溶けたアイスを体がうんと冷えるまで飲み干した。
まだ寝るには早い時間だった。床に布団を敷いていたところで、下敷きにならないように部屋の隅で丸まっていたテレスが欠伸混じりにいった。
「そういえばもう夜だろう? ご両親が帰ってくるのを待たずに眠っていいのかい?」
「そのことについて相談があるんだが」
枕をぽんぽんと叩いて硬さを調節する。おそらく、陽子はもう眠っているだろう。
「今、両親に帰ってきてもらったら困る。まだまだ俺は救いたりないんだ」
なるほど、とテレスはつぶやいた。つぶやくだけで両手を膝に置いて俺をじっと見ている。
「でもさ。ご両親は早く家に帰って、お土産を広げて、君たちとの団らんを楽しみたいだろうね」
「団らんなんていつでもできる」
「キミは幸福だからね」
「そう。幸福だから不幸に対しての義務がある」
テレスは目を閉じて、左手と右手を組み口元に添えた。それはまるで祈りだ。俺も真似てみる。目を閉じて暗闇の中で想像してみる。でもうまく浮かばない。苦しんでいる人がどれだけ苦しんでいるのか、俺は知っているようで知らない。どこまでもそれは遠い。
「さ、キミ。これでご両親はしばらく帰ってこないよ」
肩を叩かれて目を開ける。テレスは眉をさげて困ったように笑っていた。
「キミがそんなことしたって、何にも起きないよ」
「うるさい」
布団の上に置いた枕を奪って、テレスは固い床にべったりと全身を溶かして横になる。やがてすやすやと寝息を立てる、彼女の睫毛が長いことで本当に幹人は幹人でなくなったのだと実感する。
そうだ。実際にそうしてみなければ何も起きないんだ。
かつて妹と幼馴染で住宅街を探検したことを思いだす。あの時、俺たちはまだまだ小さい子どもで、道をひとつ曲がることにもわくわくと不安でいっぱいになっていた。俺は先陣をきって曲がり、明梨は目印になりそうなものをつぶやいて、陽子は俺の袖を引っ張っていた。だれとも出会わないで、ずっと曲がったり戻ったりしていた。この世でたった三人しかいないような感覚に陥った。それでも少し期待していたのかもしれない。こうやって進んでゆくうちに新しい場所につく。そこは未だ見たことのない、優しくて、明るくて、楽しい素敵なところだって――呼びかけられてふりむいた。母親がいた。俺たちはただぐるぐると狭い世界を彷徨って、同じところに帰って来ただけだったのだ。
陽子は身を縮めて、浮かせた人差し指で執拗にダイニングテーブルを叩いた。こつ、こつ、こつと間隔がやがて短くなってゆき、等間隔に刻んでいるはずの時計の音が揺らいで聞こえる。
「陽子、やめなさい」
「どうして帰ってこないの? 兄貴、なんか聞いてない?」
下手に答えてしまうと追及は激しくなるだろう。首を横に振る俺を見て、陽子は机を叩くのをやめて俯いた。
「何かあったんじゃないの。最近、ちょっとおかしいよ。幹人さんだって――」
「元幹人ならここにいるだろ」
俺の隣で下品な音を立ててお茶を飲んでいたテレスを顎で指す。陽子はテレスを一瞥もせずに頭を抱えて、そのまま突っ伏した。
「今日、学校、休む」
「分かった。きちんと戸締りしとけよ。俺たちは行くから」
「……その恰好で学校に行くの?」
席を立った俺たちは服を見せびらかすように陽子の前でくるくると回る。テレスのそれはいつもの黒ワンピースで、俺は白のポロシャツとラフなパンツを履いていた。
「こんな格好で学校なんて恥ずかしいだろ」
「うん……分かっているならそれでいいの」
陽子を納得させたところで、俺たちは足早にダイニングから退出し、息をひそめて家を出る。太陽の光を受けて白のポロシャツがまぶしく発光する。
こんな格好で学校なんて恥ずかしいから、もちろん学校には行かない。
うろついている途中で見知った顔を見つけた。俺はテレスに目配せをしてから、そっとその男の右隣につく。テレスもその反対側について、何もなかったようにまっすぐと前を見て歩いている。やがて気づいたらしい男がこちらをちらっと見て、駆け出そうとしたところで俺とテレスは昭人さんの腕をがしっと掴んだ。
「よくもボクたちを騙したなっ!」
「ハハハハ。騙される方が不用心なんだよ。この世に騙されるやつがいなかったら騙そうとする人もいない。つまり弱さが悪さを増長している!」
「キミみたいな存在は指の先端から千切っても爪の垢が汚いんだ!」
「綺麗な垢なんて他人に飲ませやすいぐらいにしか価値がないね! ところが人間は他者に垢を与えるために生まれてきたわけじゃないんでね」
「では何のために生まれてきたんですか?」
率直な質問に昭人さんは俺たちの拘束を振り払って、空に向かって大きく腕を広げた。
「一瞬のスリルに燃え尽きて、世界の燃料になるためさ!」
「人から借りた八万円をスって、あなたは世界の動力になれたんですか?」
「そうだなー。あともう八万円ぐらいあれば、ちょっとは世界をこう、三度ぐらいどうにかできると思うんだけど」
昭人さんは俺とテレスの前に両手を差し出す。誰が、誰がこんなになるまで彼を放っておいたのだろう? 胸がぎゅっと締め付けられるような思いで、テレスに囁く。
「この人を更生させるにはどうすればいいんだ」
「悪人にだって、大好きだったあの子や青春時代があったはずだよ」
テレスは昭人さんに向かってぴんと伸ばした人差し指を、くるっ、くるっと円を描くように回しながら右足を一歩踏み込んだ。
「ボクの生活にトリシャートフはいない! でもトリシャートフは言っていた。かつては良い人間になることを夢想していたと。キミもそうじゃないかい? 今ではこうだらしなく淫らなろくでもなしでも、昔はいい夢をみていたに違いない! さあ、きちんと言葉に出すんだ。キミが夢見ていたのはなんだ!」
「ええっと……パチンコライター?」
「もっと! もっと汚れる前!」
昭人さんはうんうんと唸っている。俺がテレスに目くばせすると、テレスは右手で空を一拭き。直後、情緒的なピアノの音がどこからともなく響いてくる。
「ああっ、そうだ。オレは勇者になりたかったんだ」
「勇者?」
唸る低音の中で、切ないメロディの高音が途切れたりまたは激しく鳴ったり。昭人さんは身振り手振りを大きくして、叫んだ。
「信頼できる仲間を連れ、揺るがない絶対的な目標を持って、その実現のために努力を惜しまず、何の恥かしげもなくみんなのために何かができる勇敢な人間になりたかった!」
テレスがまた手で空を撫でる。鳴り響いていたピアノ曲はいつしかオルゴールアレンジに切り替わる。
「いつから間違えたんだろうな? オレが欲しいのは女や金じゃなくて名誉だったのに。それから得られるはずのものだけを手当たりしだいにあつめて、結局、本当に欲しかったものから離れてしまった」
思わずじんときて唇を噛む。隣ではテレスが鼻水と涙をぐちゃぐちゃに垂らして泣いていた。
「あうぅぅ、演出のせいだ。演出がなかったらこんなのべつに感動シーンでも欠片もないんだ」「分かる。パチも演出で燃えてくるからな」
そうして三人でわんわんと泣く。どことなく懐かしいやさしいオルゴールの調べの中で。
音楽が止まったあとで俺たちの涙はさっと引いた。流れていたことが嘘だったかのように、肌の内部まで冷たく乾いている。テレスはしきりに首を傾げたのち「それ魔王でも通じるよね」とつぶやいた。
「魔王か……かつて《夜の魔王》で親しまれていたオレはかつて抱いていた夢を叶えていたということに?」
「そうなんじゃないですか」
「よかったね」
「そっかあ。よかったよかった」
しばらく三人でくすくすと笑いあってから、昭人さんは「おかげで心が晴れたよ。今なら何でもできる気がする……だからさ、ちょっとお金を貸してよ」と言った。
この世には救えない人間がいる。
幹人と初めて出会ったのは高校に入ってすぐのことだ、と俺は思っていた。新しい環境で緊張していた俺に、幹人はずいぶん親しげに話しかけてきた。明るいやつなんだなと思って、しばらく付き合っているうちに第一印象とは裏腹に穏やかで大人しい性格だと分かった。どうして話しかけてきたんだろう。ある日、幹人が俺の部屋で漫画を読みながら言った。『今さらだけど、月哉がいてよかったな』照れくさいなとからかうと、幹人は床に寝転がって壁の方を向いた。『ほら僕さ。中学のころ、不登校だったじゃん。みんながいない高校に進学しようと思ってきたけど、やっぱ一人でいるのは辛いなって思ってさ。でも月哉がいたから、今すごく楽しいよ』うわあ、現実に不登校の人間なんているんだ。俺がまず思ったのがそれだった。次に思ったのは己の薄情さだ。現実にいるんだ? いるだろうよ。中学のとき、埃被った空席を見ていただろうが。ニュースじゃ引きこもりなど不登校など特集しているだろうが。なあ? なんで俺は知っていながら知らないんだ?
知らなくても、いつの間にか救えた。それは違う。幹人が勇気を出して学校に来て俺に話しかけたからだ。勝手に救われただけで、俺は何もしていない。
知らない人間は、救えない。
昼食を食べようとコンビニに行ってばったりと陽子に会った。血の気の失せた顔で陽子は「ちょっと待ってて」と言った。俺とテレスは袋を持ったまま、店の前で待った。テレスは目前の道路で行き交う車の臭いを嗅ぎながら「アスファルトって臭いんだね」と呟く。自動ドアが開いて人工的な冷たい空気が首を掠めた。陽子はいつの間にか俺たちの前に立っていた。
「どうして嘘をつくの」
「兄も学校から抜け出したい季節がある」
「どうして嘘をつくの」
陽子は地を踏み締めるように力を入れていた。拳を作った両手は身体が前に倒れないように下に向けて強く伸びていた。「なんで」声が裏返ったのを隠すように、唇を一度噛んだが、それでもずっと震えていた。陽子は一度俯いて、すぐに顔を上げた。
「まだ帰ってきてないの。電話が鳴らないの。何度も何度も見たのに、メールも来ないの。インターネットを見たけど、事故、とか、それらしい情報は何もなかったの」
しばらく待ってみようと俺は提案した。彼らは幸福のために足止めされているだけだとは説明できなかった。だれの幸福のためか? そう聞き返された瞬間、俺はここにいられなくなるからだ。
長く吐く息の音が、途切れたと同時に陽子は俺の腕を掴んだ。
「家族を心配しないで、学校にも行かないで、兄貴はいったい何をしてるの? それはそんなに大切なことなの? 今、やらなければならないのことなの? 優先しなきゃだめなことなの? かけがえのないことなの?」
手を振り払って、俺はテレスを呼んだ。むにゃむにゃと目をこすりながら、悪魔の親戚は微笑んだ。
「どうしたんだい、月哉。今は妹さんの質問に答えるべきじゃないかな」
「こいつをしばらく家で眠らせたい」
何を言っているの、と陽子が聞いた。答える間もなくテレスが訊いた。
「いいよ、ボクは善の奴隷だからね」
今、困っている人はどこにいるだろう。テレスの頭に棒を突き刺してダウジングをした結果、俺たちは服屋の下着コーナーに辿りついていた。
「できれば身に着けてほしいんすよねえ。使えるものでもいいけど、食べ物みたいに消えちゃうのって悲しくないっすか」
そう語るのは大学生のヤスオ君である。社会人の彼女にプレゼントを贈りたいそうで、ひとまず下着コーナーに来たはいいが。
「大きさとか分かんないんすよねえ。揉んどけばよかったなあ」
と悩んで壁一面の花畑から動けなくなったらしい。
「女性客が入らないと女店員が困っていますよ」
「べつにそんなの気にしないでよくないですか。確かに彼女のために下着を選んでいる男の隣で自分用の下着を買うのは勇気がいるかもしれないですけど」
テレスは下着を手に取っては戻して「アクセサリーなんてどうだい。ボクのおばあ様はおじい様から手錠や首輪をもらって嬉しかったと言ってたよ」と呟く。「手錠はちょっと恥ずかしいですよ。変態と思われるじゃないですか」と言いながらヤスオ君は女性下着の裏側をまじまじと見ていた。
「そもそもプレゼントを贈るきっかけは何なんですか?」
「あのね、先月ぼくの誕生日があって。それでプレゼントをもらったら、すっごく嬉しくって。彼女のことも嬉しがらせようと思ったんすよ」
それはだめだよ、と答えたのはテレスだった。下着を商品棚に直して、両腕を組んで大きく首を横に振っている。
「いいかい。君が彼女からプレゼントを一個もらったとする。そうしたら君がプレゼントを贈っていいのは一個までなんだ。この均衡が崩れる時、愛もまた失われてしまうからね。だからもし、今、君がプレゼントを贈ってしまったら、彼女の誕生日には何も出せない! そうすると、いくら一個ずつ与え合ったとしても、彼女だけ一個分足りない状態になってしまう」
「ちょっと分かりません。どうして足りなくなるんすか?」
「だったらこういう考え方をしてみるといいよ。誕生日を祝うこと自体が一つのプレゼントなんだ。でもこれは単純に一個や二個として数えられるものじゃない……お腹がぺこぺこだから、その林檎を分けてくれと頼まれたとして、その林檎は今、分けてあげなければならないんだ。もし明日や明後日に新しい林檎やもっと良い苺を持ってきたとしても、埋め合わせは出来ない」
ふとテレスと目があった。が、すぐにヤスオ君の方を見て「だから」と続けた。
「どうしても何かを与えたいなら、本人にきちんと気持ちを伝えて聞けばいいんだよ。つながりのある人たちだけが、今、欲しいものを与えられるんだから」
ヤスオ君は目を輝かせて何度もお礼の言葉を述べてテレスの手を握った。にへにへと中途半端に喜ぶテレスの表情を見て、握手ぐらいで……と笑っていると、そういえばテレスの手をきちんと握ったことがないと思い出した。ヤスオ君は何度も振り返って会釈をして、結局何も買わずに店を出てゆく。その背を見送りながら、俺はテレスの脇腹を突いた。
「自信ありげに助言していたけど、大丈夫なのか」
服屋を出る途中、テレスは偶然に見つけた鏡の前でくるくると回った。
「大丈夫だよ。ボクはこう見えても、何もツイてないんだからね」
早く、今すぐに、出来るだけ多くの人を助けたいと思っていた。それなのに、俺はテレスに頼んでヤスオ君を追いかけていた――目には見えない、透明人間として。
平日夕方公園。ヤスオ君は何度も時間や新規メッセージを確認して、ベンチから立ち上がったり座ったりしていた。俺たちは透明人間であることを良いことに、彼の両脇にぴっちりと座っていた。テレスはいつからか口数が少なくなり、俺も何を話してよいのか分からなかった……どんどん暗くなってゆく公園から、二人の親子が去ろうとしている。母親と手をつないだ女の子が、ちらちらと振り返って砂場を見ていた。今でこそ何も残ってはいないが、それでも何もしなかったわけじゃない。少女は今日、山やトンネルを砂場に作ったんだろう。その感想を母親に聞かせながら、家に帰るだろう。
今、父と母はどうしているんだろう。
今、陽子はどんな夢を見ているんだろう。
耳に息を吹きかけられた感覚ではっと気づいた。テレスが顎で指した方向を見ると、女性を抱きしめているヤスオ君がいる。彼は頭を小さく横に振って、よくよく見ると彼女に頬擦りをしていた。摩擦のせいか、夕日のせいか。二人とも頬が紅い。
「行こうか」
テレスに声を掛けられて、俺はやっと彼らから離れる。公園を出てテレスととぼとぼと道を歩く。
「ボクはそれでいいんだと思うよ」
道の固いでこぼこに注視していると、隣でつぶやかれた。
「実現するかしないかは、もはやどうだっていいんだ。ただ相手のために、実現しようとする心が大事なんだよ」
だから、とテレスは言いかけた。それが続かなかったのは、きっと俺が立ちどまってしまったせいだ。テレスは少し進んだあとで、振り返った。
「キミ、なんで泣いているの?」
「思い出したから」
二人の抱きついたシルエットは今も視界にこびりつき、目を閉じれば光のシルエットとして姿を現す。愛だ。そうだ、愛だ。すべては愛のためにやろうとしたことだったのだ――。
いつ自分の存在に気付いたのか、よく覚えていない。いつ愛が芽生えたのかもまた、よく覚えていない。だけれどそれに気づいた時の衝撃は、発作的に蘇る。
俺の身体の一部は野菜からできておりこの野菜を調理してくれた妹からできており(妹が料理をするようになった理由のおばあちゃんからできておりおばあちゃんはお煎餅からできており)妹が野菜を購入してきたスーパーからできており(ボロスーパーの経営を支える消費者や経営者からできており)スーパーに野菜を卸した業者からできており業者が産地まで運んだトラックでできており野菜は農家の人々からできておりできておりできておりできておりできており――俺の身体は俺なくして成り立つが、俺以外なくして成り立ちはしなかったのである。俺は泣いた。ソファから転げてテレビに釘付けになって泣いた。テレビの台にしがみついて。膝立ちで。俺は呻いた。わめいた。泣き叫んだ。愛よ、愛よ、愛よ。俺は彼らの善意で生きている。彼らの愛を蓄えて育った。だが、この俺のザマはなんだ? 一つとしてその愛を他に還元できたのか? ただ与えられる愛に肥えるばかり。世には愛にも飢えている人がいるのに。リモコンを。虐待死。まだまだ小さい子どもが餓死して亡くなった。切り傷、かすり傷、火傷の痕。その子どもに愛は与えられなかった、本来は愛を与える側の両親もきっと愛がなかった。愛を持っていないから、愛を与えられなかった。なら俺は? 愛されて生きながら、だれも愛せていない俺は? リモコンを。殺人のニュース。リモコンを。戦争。リモコンを。経済的不安を抱えた人々。リモコンを。アニメ。
こうしてだれかが苦しみ喘いでいる時間は、妹の料理を待つ間にだらだらと頬杖をついている俺の暇つぶし時間となる。
だめだ。それじゃだめだ。愛をだれかに与えなきゃ。だれかを救わなきゃ。だれかが哀しいのに、笑ってなんていられない。世界のどこかが不幸なのは、俺の身体のどこかが不調なのと同じだ。
俺は世界で出来ている。俺は俺のために、世界のすべてを幸福にしなきゃならない。
「大袈裟だなあ」
テレスはじろじろと俺を見た後で肩をすくめた。
「ボクはキミの悩みを数言で解決できるだろうけれど、キミは納得しないだろうね」
「なんだと」
一歩ふみこんだ俺にびくりともせず、テレスは腕を腰にあてて不敵にふんぞりかえる。
「世界のすべてを幸福にすると言う。しかし、もともとキミの世界はそんなに大きいものだったかい? 本当は、もっと手に収まる範囲が世界だったんじゃないか?」
テレスは俺の前に両手をつきだして、拳を開いたり閉じたりした。と思うとテレスの方から俺にぐんぐんと近づいてきた。
「もしくはこうとも言える。手に収まらない範囲のことなんて、そもそもキミの世界にあることじゃない」
「そんなことない! 現に俺はだれかが苦しんでいることを痛いほど知っているし、テレス! 君のおかげでその人たちを少しでも救えたはずだ」
「そう。ボクのおかげで、ボクがいたからね」
「ああ、君は奇跡の塊だ。本当に君には感謝している……」
俺はテレスの手を取ろうとしたが、テレスはその手を払った。
「そうだ。ボクはかなしいぐらい奇跡なんだよ、月哉」
今まで踏みつけられてきたとは思えないほど、きっぱりとテレスは続ける。
「ボクのこともそうだけど、まったく困ったものだよ。キミたち人間の情報伝達技術の発達にはさ。おかげで、知り得ないものを簡単に知り得てしまう。世界を広げてしまう。本来ならば自分の周りにありえないものを自分のものに数えてしまう。悪い例があると知り、その例のようになりたくないと怯える。恵まれている人がいると知り、その人を妬んだり基準にしたりする。不幸な人がいると知り、自分の夢も何ももたないのんきに生きている少年がその罪悪感を払うように正義に燃える」
「じゃあなんだ。知らないままでいた方が良かったって? 何もしない方が良かったって?」
「言ったじゃないか。キミのその心はとても大切だよ。仮にそれが進路も特に決めていない焦りからの逃避だとしても、だれかを幸せにしたいと奔走する心はかけがえのないものだ。でもね、それは現実に何かを失ってまで実現するべき理想でもない」
友とまったく似ていない彼女を前に、友にまつわるかつての教訓を思い出す。
知らない人間は、救えない。
「俺には知らないことが、いや、知ることができるのに知ろうとしないことがたくさんある。クラスで暴れているやつがいれば、きっと止めに入っただろう。みんなの迷惑で悪いことだから。だけど一人で引きこもっているやつのことは気に留めないだろう。特に俺も、みんなも、目に見えて困るわけではないから。一見は個人で解決すべきことに思えるから――でも、だけど不登校がそいつだけの問題じゃないってことが分かってきた。そいつだけが悪いんじゃないって」
「周囲の人間がそうさせているってこと?」
「違う。悪いことをはじめることは、一人でも出来る。だけど悪いことが継続するのは周囲の人間にも責任がある。ずっとだめな人は、本人だけでなく環境が悪い。周囲の人間も助けにならない。だから外から救い出さなきゃいけないんだ。世界の違う人間が手をさしのばさなければダメなんだ。そうしなきゃいつまでも改善しない」
「改善するというのはキミ側の善だ。環境がそうさせるのなら、それもまた一つの善かもしれない。生き物は環境に適応してはじめて生き延びることができるからね」
それに、とテレスは俺から少し離れその間際につぶやいた。
「だれしもがキミと繋がって生きているわけではないよ」
「繋がる」
「奇跡があればね」
声は冷淡さを増し、彼女は進行方向を向いた。
「そしてキミは、たかだかありえない奇跡のためにありえるものを犠牲にした」
「何の話だ」
「見てみる?」
テレスはそうして歩き出す。俺はそれについてゆく。決して並んで歩くことはない。テレスの背を追いかけて、追いかけて。急いでいるわけでもないのに、やたらと息が苦しくて疲れる。俺がしようとしていたことは何一つ間違えていなかったはずだ。みなが幸せになることのいったい何が間違えているというんだろう。間違えているんだろうな。間違えているから神様とやらは正しく人を不幸にするんだ。
「許せない」
小さな呟きを聞き逃さなかったらしい。少し和らいだ口調でテレスは言った。
「許してあげなよ。幸せを望むなら。だれだってなんだって許されたいに決まっているよ」
道を歩いているうちに、辺りはすっかり真っ暗になっていた。それでも進むにつれ、どこに導かれているのか分かってきた。手が震える。次に足が。歩幅は小さくなる。それでもテレスは迷うことなく先に進む。まるで我が家に帰るみたいに。
その人は扉の前で立っていた。俺たちの足音に急いで顔を上げて「ああ」と漏らした。彼女はよたよたとこちらに近づいて「知りませんか」と聞いた。何のことを問うているのか、聞くまでもなかった。「幹人が帰ってこないんです……月哉さん、知りませんか」
ゆるしてください。俺は跪き、乞おうとした。現実にそれができなかったのは、俺があまりにも醜いからだ。
「もし幹人から連絡があったら、教えてちょうだいね」
おばさんは大きな音を立てて扉を閉めた。俺はそのまま立ち尽くしたあとで、踵を返してテレスの元に戻ろうとした。でも数歩で軸がぐらぐらとしてきて、駆けつけたテレスがいなければ倒れるところだった。
「帰ろうか」
「ああ」
ああ、ああ。だれかの味方になるなんて漠然とした目標をかかげて、それで満足したっきり。
歩いてきたはずだった。疲労は確かにあったし、振りかえればおそらく道程を確かめることができた。しかし俺は進むことも戻ることも出来ず、道の真ん中に座りこんだ……ふれくされて垂れ下がった俺の腕を、テレスが渾身の力で引っ張り上げた。
「キミは言う。遠い愛の方がより強いと。弱い愛こそが強みなのだと。だけどボクは思うんだよ。強さのためにすでに浸透してしまったような大きな愛を捨ててもいいのかって」
夕色の眼光が俺の背景まで捉えようとしている。俺の魂は今にも貫かれようとしている……。
「その愛は少しずつ、たんねんに、磨きあがれ、大きくなっていった。かけがえもないキミに捧げられてきた。それをまるで当たり前や常識みたいに投げ捨てて、だれかの弱き愛に感動するという。弱き愛に踏み込んで満足するという。キミは本当に馬鹿だ。大ばか者だ。どうして見知らぬボクなんかのために、キミの大事な友達を捨ててしまったんだ? 見知らぬだれかを救うために、キミの知っている人を犠牲にしたんだ? 近くの人もろくに愛せないのに、なんで遠くの人を愛せるっていうんだ」
こみあげて、しゃくりあげそうになる。
理想のために大事にできなかった家族や友達。還元すると言って、本当に与えてくれた人たちに何もしてやれなかった。
でも……。
「でも今はもう、君も近い存在なんだ!」
「ばかだねえ。ボクは悪魔の親戚であって人間の友達じゃないよ……だけど、うん。そうだね。時間だけは裏切らないからね」
「そうして俺はどれだけの時間を裏切ってきたんだか!」
「挽回できるよ。キミがそうしたいと思ったら、いつだって」
テレスが俺の手を握る。ああ、はじめてだ。ようやくはじめてテレスの手をとった。細くてすべすべして柔らかい手。なんでそのことに疑問をもたなかったんだろう。こんなに近くにいたのに、手さえ触れあわなかったなんて。
「キミが近くの人をきちんと愛せるようになったら、また遠くの方をみてほしい。二人してその甘い奇跡を信じよう。それは遠くて、弱いけれど。でも確かにボクとキミはつながっている」
目を覚ます。光が急に射したようで視界がぼやけている。何かがどたどたと近づいてきて、俺の視界にぬっとあらわれる。
「おいおい、頼むよ月哉。部屋主が寝ていたら恐縮するじゃないか」
やがて鮮明になってきた。見慣れたいつもの冴えない顔が俺を不安げに眺めている。ああ。
「幹人!」
「うわっ、な、何?」
身体を起こして、友を固く抱きしめる。傍にあるもの、手元にあるもの、それだけが俺の世界だ。
「おまえのこと、絶対に幸せにするから。ずっとずっと幸せにするから……」
「うぇっ? お、おお……よ、よろしくお願いします?」
さて、なぜか顔の紅い友をつき飛ばし、階段を駆け下りて俺はダイニングに向かう。すでにいい匂いが立ち込めていて、エプロンをつけた妹が覗きに来る。
「なんなの、急にどたばたして。幹人さんは?」
「幹人はいるぞ!」
「うん? そりゃね、さっき兄貴が寝ているって言ってたけど、幹人さんはそこで勝手に帰る人じゃないし」
思わず陽子の頭に手を伸ばして、そのままくしゃくしゃと撫でる。反射で文句を飛ばした陽子も、俺の顔を見てばつがわるそうに、それでも微かにつられて笑った。
「陽子、せっかくの休みだしさ。明日は幹人と明梨を誘って一緒に遊びに行こう」
「え、うん……明梨さん、喜ぶと思うよ」
「おまえは喜んでくれないのか?」
ぷいっと顔を背けた。だけれど角度が変わっただけで、口元はそのままだった。
「そんなの、決まってるの」
四人掛けの椅子に父と母、妹と俺が座っている。学校に行けば幹人と会うし、道の途中で明梨に声を掛けられる。そこには理解を越えたことも、魔法も存在しない。でも発見したことを言いあって、相談したりされたりする、少しずつ進んでいることを互いに知っている、この当たり前の連帯にふと感動してしまう。
ときどき、ひどく俺は世界の外を覗きたくなる。自分の手には届かない地球の裏側や横っちょに行ってみたいと思う。きっと歳を重ねてお金が貯まればどうにかできるだろう。そういう時代になった。俺たちはいつでも近くになれて、遠くになれる技術のもとで育っている。その一方で、手と手が触れあうことはまだまだ難しい。
雑踏の中で。
たくさんの人にすれちがう。その人たちは、その人たちの愛する人を幸せにするため、今日も俺とすれちがう。
自分の手でそのすべてを救うことは無理だ。でも、それでいい。ここにいる人すべてが、ただ一人でも己の隣人を救えたのなら全世界は幸福になる。
俺もそうする。ここから早く帰って近くの人を幸せにしよう。
できるかぎりのことを。愛で、愛で、愛で。どうかあなたを幸せにできるように。
ふいに指を絡め取られる。
振り向いて、思わず立ち止まる。通り過ぎる人は俺たちを一瞥しながらも避けて進んでゆく。無関心の濁流に押し流されぬように、知った体温だけが俺を繋ぎとめている。どうにか笑おうとしてこわばる。瞬きをこれ以上しないように凝視する。何か言いたかったのに震えた唇を噛む。俺が君に言いたかったのは、ただ、ただ――。
ただ、そこに愛があった。
それだけの話だ。