ホワイトバランス
男子大学生が知らない相手と文通リバーシをするオンライン小説です。
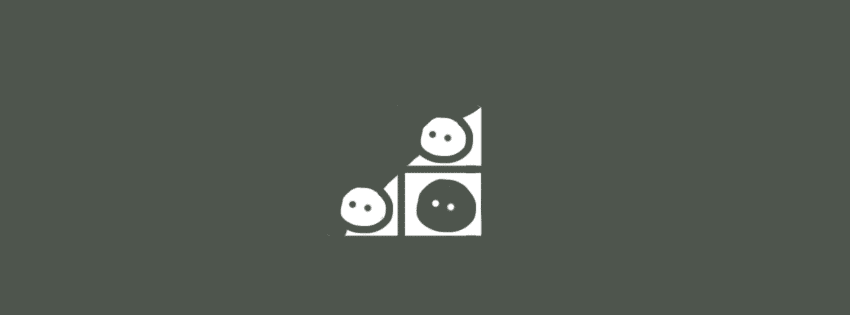
気持ち柔らかな緑の盤に黒の格子が走っている。盤の両ふちに縦に並べ置かれた石をつまみ、黒、白、黒、白、と指のなかで転がして視線をずらす。その先には一枚の写真がある。中央にぎっしりと、端には掛かっていない盤面がそこにある。お手本を真似するように石を一個ずつ配置してゆく。ぱちん、ぱちん、ときどき間違えてぱたぱたと裏返し、ようやく現像されたそれを眺めて、白の数が多すぎると確浦衡平は考える。
震えながらに掴んだ黒をぱちんと端において、その隣に連なる白を指の腹でそっと起こす。一個、二個、三個。こたつ布団で手汗を拭いながら、その仕上がりを一望する。バランスが良くなった。興奮と達成感が微笑に現れた。そのまま盤のすぐそばに置いていたデジタルカメラを手にとって慣れた手つきで操作する。すでに百の試行があった。いつも白が舞台を支配し、黒は散らばり悄気ていた——シャッター音によって我に返った確浦は液晶モニターに顔を近づける。盤が枠内にすべて収まりきっている。
カメラから取り出したメモリカードを握りしめて確浦は立ち上がる。
集荷時刻を記した白のプレートは暗く薄汚れていた。プリントした写真を封筒に素早く収めて、ズボンのポケットから液体糊を取り出す。しわがよるぐらいに塗りたくって封を閉じる。宛名と差出人を用心深く確認して、小銭入れから拾った切手の裏を舐める。封筒の表に貼り付けて、ポストの差し出し口にこれをおそるおそると投函する。
今日には集荷され、明日には運ばれ、明後日には辿りつき、一週間後にまたやってくるはずだと確浦は歩き出す。
「美人だといいな、その文通相手」
ざわつく講義室に、期待のにじんだ明るい声が響いた。確浦はまじまじと豆本の顔を見つめたまま、パンにかじりつく。
「何見てんだよ」
「いや……なんでおれの文通相手が美人だと良いんだろうと思って」
豆本はわざとらしく目を見開いて、机をバンバンと小刻みに叩いた。
「僕は思うんだが、君とそのやりとりの主は何らかの強い縁で結ばれているぞ。何故って、今どきオンライゲームで出来るようなものを、それでなくてもメールで写真を添付してやりとりすれば良いものを、というか直接会ってやっておけばいいような遊びを、わざわざ写真に撮って、プリントして、郵送してやりとりするような馬鹿は君とその人ぐらいしかいないからだ。君と同等の馬鹿に恋できるチャンスは今しかないぞ」
うんうんと頷きながら確浦は空になったパンの袋をくしゃくしゃにまとめて、ビニール袋に放り込んだ。
「美人以前に、性別が女かどうかも分からないし」
「あて名を見れば分かるだろ」
「傍島翼」
微妙だな、と呟いて豆本は何もない机で石をひっくり返す真似を始めた。
「そもそもネットで知り合ったんだろ。何で文通なんだ。とんだミステリーだ。白と黒で遊んでいる場合じゃないぞ、君」
「伝達手段が何であれ、遊びの内容は変わらないし」
「何であれじゃないんだよ、君。何であれじゃ」
ぶつぶつと文句を垂れる友の姿を見て、確浦は腕を組んで静かに俯く。
「白黒を付けることにこだわっていると、大事なことを見逃すものだ」
豆本は空気を弾く手をそのまま確浦の顔に近づけて、ぱちんと額を叩いた。
「それは君にぴったりの警句だ」
コンピューターを相手にして石を打つ時、確浦はふとして手を止める。本当にコンピューターなのだろうか。じつは生身の人間が相手をしていて、自分が石を打った同時に急いで応答しているのではないだろうか。疑念を晴らすべく、次の手に移るのを遅くして、逆に自分の番になった瞬間に石を打ってみる。反応に差がないことを何度も何度も確認して、ようやく確浦は座椅子の背に身体を預けて息をつく。自分が何もしなければ、何も動くことのないその画面をぼんやりと視界に入れる。だけど、と確浦はうとうと考える。生きているかもしれないのだ。死んでいるかもしれないのと同様に。
「おまえのいたずらかもしれない」
こたつの中に入ってぬくぬくとしながら、豆本は真向かいで頬杖をつく確浦の顔を見た。
「僕がなんでそんな無意味なことをしなきゃならないんだ。確浦、よく考えろ。封は綺麗だったんだろう」
「封筒を真似してやったという可能性もあるし」
「初めて見たんだからな、その封筒も写真の撮り方も。偶然一致させることなんて不可能だ。それよりもっと疑う相手がいるんじゃないか」
がくっと項垂れて確浦は指の圧で少し曲がってしまった一枚の写真を天板に投げ出す。
気持ち柔らかな緑の盤に黒々とした赤が散っている。変わらず走る黒の格子に閉じ込められる形で、確浦の送り返した盤面に赤の一石だけが投じられていた。
「変人の考えることは本当におかしなもんだ。負けるなよ。青い石でも置きかえしてやれ」
「だけど、今までこんなことはなかった」
「何かのメッセージかもしれんな。この赤の置き方を見るに、近々宇宙人でも降臨するかも!」
「茶化すなよ」
君たちのやっていること自体が現時代への茶化しなんだ、と豆本は鼻息を荒くして、出されてしばらく経った茶を渋い顔で飲み干した。
「相手にメールで質問すればいい。これはどういう意味なんですかって」
「ゲーム中は無駄なお喋りをしないようにと決めたんだ」
「先にルールを破ったのはそっちだろうって言ってやれ。赤い石なんて認めませんってな」
おろおろとして確浦は自分の手元にある緑の盤と、染みついた盤の写真を見比べた。
「もしかしたら、誤送かもしれないし」
「君はいったい何を言っているんだ」
友にギンと睨みつけられ、確浦は身体を小さくしてこたつの中に深入りする。視線をさらに落として、盤の横に備え付けられた石の、白と黒の境がはっきりと見えるその側面を見つめた。
「おれが誤った宛先に送って、だれかがこれを送り返した。もしくは、だれかが誤送したのをおれが送り返してしまった可能性もある」
「前にも言ったけど、こんな手間のかかることをする変人は君と翼さんぐらいなものだぞ。というか、その考えでいくと翼さんとのやりとりが途切れているってことになるけど」
「それは……困る」
「知らねえよ」
ため息をついて豆本はひょいと腕を伸ばし、開けられた封筒を摘み上げた。
「でもよ、これって翼さんの字と一緒なんだろ。住所も……あれ、差出人が書いてないな」
「それはいつもどおり。宛先とおれの名前しか書かない人なんだ」
「ふうん。誤送は置いといて、それじゃ宛先を間違えた時に宙に浮いちゃうな」
ぱたぱたと羽ばたくように手を動かす豆本を恨めしそうに見て、確浦は写真を指で自分の目前にまで寄せて、盤の石に手を掛けた。
「えっ、やんの?」
「何が起きてもルールだけは変わらないんだって、おれは信じている」
「ああ、そう……で、赤い石はどうすんの?」
「無視するよ。だって黒で挟めないし」
確浦衡平が小学四年生になったころ、全教室に紙製の郵便ボックスが設けられた。配布された紙を切り取り、クラスと名前を書いて投函すれば、次の日にはその相手に手紙が届く。大して親しいわけでもない下級生に、ただ手紙を投函したいという理由だけで手紙を書いていた。確浦はさらに思い起こす。しかし確認しなかったのだ。出すだけで本人に届いたのか、きちんと読まれたのか、一瞬も確かめなかった。一通だけ来た返事は当たり障りのない文面で、それは仮に違う手紙を読んだとしてもそうなるだろう文章だった。
——本当に通じていたのだろうか。
小学五年生に上がるころには、手紙を送ることもしなくなり、郵便ボックスが撤去されていたことにはいよいよ気づかなかった。
気持ち柔らかな緑の盤に黒々とした赤と人間の指が散っている。変わらず走る黒の格子に閉じ込められる形で、確浦の送り返した盤面に青の一石だけが投じられていた。
「今回は勝てるかもしれない」
確浦の言葉にはっと目がさめたようにして豆本は悲鳴を上げた。ぎょっとする友から写真を奪って、指さしながら叫ぶ。
「君、指、指、これ、人間の……ばらばら……指!」
「豆本のいうとおり、翼さんのいたずらかもしれないね。写真編集ソフトでも使用して作成したんだと思う」
呆ける豆本から写真を奪い返して、確浦は盤をなぞりながら呟く。
「赤と青は少なくともおれの石として勘定されないだろう。だから今までどおり黒を置いていかなければならない。赤は挿めないけれど、青なら挿める。赤もいつか白や黒に変わるだろう。そうしなくても赤や青といった新しい色が盤面を支配することはないのだから、最終的には残った白と黒の色を数えればいい。それで勝ちか負けかは決まるし、問題はないよ」
そう言って写真の通りに盤面を作り上げてゆく手つきを、豆本は恐ろしさから目を離せぬといった面もちで目を見張っていた。ぱちん、ぱちん、ぱちん。準備が整った舞台を見下ろして、おや、と確浦はたまらず声をあげた。
「形勢逆転かな」
まったく手の進まない教え子を背に、漫画棚を物色しようとしたところで確浦衡平は寄井永に声を掛けられた。
「先生、ちゃんと見ててくださいよ。僕の成績が上がらなくて困るのは……僕ですかね?」
「うん。おまえだ」
寄井はペンを勉強机に転がして、座ったまま椅子をくるくると回し、漫画棚から素早く退散して隣に戻った家庭教師の顔を上目でみつめた。
「先生はいいですよね。見知らぬ女の子と文通をしたり、家庭教師のバイトをしたり。僕も血の指レターが欲しいんですけど」
「それは来年にでも置いておこう。とはいっても、少しは息抜きがないとな」
「そこまで心配してくださるとは、なんてハートフル! でもご安心ください。息抜きならありますよ」
教科書の並ぶ机上の棚から一冊のノートを取りだした寄井は、広げていた参考書を脇に寄せてちらちらと確浦を見た。
「どうしよっかなあ。見せましょうかねえ」
「見せなくていいから勉強しよう」
寄井はにっと笑って、ノートを机の上で開いた。
「一般的な息抜きとはまた違うかもしれないんですけどね。事実にしたいことを書いているんですよ」
「合格後にやりたいこととか?」
「もう先生、受験のことはちょっと忘れてください。これは僕に美しい姉がいるって話ですよ」
「いないだろ?」
「だから既成事実にしたいんです」
口をあんぐりと開けた確浦に対し、寄井は右手でリズムを取りながら思い起こすように語りだす。
「自分、ビートルズって会ったことがないんですけど、たぶん存在していたんですよね。音楽が空気に残留しているし。第二次世界大戦もちょっと参加しなかったんですけど、ありはしたんですよね。そう記した文章を見たから。その理屈でいくと神様もいると思うんですよね」
「はあ」
「逆に、逆にですよ。本当はなかったことをあったことのように書いてみんなに共有しておけば、最初のうちは信じてもらえなくても、時が経ったら本当にあったかのようになるんじゃないかって思いまして」
僕はそういう精神を大切にしていきたいんですよね、と胸を張る寄井の背をばしばしと叩きながら、確浦は未だポストの底に入ったまま回収されていないだろう手紙のことを思いやる。
「みんなに信じてもらえなくても、おまえ一人が姉の幻覚をみて満足すれば済む話だろ」
「いやいや先生、それで済むならビートルズも第二次世界大戦も神様も個人の空想で終わってしまうわけで、だけどそうやって閉じてはじめて心が落ち着くのは、そんなの、ただのビョーキです。自分の好きなものが現実に共有されてはじめて正気でいられるんです。実在しない姉のことを暗い部屋でひとり想いつづける僕は狂人ですが、僕以外の人間が僕の姉のことを少しでも信じてくれたら、実在しない姉のいる僕は正気なんです」
確浦は寄井の口調がだんだん熱帯びてくるのを聞き流しながら、分厚い参考書をぺらぺらとめくって、数字と文字と図形が飛び交っては重ねられ去ってゆくのを始まりから終わりまで何度も繰り返し眺めていた。
「僕の姉はですね、先生。美しくて残忍な人なんです。僕がはじめて僕に気付いた時、姉はまだ小さい僕の手を金槌で叩き割ろうとしていました。もちろんそれは実際に行われなかったので僕の手は受験勉強に役立てられているわけですが、もし飼い犬が吠え立てなければ彼女は容赦なく僕の指先から手首まで隙間なく金槌を振り下ろしたでしょう。僕の手の恩犬とも言える彼は、僕が小学三年生の頃に死んでしまいました。姉が面白がって洗剤をたくさん飲ませたのが死因だと思うのですが定かではありません。なぜならあらゆる犯罪においてよくあるように、加害者が己の犯した過ちを隠したからです。だから家族や近所の人たちの間では、犬はひとりでにふらふらと出かけてから戻ってこなかったという話になっています。本当のことを知るのは姉と僕しかいません。だけどお分かりのとおり、姉はそのことをだれかに話しはしないし、僕が話すにしてもそんなおそろしいことだれも信じてくれないでしょうから、犬は真偽に問わず失踪していて、心の優しい母なんかはあの犬もだれかに拾われて可愛がられているだろうと生存すら考えているのです。もう死んでいるというのに! だけどこれは世間の人々や母が愚かだというわけではありません。むしろ現状況で最も愚かなのは僕なんですよ。仮に犬の死が事実であろうと、死体を蹴って確かめても、本当に少しも生きていないかと刃物で切りつけてみようと、切りつけて確かめた痕を隠すためにさらにでたらめに切断してみようと、誰も信じてくれないなら犬の死なんてものは幻想に過ぎないですからね。流れた血の生ぬるさなんてものは、説得力を前にして説得力を失うんです。ねえ、先生。先生だって馬鹿げていると思いますよね?」
語尾がわずかに上がったのに反応して、確浦は参考書を弄ぶ手を止めて顔をあげた。
「高校生のころ、痴漢を見たことがあって」
「えっ、突然なんですかその話。すごく気になります」
俊敏に姿勢を正した寄井に、確浦は固い笑顔を作って椅子に深々と座り直す。
「見たことがあるといっても曖昧だけど。おれの目前に座っている女の子が、隣のおじさんに太腿を触られていたんだ」
「そんな大胆な痴漢というものがあっていいんでしょうか?」
「おれもそう思って、つり革を持ちながら見下ろしていた。二人はもしかしたら恋人同士なのかもしれない。歳の差が離れているだけなのかもしれない。これから仲良くなるのかもしれない。色々なことを考えて、おれは彼女と目があった。数秒ばかり沈黙があって、彼女の方から目を逸らした。おじさんはその間も太腿を撫でまわしていて、滑りだす様にスカートの中に手を入れ始めた。彼女は俯いて、唇を震わせているように見えた。当時から視力があまり良くなかったから、気のせいだったかもしれない。おじさんの手の動きが激しくなって、その上に被さるスカートが荒れ狂った。布をひっかく音とおじさんの息が電車の音やアナウンスを上回った。だけどそれはおれが音楽を聴いていなかったからかもしれない。彼女は手に抱えていた黒い鞄で膝を隠すようにした。おれから彼女のスカートの中が見えなくなるだけで、布の擦れる音はまだ続いていた。でも実際は終わっていたのかもしれない。やがて水音が響いたとき、電車が目的地についた。おれは立ち去る前に視線をあげて、やっと彼女がこちらを見ているのに気づいた。こちらではなくて虚空だったかもしれない。彼女の口が音もなく動いた。焦りで見間違えたのかもしれない。い・か・な・い・で。勢いよく手放したつり革が遊びもなく平常に戻るのを横目に、おれは電車を降りた」
「そして続くんでしょう——本当は今も降りてないのかもしれない」
「英語で言うと?」
「勉強の話はやめましょう。僕たちは勉強の話をするために集まったわけじゃないはずです」
そんなことない、と確浦は否定しようとして口ごもった。寄井は確浦の隙をついて机の上にある参考書をベッドの上に投げつけて、ほっとした息をついた。
「先生、僕にもっと貴方の話を聞かせてください。ひょっとすると、失踪してしまった僕の姉の手がかりになるかもしれません」
「いついなくなったんだ?」
「僕が小学三年生の頃ですよ。みなは失踪したというし、母は親切な人に拾われたから大丈夫だというんですが、僕はそんなこと真実だとは思っていないんです」
ベッドに投げ捨てられ開かれたままうつ伏せになった参考書を見ながら、確浦は思い出したように頷いた。
「最近、豆本がおかしいかもしれない」
「豆本という方は女性ですか?」
「男友達」
「その話は来年にでも置いておきましょう」
真剣なまなざしに、確浦は教え子の頭をこつんと小突いた。
天板を覆うようにずらっと並べられた写真のうち一枚をとって、豆本は反射する室内照明の白を泳がせるように手首を動かした。
「誰が、どのように、何故このようなことを行ったのか。疑問のために大好きなビーフシチューすら喉に通らん。ここに来るまでは車に轢かれかけもした」
「深刻に考え過ぎだ。これはただのゲームなんだから」
ゲーム、と豆本は空ろに反復してから写真を持ったままぐるぐるとこたつ台の周りを歩いてゆく。
「抽象戦略ゲームを前にして、君はそれでも物事を曖昧にしたがる。いいか、君が熱心に勝敗を決めようとしているそのお遊びだって運命の手の施しようがないのさ。理論上では先読みできるんだぞ」
「おれも相手もあんまり巧くないから、理論は関係ないかもしれない」
歩いている途中で豆本はこたつの中に入っている確浦の背中を蹴って、被害者の非難から逃れるようにぐるぐるぐるぐると周回を続ける。
「色のついた石にだって何らかのメッセージが、暗号があるはずだぞ。そうでなければ、どうなる? どうにもならない。でもどうにもならないということをわざわざする必要があるか? そこには必然性が、合理があるはずだ」
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐぐぐるるると回り唸りつづける。
「動機があったはずなんだ。おまえと文通で遊びをやりとりしようと考えたのも。たとえばネットゲームだと相手が対戦中に切断ばかりしてくるのでうんざりしていたというような、そういう、理由が、ワケがあるはずなんだ! 僕がいざ問い詰めて、答えなければ顔面の皮をそいでやると顎から刃先を入れて拷問した時に一滴の血も流さずにいられるような、当然じみた釈明がある、あるものだぞ」
並べられた写真をそそくさと集めて束にした確浦衡平は、指でぎゅっと面を押してその厚みを確かめた。
「おまえを見ていると昔みた劇を思い出すな。木を前にして二人の男がだれかを待っているんだが、その待っているだれかはやってこない」
「アポリア……ああああ、僕は耐えられない。なんて不合理、なんて不条理! 歩いていればうんこにも当たると言わんばかりの君の態度、血の指、明らかな事件、盤面を睨み現実には何もアクションを起こさない君の態度、非日常が何気なく日常にすりこむように馴染んでゆく恐怖、来週にはその写真の指が僕の指になっているかもしれない、それでもきっと何事もなかったように石を盤に敷き詰める君の態度、態度、態度!」
言い切ったあとで豆本は立ちどまり、持っていた写真を確浦に返した。
「君は本当に何も気にならないのか? 少しは確認してみよう、それではいけない、そういった考えは欠片も浮かばないのか?」
「まあ、言われてみると気になるかもしれないし、でも、わざわざ聞いてみるのもどうかと思うし」
豆本は立ったまま見上げる確浦の顔を、目を見開いたままじっと見つめて、それから何も続かないのを悟ると確浦から顔を背けた。
「僕は、不安だ」
浮かない顔をしていますね、寄井の言葉に起こされて確浦はぐらつきながらも背筋をぴんと伸ばした。
「友達のことでちょっと悩んでてな」
「今、寝てませんでした?」
「最近、豆本がおかしいかもしれない」
「僕はもう浪人生ですか」
首を傾げる確浦に対し、寄井はやれやれと口ではっきりと呟いて頭を抱えるポーズをした。
「豆本は真実を知りたいそうだが、真実というものがまったく見えてこないので、はっきり言って発狂しているんだ」
「なるほど。事情はよく分からないんですが、僕の姉や先生の痴漢みたいなものですね」
「その言い方だと、おれが痴漢したみたいじゃないか」
そこまで言ったあとで確浦は指で唇をぎゅっとつまんで顔を少し俯けた。
「でもその通りかもしれない。何故かいなくなってしまった空想の姉、そこにいたかどうかもわからない痴漢被害者、すべてが謎に包まれているおれのゲーム相手……」
「もしかしたら、同一人物かもしれないですね」
寄井は家庭教師に顔をぐっと近づけて、暗い瞳の中に映る己の顔を見つめ返す。確浦も時を同じくして寄井の瞳の中にそっと過ぎ去った女の像を捉えて、大きな音を立てて立ち上がった。
「その案は最高かもしれない」
確浦衡平の言葉に寄井も立ちあがって、顔を興奮で紅潮させながらはきはきと答えた。
「僕、受験合格できますか?」
「その話は来年にまで置いておこう。それより同一人物説というのは豆本によく効くかもしれない。少しでも謎が収束すれば、豆本も安心して眠れると思う」
ベッドに行きましょうと誘った寄井に従って、確浦と寄井は狭いベッドでぎゅうぎゅうに横になって、固い枕の上で一冊のノートを広げた。
「本当は数学用のノートにするつもりだったんですけど、数学用のノートというのは結局、古典用にも地理用にもなるわけですから」
「おまえは良い受験生だな」
「僕、受験合格できますか?」
確浦は机から持ち出した寄井の鉛筆をノートの横罫線に沿って「寄井の姉」「痴漢被害者」「ゲームの相手」と書き並べ、それぞれの単語の間に「=」を付け足した。
「時と場合と空間によって、被害者は加害者にもなりうるということですね。現代文の勉強になります、先生」
「英語で言うと?」
寄井は確浦から鉛筆を奪って「寄井の姉」の二行斜め下に「失踪している」と書いてそれを線で結びつけた。
「このようにあらゆる情報を拾っていって、世の不条理をまとめて解決してくれる人を作りましょう」
「空白にぴったりはまるように」
「ええ、空欄にぴったりと丸になるように」
ついに玄関から動かなくなった豆本を引っ張ってなんとかこたつに入れさせた確浦衡平は、その対面にて足を入れてぬくみながらに切りだした。
「傍島翼の正体が見えてきたんだ」
豆本の暗い瞳にわずかな光が宿ったのを見て取った確浦は走る緊張で唇が歪みそうになるのを指で押さえながら、頭に浮かべた空想を噛み締めるように続けた。
「見えてきたというのは違うのかもしれない。見ようとしなかったものを、すでに知っていたが関係ないと決めつけていたものを、音の響きが違うからと紐づけることをやめてしまったものを、冷静になって考え直した結果、すべてのことは何かしらの意味があってそれぞれ影響しあっているかもしれないと至っただけなんだ。それで、おれはかつて彼女に手紙を出したことがあった。小学生四年生のころ、どうしても誰かに何かを書いてみたくて、宛先に彼女の名前を書いた。返事は来なかったけれどきっと届いたのだと思う。おまえに話していなかったかもしれない。高校生のころ、おれは痴漢を見かけたことがあった。その時の被害者が彼女だったんだ。まるで手紙の返事がやってきたかのような再会だった。でも正確にそれを痴漢だと言い切れなかったおれはそのまま逃げてしまった。その後、おれはコンピューターを相手にゲームをしていた。だけどそのうち相手がコンピューターではなく人間であるということに気づいた。あなたはだれですか? おれがそう問うと、彼女は傍島翼だと答えた。それからおれたちの文通が始まったんだ。だけどおれは知ってしまった。バイトで教えてやっている家庭教師先の教え子には非常に美しい姉がいて、彼の両親が離婚して苗字が違ったそうだから、詳しく聞くまでは気づかなかった——彼の姉の名は傍島翼。しばらく失踪しているらしい」
そうだとすると、豆本の唇が形だけを作ってそのまま閉じた。確浦はこたつの温度が低いことに気付いて、スイッチを「強」に切り替える。
「家族ですら行方の知らない人間と赤の他人が繋がれるなんて。でも、そういうものなんだ。手紙というものは一度でも往復しさえすれば互いの心が変わるまで自動的にやり取りが続くものだからだ」
時計の針の動く音が、向かい合うように掛けられた二つある壁時計と枕元に置いていた目覚まし時計とソファの上に転がしていた腕時計の音が、独立してまったく干渉することのない規則的な不揃いの音が、確浦衡平の早まる鼓動をさらに急かすように強まってゆく。
「返事を出したから返事がやってきた。それだけだ。もしおれが何も返さねば、盤面の指はこれ以上増えないだろう」
言い切って目を逸らした確浦幸平に、豆本は笑みをこぼした。
「だけど君は返事を出すんだろう?」
寄井は大きなため息をついて、ベッドの上に寝転んで写真集を眺めている家庭教師の背に参考書を投げつけた。
「優秀な教材は攻撃力も高いな」
「先生ってばあ、最近だらけすぎでしょ。僕の成績を上げる気があるんですか? ええ?」
確浦衡平は閉じた写真集を枕元に置いて、ベッドの上であぐらをかいた。
「おれが何かをしておまえの成績が上がるわけでもないからな」
「何のために家庭教師やってんですか、先生」
勢いから壁とベッドの間に落ちてしまったらしい参考書の背を見つけて、確浦はよく確かめないままその暗がりに手を伸ばし、何か違う感触に突き当たった。
「せめて先生が巨乳の美人だったらな。こう、先生がだらだらとベッドに寝転がっているのにドキドキしながら、それでも過ちを犯さぬようにと目前の課題に集中しようとして、出来ず、ついつい少しだけ振り向いて先生の方を見たら、むにゃむにゃと無防備に曝け出された先生の乳が見えてしまい、僕の成績が下落するというストーリーで」
ぬらりと滑ったそれに指が絡んだ確浦は、そのままそれを引き上げてゆく。
「巨乳でもなければ美人でもなければそもそも女でもない家庭教師が人の部屋でだらだらとエッチな本を読んでにやにやしているのに気を取られて僕の成績が下落するなんてストーリーは、これが、まったく、ナンセンスなんです。あるストーリーがあるからそうなるという自己分析ではなくて、自分という現在に合わせてどうしてそうなったかのストーリーを好きに選んで好きに捨てる、僕はそういうことを大切にしたいと思うんですよ、先生」
薄汚れた犬のぬいぐるみの赤黒く濡れた足をぶらぶらと持ちながら、室内照明に焼き付けるように、確浦はさらに腕を高くした。
「そう、先生が巨乳の美人であることもノートに書かないといけません。夢は願えば叶うし、情報は一冊のノートにまとめると良いらしいですし、買ってはいけないものは買ってはいけないんです。そういう道理があるんですから、僕も引っ込むわけにはいきません。先生はだらけてもいいかわりに少し譲歩なさって巨乳の美人になるように擦りあわせなければならないんです。三次元の女が二次元の美少女になるために、瞼を切り取るころから始めるみたいに」
ぶら、ぽた、ぶら、ぽた。
ぬいぐるみの頭から生えた黒い髪の毛が赤をしたたらせながら、確浦の遊び心に合わせて揺れている。
「先生だったらまずはそうです。身長が僕より高すぎるのはやっぱりどうかと思うから、足と胴体の方に切れ込みを入れて、もうちょっと短くするべきなんです。そうじゃないと僕が受験に合格して先生に抱きしめてもらう時、すごく恥ずかしい思いをするでしょう。切り取っていらなくなった部分は胸に使うんです。もちろん僕は先生の胸を揉むことはありません。だって血や肉が噴出してきたら流石の僕も気分を害してしまいますからね。それでそうだな。顎を削ったり鼻を低くしたりしないといけないですし、額の方も丸くしないと……でも性器だけは問題ありません。何故なら僕は先生と性行為をしないからです。プラトニックだからです。プラトンチックだからです。プラスチックだからです。僕のメンタルはあまりにもプラスチックなのでセックスがなくても想像だけで生きていけます。そう、僕は想像だけならすでに十回は大学に合格しているんです。もう先生より遙かに年上で社会人なんですよ、僕は!」
確浦はそのまま犬のぬいぐるみを壁とベッドの間に戻して、ベッドシーツに手をこすりつけて振り返る。
見下ろすようにして寄井永がベッドの前に立っている。
「ドーナッツ問題って知ってますか?」
「郊外に人が住んで中心部ががら空きになる……」
「受験勉強の話はやめてください。気が狂いそうなんです! ……ドーナッツを穴だけ残して食べるにはどうすればいいのか。ねえ、先生。僕たちは世の悲しいことや死刑のことより、こういうことだけを考えて生きていたいとは思いませんか?」
鼻と鼻がぶつかるぐらいに家庭教師に顔を近づけて、寄井永はその返事を待った。確浦衡平といえば教え子の息を数えながら、小さく首を横に振った。
「ドーナッツの穴だけ残しても、受験には合格できない」
だからその話はやめましょうよ、と頭を抱えて床に転げてのたうちまわる教え子を見下ろしながら確浦は指で宙に円を描いた。消える軌跡を辿って無い円の内側を見る。
「それぞれ別々の産地で他の人に食べられるはずだったドーナッツの穴々を偶然にもおれの人生という名の糸がくぐり抜けてしまったがためにドーナッツの輪ができてしまったのだとしたら」
「だとしたら?」
「おれは糸を断ち切ってドーナッツを返品するべきなのか?」
横に置いた写真を見ながら盤に石を置く確浦の対面で、豆本は大きな欠伸をして破かれた封筒に手を伸ばした。
「そろそろ見逃しきれないだろ。その混沌加減」
「最初はあまりひっくり返せなかった分、後半は有利になってきたから大丈夫」
「そのスプラッタ染みた写真を見て何も思わないのかい、君は」
確浦は石を掴んだまま静止して、改めて写真を見つめる。
気持ち柔らかな緑の盤にこびり付いたような赤が映えている。佳境となった盤面の邪魔にならないように端の方で切り取られた指が神経質に並べられており、石の色は定番の白と黒から赤、青、黄色と増えている。
「傍島翼の室内照明は白熱電球なのかもしれない」
「なんでだよ」
掴んでいた封筒をくしゃりと歪めながら、豆本は机を勢いよく叩いた。確浦はちらりと豆本の表情を窺ったあとで、盤面に戻る。
「全体が赤みがかっているから。昔、父に写真について教えてもらったんだ。色温度というのがあって曇りの日には曇りの色になるし、晴れた日には晴れた色になるって」
がくっと天板に顔面をぶつけた豆本はつい曲げてしまった封筒を開き戻そうとして、体を起こした。
「どうした?」
「この封筒、消印、ない」
行き詰まった課題を前に、確浦はキーボードをつたなくも懸命に打鍵していた。完成した文面に頷きながらメールを送信しようという段階にきて、頼ろうとしている友と連絡が取れないことを思い出し、別窓で開いている真っ新な課題と一緒に退ける形でノートパソコンを閉じる。
消印のない封筒に気付いてからも手紙のやりとりは数度続いた。が、ある時になってばったりと次の盤面はやってこなくなってしまった。確浦はいなくなった友と来なくなった手紙に思いを馳せながら、床にゆっくりと背をつけて寝転がった——と同時に、玄関のチャイムが鳴った。
玄関先に直接来た来訪者には対応しないように。一人暮らしをする際に母からしつこく言われた注意を呼び起こしながら、二度目のチャイムに急かされるように確浦は立ち上がる。
扉を開けた時、三度目のチャイムが鳴った。確浦はドアチャイムに伸ばされた人差し指の爪と皮膚の間に赤黒いものが詰まっていることを見つけたのち、来訪者に視線を向ける。確浦とそう変わらない背丈の来訪者は汗で濡らした封筒を呆ける確浦の方に差し出した。
封筒を受け取った確浦はその筆跡を確認したのち、ゆっくりと大きな声で相手に尋ねた。
「あなたは誰ですか?」
「傍島翼です」
遅くなってしまい申し訳ないとの旨を述べて、来訪者は一礼してすぐに確浦の前から立ち去る。その背がエレベーターの中に消えるまで立ちつくしていた確浦は直接届けられた封筒をひらひらと空気にさらしてから、玄関扉を閉じ、鍵も閉めずにこたつの方にばたばたと走り出して、盤を取出し、封を千切って、石を掴んだ。
すべてが終わった時、何故手紙がしばらくこなかったのかに思い当たった確浦衡平は、自分でも意図しないうちにふらふらと立ちあがって、コンピューターを相手にしたゲームのこと、届いたかも分からないかつての手紙のこと、教え子の存在しない姉のこと、痴漢被害者のこと、血にまみれた盤面のこと、豆本のこと、作り上げた犯罪のこと、そしてそんな些細なことに気を取られたがために、ある重大な偏りを見落としてしまったことに気がついた。
黒が占める盤面に、もはや白の置場はどこにもなかった。