ティッピングポイント
男子高校生がちょっとずつズレて戻れなくなるオンライン小説です。
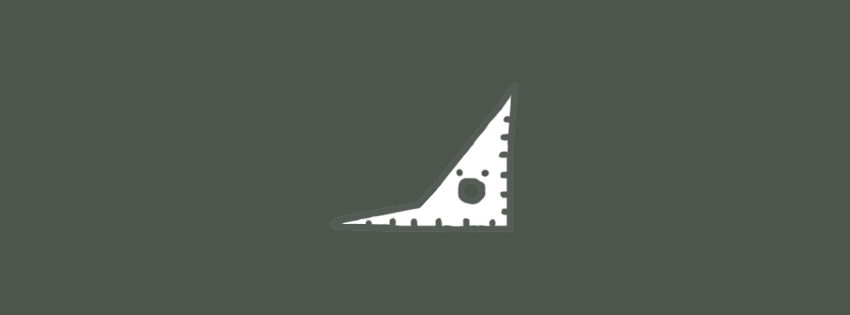
一生は長くて百年しかないのに、ミリだかインチだか変わることにおセンチになってどうする。
「一ポイントずれとるううう」
しかし一年が百年に相当する小学生にその理屈は通用しない。部室の中央にて大きなディスプレイを前に悲鳴を上げているDTP小学生の後頭部をめがけてゲンコツをお見舞いしようとしたところで腕を掴まれた。誰のものか見なくてもわかる。漫画研究会の出席率は幽霊部員の楽園こと卓球部のそれより低いのだ。
「歴史の動くじゃまをしてはいけないよ」
芳岡会長は淑やかに微笑んでおれの腕を放した。万力で締められた跡が腕に残っていないことを確認しつつ反論する。
「コマが割られているだけの素人の落書きを集めたところで完成するのは不動の黒歴史だけなんで。五分ごとに部室の中心で一ポイントズレを叫ぶタイマーを置かないでください」
「はあ、君は小中高一貫校が増えている理由を知らないんだね」
「小学生にDTPをやらせるためではないと思います」
「小学生にDTPをやらせるためだよ」
おれたちは話題のDTP小学生の背中を見つめた。上履きを脱いで椅子にあぐらを掻き、我ら漫画研究会の全体的に画面が白くて線もよれよれの糞原稿に前のめりになっている。
「若いってのはいいねえ」
「そうですねえ。ぼくが彼ならこんな虚無みたいな雑務を引き受けないで古典を読んだり名作映画を観たりしますよ」
「君もまだ私より一年若いようだね。金や時間を払えばだれでもできることに懸命になっていては自分の仕事をできないよ」
「でも、結局、何にもならないでしょう」
「一ポイントずれとるううう」
五分が経った。おれはいたいけな小学生の眼精疲労を阻止するという名目で先輩の制止をふりきってDTP小学生の肩に手を回した。
「一ミリでぎゃあぎゃあ騒ぐなよ糞ガキ。そんなんズレてもだあれも気にせんからな」
DTP小学生は食い入るようにおれをじっと見つめた。原稿の粗を探す熱心さで、あるいは人のズレを指摘してやろうという無邪気さで。
「一ポイントは一ミリじゃない。もっともっとちいこいんじゃ」
「問題はもっともっと矮小ってわけだ」
やつは会長やほかの会員には見せない特徴的な表情をした。きれいな弧を描いた嘲笑だ。
「一ミリずれたら二・八三ポイント以上ずれるんじゃけどなあ」
「だからどうした」
「先輩はわしのことをあほう言いたいんか、それとも一ミリのずれがあほう言いたいんか」
「おれの気持ちは両方だが後者に譲ってやろう」
会長がそっと近づいてきた。彼女はDTP小学生の丸い頭を撫でながら「短い毛で覆われたものを撫でるときにしか生成されないビタミンの黄色を感じるよ」と迷言を残した。
「一ミリずれを一ミリずれと放っておくと一ミリずれたところが基準になってさらにずれていくけえ、そうして放っておいているうちに運ばれていくんじゃ」
「誰に。どこに」
「一ミリずれ宇宙人の好きなところに」
無学なおれにも一ミリずれ宇宙人とやらがDTPとはまったく関係のない分野からやってきたとわかった。やつは目を細めてにやにやとした。
「先輩はな、それを運命と思うんじゃ。本当は意図的に命を運ばれていて、だけど先輩は一ミリずれをあほうと思うけえ、一ミリずれ宇宙人の策略に気づかんのだ」
「人間なんてハイテクビームとかでなぎ倒して服従させればいいだろ」
「いずれ自分が棲みつく家を燃やす宇宙人はおるまい」
「宇宙人はいねえよ」
会長が横から「漫画研究会が宇宙人を否定しちゃだめだよ。科学なんてわからないくせにSFに挑戦したい人間の最後の砦だよ」と説得してくるが、小学生のユーモアに付き合う余裕はない。
「先輩が自分は周囲に何も影響を与えない無力の存在だからと流されて生きているあいだに一ミリずれ宇宙人がちょっとずつ運命を切り開いているんじゃあ」
「おれを悪いように言うな。宇宙人を良いように言うな」
「あれもこれも全部一ミリずれ宇宙人の仕業で、でも一ミリずれに頓着しない人間のせいじゃあ。わしはよう気づくんで、先輩たちの原稿はどうしようもないってお墨付きを与えるわい」
糞ガキDTPerの舐めきった言葉に芳岡会長は両人差し指で両頬を押し上げてダブルピースをした。
「やったね」
「何もやってませんよ、何も」
食堂で選択する昼飯がどうであろうと丼でなかろうと大局には影響のないことで、対面にいるクラスメートから「全身カレー人間め」と悪罵を受けようと気にしない。
おれが全身カレー人間だったとして何がどうなる。
「なあ、どうして小中高一貫校が増えていると思う」
「そんな大層なことを問うためにオメエは毎日カレーで思考を節約してリソースを確保しているのか。俺なんか三時間目から昼に何を食べるかに全集中力をベットしているが」
「会長に聞かれたんだよ」
「かけがえのない命をひとりずつ運ぶより何百人も十把一絡げで唐揚げにしたほうがマヨネーズのかけがいがあって安く済む」
かつてはそうではなかったと反論すると、了木は「かつては今じゃなかろうもん」と絞りたてのレモンをおれに突きつけた。
「教師が人間なら管理できる子どもの数にも限界がある。だから昔は教育側のキャパシティに合わせて学びより先に選別があった。ところで機械は一つを精巧に作り上げるより多くを均した品質で同時に出力することに長けている。そう考えると機械は人間よりはるかに教師の適性があると思わないかね。高い人件費と長い時間をかけて特別に優れた人間をひとり輩出することに全力になっていては輸送費が輸送費が」
「そのレモンは何なんだよ」
「合理化に対する一つの抵抗である」
了木は合理化に対する一つの抵抗を皿に置いてシャツの襟で指を拭いた。
「でも機械が好きなんだろ」
「機械は誤送信しないから」
「それに抗っておまえは誤送信するわけね」
「天の配剤と俺の誤配は近似値である」
偉そうに胸を張った後で、了木はこそっと「ただの人的ミス」と付け加えた。
「機械の正確で信頼できるところが好きなんだ。目で見たものが正しくても後になって振り返るときは写真で見るものが正しい。なぜならカメラはメカで俺はバカだから」
ふと思いついてDTP小学生の話をすると、やつは意味深長に頷いて皿にこびりついたマヨネーズの残滓に唐揚げをぐりぐりと押しつけた。
「ソイツは幽霊が見えるかもな」
「オカルトつながりで」
「心霊現象は微妙な差異に気づきやすい存在を前に起こるものだと考えたらどうだろう。物が移動していることに気づかぬマヌケにはポルターガイスト現象は起こらない」
「まぬけで結構」
「正確に物事を捉え、記憶し、差分を比較するのは機械の領域で、そこでは人に見えないものが見える」
「機械は幽霊を見ることができるってか」
「機械は幽霊を見ることができる」
おれは首を後ろに倒す運動をした。
「一緒に心霊スポットに行こう。公共交通機関と徒歩で行ける廃墟がある」
「観光スポットの間違いだろ」
だいたい小学生と遊ぶほどガキでもない――と答えようとしたところで、肘を引っ張られた。
「暗いところはいけん」
同じカレーセットだった。やつの腕が周囲にいる女子小学生らの視線を誘導していることに気づき、振り払う。
「何で女子とメシ食ってんだ」
一瞬、軽く発した言葉が空気のなかに留まって淀んでいく印象がよぎった。が、DTP小学生の笑い声でかき消えた。
「わしはパパやママと同じ卓を囲むこともあるけえ気にならん。先輩はパパとママを見て男と女がおると思いながらおかずにするんか」
女子生徒らに見えないように太ももをつねると、やつは身をよじって「狭量じゃけえ好かれんのだ」と誰にも聞こえないようにささやいた。
「盗み聞きすんなよ」
「先輩がふだんは話しかけてくんなって」
訳がわからない了木は「かわうそのようにかわいそう」と訳がわからないことを言った。
「おかげで話が早くなった。幽霊が見えるところを見せてもらおう」
「ヤッ」
すげなく断られて皿に散っているパセリの粒をうつろな目で見つめる了木のかわりにしぶしぶと交渉を続ける。
「幽霊が怖いんだろ」
「そんなもんはおらんわい」
「宇宙人はいるのに幽霊はいねえのかよ」
「人は一度おらんよなったら一生会えんのだ」
「いねえならべつにいいだろ。何もないところをスタスタ歩いて回って帰るだけだ」
「暗いところはいけん」
ぷいとそっぽを向いたやつの頭の丸さに驚嘆しつつも、この糞ガキも何だかんだ幽霊を信じていて怖がるのかと溜飲が下がる思いがした。横方向にからだを揺すって隣の女子小学生らに迷惑をかけている了木を宥めた結果、最終的に二人で肝試しをすることになった。
ヤッ。
「一ポイントずれとるううう」
長机で上品に仰向けになって漫画を読んでいる芳岡会長に話の顛末を聞かせていると、彼女はいきなり上体を起こした。壁際にまっすぐ立って見下ろしていたおれのほうを向いて、髪をぶんぶんと振り回す。
「だれかの切った爪が落ちてきた」
「ぼくのじゃないですよ。いや、だからぼくは違いますから。違う、違いますって」
本棚に漫画を戻してから、先輩は慎みぶかく机に座り直した。
「了木くんは本当に面白い子だね」
彼女のつむじが上機嫌に動き、髪が制服を撫でるようにさらさらと流れ、つま先だけで支えている上履きの底が床についたり離れたりする、音がする。
「彼は二日に一回は誤送信するけれど、私はそこに可能性を感じるんだ」
二日に一回。
「興味のないものが送られてくる一方で、今この瞬間に必要だとわかったものがやってくることが稀にある」
一方で、稀に。
「そのとき、私はきっと本来の送信先である誰かと仲良くなれるだろうと考えるんだよ。自分は予定内の世界に生きていて、予定されていない誤りが予定外の世界があることを教えてくれる。だけど、その誤り自体がすでに予定されていたような気がするんだ。そして背後から誰かが言っている――手の鳴る方へ行け! 導かれるままに向かってみると、おじさんの尻を叩く音で、でもそれが自分に相応しい道だったと気づくんだ」
「どんだけあいつと頻繁に連絡を取ってるんですか」
さりげなく投げてみた石が見知らぬ人を流血させてしまった、その静寂だった。
芳岡会長は両手を膝に置いて、ぞんざいに微笑んだ。
「不思議なことが不思議だね。了木くんは送り魔で、誰彼かまわずに連絡を取ってプライベート写真を誤送信するものだよ」
「けどまずどういう縁で」
「宛先を教えてないのに勝手に誤って届いたんだよ」
「で、ずっと続いているんですか」
「それ、君に関係のある話かな」
「一ポイントずれとるううう」
おれはつかつかとDTP小学生に近づいて後頭部をゲンコツで殴った。
「少しは黙ってろ」
作動している機械の音のみが明瞭になり、拡大され、場を満たしていった。やつは振り向き、何もない表情でこちらを見つめた。ただ、頭を押さえた両手がいつまでも下ろされることなく硬直しており、何かがあったこと、その何かによって幼い少年が傷つけられたことは誰が見ても明らかだった。
ああ、もういいや。
荷物を持って部室を出た。了木が少女漫画原作の恋愛映画の誘いを送ってきたので「違う」とだけ返したちょうどそのとき、おれは階段を下りようとしていたのだが――後ろからしがみつかれて転落しそうになり、なんとか踏みとどまった。
体勢を立て直して背中に張り付いていたものを剥がしたところ、DTP小学生が現れた。
「復讐か」
「わしのことはええから部室に戻って会長に謝れ」
「何でおまえに指図されなあかんの」
「明日になったら元通りになると思ったら大間違いじゃ」
やつはおれの腕を掴んでぐいぐいと部室の方向へ引っ張り出した。だが、おれは背も高いし重いし踏ん張っている。未熟な小学生に動かせる相手ではない。
「先輩が今いるのは階段でも踊り場でもなくて、緩い坂道なんじゃ。何もしなければ何も変わらない、その場にとどまり続ける、そんな場所はどこにもないけえ、つらくても坂を上っていくしかないんじゃ」
「ガキに何がわかるんだよ」
「会長が好きなんじゃろ」
少し傾いた。
「ぼく、ぼくってかわいい子ぶって、ちょっとでも失望されたと思ったら全部いけんってハイもう無理だ終わりだって、ふうが悪い」
脱力感から自然に足が一歩出て、やつの足を踏みつけた。
「ぎゃあ」
「かっこ悪くて結構。だけどおれにはどうしようもねえし、おまえも何もできない」
「ねこかぶりっこ。ねこかぶりっこがあ」
挑発にも動じない。おれは動かないし動かせない。そんな膠着状態がずっと続く。
「ええ加減にせえよ」
「わしが恋愛を指南しちゃる」
はあ。
「こう見えて気が利くうと女子からもてもてじゃけ、恋愛のことなら先輩に何でも教えられるわい」
顔をまじまじと見る。こいつは、いや、どうせ成長したら面長になって微妙になる。
「原稿の編集作業も終わったけえ、部室にはもう出ん。相談に乗ってほしいなら教室でも食堂でも気軽に話しかけい」
振り払いたかった腕がいざ離れると、おれはとっさに掴みそうになった。
「ついさっき一ミリズレとる言うたやんけ」
一段、二段と両足をついて降りたDTP小学生は振り返りもせずに。
「うそつきました、ごめんなさい」
やつは急いで駆け下りて壁に隠れて消えて遠ざかったが、おれはしばらく動けなかった。
何故あのとき嘘をついたのか、ズレていないのにズレていると言ったのか、考えているうちに部室の前に戻っていた。重い扉をゆっくりと引く――あるいは誰を救うつもりだったのか。
頬がかっと燃える。してやられた、何様なんだあいつは、おれはガキに助けてもらいたかったわけじゃない、落ちるところまで落ちて良かった、放っておいてくれ。
興味なさそうに雑誌をぺらぺらとめくっている会長に平謝りしながら、おれの心は糞ガキへの復讐心でたぎっていた。了木から「こっちっした」の訂正と共に送られたマップを眺めて返信をする。
どう足掻こうと無駄だってことをわからせてやる。
一時間目が始まる前、おれは初等部の教室棟に行ってDTP小学生を呼び出した。やつは引き戸の側面にからだを預けて、寝ぼけまなこでおれを見上げた。いつもの生意気な態度がないと庇護すべき対象に見える。が、こんな糞ガキに優しくしてやる必要はない。目が覚めるように、大声で用件を告げる。
「おれと付き合えよ」
「くうくう」
「逆に眠った!」
「みんなきにするけえ、くわしくはあっこで」
目を閉じたまま、やつはおれを教室から押し出して壁際まで移動した。
「今日の放課後、時間あるか」
「あるう」
「じゃ夜に会おう」
ゆっくりと目を開けて何度も「夜」の一単語を繰り返す。
「お子ちゃまが夜に出歩くのは危険かなあああ。遅くなったらパパとママが気にするかあ」
首を横に振る。力のない動きで、しかし発声ははっきりとしていた。
「パパとママは気にせんけえ」
行く先は告げず、駅で集合と伝える。謀られていると気づいていないDTP小学生は「さっそく先輩に必要とされてうれしいのお」とはにかんだ。
知るか。誰もおまえなんて必要じゃない。死ね。
というわけで、駅からやけにおれにひっついて歩くDTP小学生を連れて廃墟ホテルの前で大荷物を背負って屈伸している了木と合流した。
「騙したあ! 騙したあ!」
「おまえが騙されただけだ」
やつは恨みがましい目つきをして、何故かおれにしがみついた。
「気にするな小学生。幽霊が見える機械に幽霊が入る隙間がないように、幽霊が見える人間にもたぶんきっとおそらくない」
存在しない幽霊より存在する了木。身震いしていると「幽霊はおらん、おらんわい」とべつのところからも震えが伝わってきた。了木から懐中電灯を受け取る。
「廃墟って外壁から廃墟っぽいな」
「暗いからそう見えるだけだ」
「昼に見たら」
「廃墟そのもの」
カメラを首にぶら下げた了木の先導で、開かれたままの自動扉を通過する。外も寂れていたが、建物のなかはよりいっそう暗く、懐中電灯の助けなしでは一歩も進めないと思われた。
この唯一の光源をいきなり絶って、糞ガキを泣かせることがおれの目的だ。
「幽霊のオフショットを撮って、俺の仮説を検証するぞ」
これが了木の目的。
「DTPとやらでは修正できねえ心霊写真が出来上がるだろうなあ、なあ」
「暗いところはいけん」
「はいはい」
おれは立ち止まって周囲を照らしてみた。役立たずの華美な照明装置、煤けた壁紙、側面に穴の開いたフロントデスク、しみのついた絨毯。耳をすませば外から虫の声が聞こえ、鈍くて低い振動音のようなものが掠め、はあはあと熱い息がおれの服に当たって跳ねかえり、了木の足音が消えた。
「何か見つけたのか」
返事はない。
「ん、じゃこっちだよこっち、こっち来いよ、こっちはガキがいるんだぞ。誘ったのはおまえなんだから案内しろ。せめて断ってから別行動だろうが。どこだ、大浴場にでも行ったのか、客室に、いやここの階段は封鎖されているな、誰か管理しているのか、非常階段は、扉は開く、でも本当に二階に進んだのか、フロアマップはどこだ、おい了木、しばくぞ」
返事はない。
壁を手で伝いながらフロントまで戻る途中、角を曲がって何らかの空間に入った。照明のスイッチを見つけるが、当然のように電気はつかない。了木もいない。
だが、良い機会だ。先ほどから黙りこくっている糞ガキを驚かせて転ばせて背中を踏みつけてやる。
どうせおれが何をやろうと何にもならない。
了木を探す振りをして、わざと部屋の奥まで進む。懐中電灯のスイッチに指をひっかけ、いざ電源を切ろうとしたとき、世界は闇で覆われた。
カチカチカチ。スイッチを何度もスライドさせた。何も起こらなかった。
連絡を取ろうとした。何度も操作をした。画面は真っ暗のままだった。
先ほどまで半身にかかっていた重みが消えた。やつはうずくまって息を切らしていた。
ほらほら怪奇現象だ。大袈裟なやつだな。返事はなかった。
正面に回って膝をつき、抱き起こす過程でシャツの広範囲が濡れた。腕で支えたやつの背中もびっしょりで、暗くてろくに見えないはずの輪郭が噴き出した汗で光って青白く浮かび上がっていた。
――ソイツは幽霊が見えるかもな。
おまえには人には見えないものが見えているのか。それで苦しんでいるのか。
「肝試しごときで死ぬな、あほんだら」
「だ、で、わしゃいらんこなんじゃ」
「何言ってんだ。死んだやつに化かされて生きたやつが死ぬなんて馬鹿げているぞ」
「お、お化けなんて、幽霊なんておらん」
「そうだ、その調子だ」
「わし、わしは暗いところが怖い」
小さなからだが命を縮めるような激しさでおれのなかで引きつってあえいでいた。
「そこまで怖いなら先に」
大きく見開かれた目から大粒の涙がこぼれた。
「言った、言うた、言うとった。暗いところはいけんと何度も言うたのに聞いてくれんかった」
おれの胸に押しつけることも自分の手で隠すこともなく、錯乱していた。
「嫌いだったんじゃろ、わしがたいぎいけえ死ねばええと思ったんじゃろ、あんねえ、わしにはパパとママを見て他人がおると思いながら食べよるときがあった、血ぃ繋がってないけえのお、わしの他人じゃないママはわしのことが少しずついけんようなって、知らん人たちに救出されて箱から出たときにはどこにもおらんよなったわい」
とめどなく流れる涙で指がふやけて、拭ってやっているのか濡らしているのかわからなくなった。
「新しいパパとママには嫌われんようにええ子にせにゃあと誓ったが電気を消して寝られんから気味悪うてちょっとずつ遠ざけられて、きっと今からおらんよなっても気づかれん、隠してないないしたらない、わしはない、わしが幽霊なんじゃ」
違う、こいつは錯乱していない。
おれにも見えるように説明していただけだ。
頭に伸びたおれの手を見て、やつは今にも息絶えそうな声で嘲笑った。
「ここまで話さないとやさしくしてもらえんのか」
傷ついたことで傷つけてくるなよ。
逆恨みだとわかっていた。しかし正当な恨みなんて持ったことがなかった。
やつの汗ばんだ短い髪を撫でる。
「おれは、パパとママを見て男と女がいると思いながら冷めたメシを食っていたよ」
二つの半身から聞かされた失敗は、一つの全身の失敗を意味した。
「どうにもならねえことがある。だから無力で、何をしても意味がなくて、でも、本当は」
言葉にしてしまえば耐えられなくなると思った。決壊して原形を保てなくなると。
「おれが頑張らなかったせいで決定的に間違えてしまったのかもしれない、その結論に至ることが、怖かった」
何も変わらないと言い張ることで、おれのせいではないと正当化したかった。
「不幸な結婚はしない。一緒に一生いられる完璧な関係を得る。その出会いを見逃さないようにする。あいつらを反面教師にしようと考える一方で、うまくいかなくて、焦って、台無しにして……早く幸せな家庭を築いて、早く死にたいよ」
撫でる手を撫でられ、掴まれ、握り締められた。
「最初はどこも幸せな家庭だったと思うぞ」
抵抗する、逆恨みをする、どうしようもないとわかりながら握り返す。
「でも、ちょっとずつずれていくんじゃ」
簡単なことで永遠に離れてしまう弱さで、一瞬だけ強固につながる。
「じゃけえわしらは油断せんこうに。始めるときの努力を終わるまで続けるんじゃ。ちょっとのずれをその都度ちょっとずつ直す」
「おん」
「維持するだけじゃのうて、自分がええと思うほうにちょっとずつずらしもする」
「相手がそれに合わせてくれなくて、徹底的にズレてしまったら」
「ただの音楽性の違いじゃけえ、ちょっとしかつらくない」
「少しでもつらいのは間違えた証拠だ」
「すすんで歩いた道は間違えていても間違えていない」
同時に手を離した。しかし離れたにもかかわらず一抹の寂しさも感じなかった。おれたちは意味もなく抱きしめあった。意味はなかった。本当に何の意味も。だが意味はあったのだ。
「これがわしの恋愛指南じゃ」
お互いに何も言わずに百年は過ぎた。床に置いていた懐中電灯が床と壁を照らし、シャッター音がおれたちを脅かすまでは。
了木は「何だこのオフショ」とおれたちに近づいた。そそくさと抱擁を解いて立ち上がる。
「左右から幽霊に挟まれたのか」
「懐中電灯が何もしていないのに壊れた」
「機械を舐めるな」
「連絡しようとしたら画面が真っ暗だった……さっきまでは」
「連絡も何もまだ入って五分も経っていない。ちょっとはぐれたぐらいで、機械と幽霊の交尾を邪魔しないでもらおう」
おれたちは顔を見合わせた。
翌朝、おれは教室に入ろうとした了木を廊下まで押しやって胸ぐらを掴んだ。
「おいおい、朝から暴行か」
「写真を送って寝落ちしただろ」
やつはおれに背を向け、確認をし、天を仰いだ。
「すまん」
「どうやって撮ったんだよ、佇むビキニ姿で会長が滅茶苦茶かわええ砂浜にオフショット!」
「本当にすまん」
「謝らなくていいから説明しろよ」
「説明したら謝らなくていいのか」
「おん」
「ふつうに付き合っとるけん」
「謝れ、謝れよ!」
了木は「今日はもう謝らない」と逃げるように教室に入っていった。
夜まで暴行してやる。
昼休み、周囲の視線を感じながらも了木の背中にぴったりと張り付いてやつの踵を踏みながら食堂に入ってメニューを選んで運んで着席すると声をかけられた。
「毎田先輩」
学食で初めて選んだうどんセットが奇しくも横にも並ぶ。その現実に見入っていると顔を覗きこまれた。
「たいぎいのお」
「何だ、生永。取り巻きの女子にはフラれたのか。仲間仲間」
「違うが、先輩は振られたんか」
「うっ、昨日の夜はあんなに可愛かったのに昼になったらこの態度」
「事実を答えて質問しただけじゃ」
ビタミンの黄色を補給しようと生永の頭をなでなでしていると、何か、見られているような、一挙一動を注目されているような奇妙な感じがよぎった。
生永はおれの手を払って「麺が伸びる」と食べ始め……る前に横目でこちらを見た。
「帰ったらパパとママに怒られたんじゃ。夜、遅かったけえ」
「そうか、良かったな」
「昨日はどきどきすることがあって、あらかじめ知っていたら行かんかったのに、行ってええ思いをした。たまには流されることも悪くないのお」
しみじみとした感想を述べ、生永はふうふうとうどんを食べ始めた。おれがその余韻を噛みしめていたところで、ふと、気になる話が聞こえてきた。べつにおれに関係ない、まったく、これっぽっちも縁のない話なのだが。
「やっぱり男子小学生が好きなんだねえ」
振り向く。
「女子と一緒なことに露骨に嫉妬してたもん」
斜め後ろを見る。
「おれと付き合えって告白したんだって」
斜め横も。
「この前はカレーで、今日はうどん。もうこれペアフードじゃん」
斜め前も。
「隠れて太ももを触ってたよね」
「いちゃいちゃしやがって」
「夜に可愛かったと言ったらサア」
「男子小学生を抱いている写真をダチ経由で流布するのって何罪になるんだろう」
了木を見る。
「今日はもう謝らない」
機械なら間違えないかもしれないことを、おれたちは平気で間違え、そのことによって別れ、そのことによって出会える。
それにしたって、それにしたって。
恐る恐る隣の生永を見て、視線がぶつかる。やつは片手で口元を覆って――しかし、ゆるく開いた指の隙間からきれいな弧を描いた嘲笑が見え隠れしていた。
「一ミリずれ宇宙人の仕業じゃあ」