ネタバレゾナンス
ネタバレされた女子高校生がクラスメイトと共鳴できないオンライン小説です。
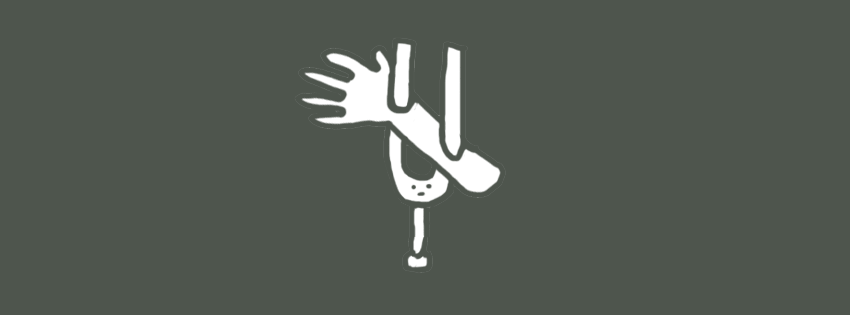
Ⅰ
いつも泣きたくなる。
白本さんが私を見ている気がする。白本藤雄、やせ型。部活、入ってるのかな。出身中学、どこだろう。前のクラス、知らない。成績、わからない。運動、どうだろう。財産、さて。六月の席替えで隣になったことしかわからない彼。目前にいる吉水沙理絵の見解は。
「ようやく気付いたか」
「なにが」
沙理絵はパッケージに「おいしいパン」と書かれたパンを食べながら「おいしい」とつぶやいて、つけたした。
「あやつはおまえを前から狙っとるよ」
「つまるところ、彼は私を愛している?」
「おいおい、そりゃねえぜ純ちゃん。男子高校生の頭を割ってみたことがある? 性欲と焼きそばパンのことしか頭にないよ、彼ら。愛? そんなものはない」
「そっかあ、愛してないのかあ」
すこし泣きたくなる。
食堂からパンを買ってきたらしい白本さんが教室に帰ってきた。確かに手には焼きそばパンがある。
「しかしわれわれはまだ十七歳。いそいで真実の愛など求めなくてよい年頃」
「私はまだ十六歳」
「あいあい、十六歳ならなおさら性欲限定の愛で結構。付き合っちまえ」
まるで手で虫を追い払うようなしぐさをする沙理絵。
「そっか、私はサリーの孤独のおじゃま虫なんだね」
「どういう解釈よ」
「女の子とラブしたほうが楽しいお年頃なのに」
「昼っぱらからしていい発言ですか? ええ?」
今日のお弁当のバランはピンク色のうさぎ柄だった。いつもよりたまごやきが大増量。ちょっとしょっぱい。一口サイズのおにぎりはしそ味。やっぱりしょっぱい。
「弟がね、今日もお弁当を作ってくれたの」
「え? 白本の話題もう終わり?」
「本人がいるそばで陰口をしたら悪口になっちゃう」
「なんだその当たり判定。当たり判定? 当たり判定ガバガバだおまえ」
「サリーがそんなに白本さんの話をしたいのならしてもいいけど」
「何その言いよう。だれがするか、あんな凡夫。おまえの弟の主夫ぶりについて語ったほうがええわ。ウインナーくれ」
つまようじで刺して絶命させたタコさんウインナーを沙理絵の口元に運ぶと、彼女は「ぱく」と言いながらあむっと食べた。
「しょっぺえね」
「なんでなんだろう。いちど、一緒に作ろうかと提案したんだけど、私が早起きできなくて、しょっぱくなっちゃう」
「まあ逆に考えなさい。弟の弁当がしょっぱいからおまえはぐっすり眠られるのです。よかったですねえ」
「よかったです」
くっつけている私と沙理絵の机のもっとも長い辺にごつごつとした手が乗せられた。顔をあげると白本さんがいる。すこし目があって、すぐに彼は沙理絵を見た。
「だれが凡夫だ」
「あ? てめーだれだよ。許可書だせや。学年で一番のビジンに話しかけるには許可書が必要なんだぞおい」
「学年で一番の美人はあんたじゃない」
最後に残しておいたラズベリーをつまんで口に入れる。あまじょっぱあ……表面に塩を練りこんだのかな。
「純ちゃんさん、純ちゃんさんや。見てみいこいつの顔、真っ赤」
首を少し上向けて白本さんを見ると、あごしか見えなかった。首が長い。
「おい、こら。天井を見てごまかすな」
「ちょうどそこにハリガネムシがいたから」
「男の子ののどぼとけってグロテスクかも」
「おまえらわざとやってんのか」
沙理絵は立ち上がったと思うと自分の席に白本さんをむりやり座らせた。そのまま彼の両肩を手で押さえて椅子の後ろに立つ。
「おいストーカー。おまえのストーカー行為がついにバレたぞ。謝罪しろ」
「ご、ごめん」
「壁の一面に私の写真がはってありますか」
「ないです。写真ほしいです」
「彼は本当にストーカーなの? 私の写真すらもっていないなら、ただの他人なのでは?」
「せめてクラスメイトにしてやりんさい」
おそらく私ははじめて真正面から白本さんを見た。男子生徒だ。なぜかじっと私を見ている。
「卑猥な目……」
「ち、違う。違います」
「そこは肯定するところだろうが。エロエロしたいって言え。告白しろ」
「え、エロエロしたいです……」
「私、えっちなこといやです」
終了ーと言いながら沙理絵は白本さんを椅子から押し出してふたたび私の正面に座った。
「はい、白本の恋は終了。残念でした、来世からやり直してください」
床に膝立ちした白本さんは「そこをなんとか」「だいたい吉水が悪い」「一回だけ、ワンチャンス、ワンチャンください」と私たちの机をがたがたと揺らす。
「ううん、ごめんね。もういちごのヘタしか残ってないよ」
「まあデートの一回や二回、してやってもいいんじゃね」
「サリーはやさしいね」
「おまえがするんだよ」
視線を落として白本さんを見る。濡れた子犬を飼いたい少年の目。
「今週の土曜、どうですか」
「わ、わかりました。弟に弁当を作らせてきます」
「おまえが作れぃ」
人生初の男の子とのデート。あまりにも美しい嘘。よく弟と服を買いに行く。お姉ちゃんの服が着たいと私のスカートを引っ張っていた彼も今や立派な中学二年生。フリフリのエプロンをつけてデート用のお弁当を作っている。
「姉ちゃん、おはよ」
「おいしいね」
「まだ食べてないでしょ。今日はいっぱい肉を入れたよ」
「お休みなのにありがとね。お肉もがんばるよ」
テーブルにつくと弟は私の前に朝ごはんを用意してくれた。目玉焼き。大量のつぶつぶと白くて透明のものがかかっている。食べる。塩。
「しっかし姉ちゃんがデートとはねえ」
「人生に伏線なんてないんだね」
「どういう服でいくの?」
私はちらっと今の服を見た。パジャマのまま。
「いつもはサリーが着てきそうな服に合わせていたからなあ」
「前にぼくがセールで買った服があるけど見てみる?」
「見る見る」
小さな駅の改札前、ラックに入った見慣れたくすんだフリーペーパー。とん、と背中をノックされてはっとした。
「目がさめたらデートが終わっていました」
「立ったまま寝てたの?」
少し不機嫌そうな白本さんは黒いポロシャツに白いクロップドパンツを履いていた。そうきたか。やわらかな青と白の半そでボーダーに合わせた白の膝丈スカートを撫でる。真っ青でもよかったかも。
「白本さん、かっこいい」
「え、あ、おう」
時計を見るともうすぐ電車が来る時間だった。私は動かない白本さんの背中をちょんちょんとつつきながらなんとか電車に乗った。人はまったくがらがらがら。
空いていた長椅子に座ると、白本さんはその対面に腰を下ろした。とても泣きたくなる。私は彼の隣に座りなおした。
「白本さんは何人兄弟?」
「一人っ子」
「みたらしとあんこはどちらがお好き?」
「みたらし」
「体育の成績」
「さん」
「私は五だった」
「谷地さん、かわいいです」
「ありがとう。得意科目は?」
「数学……さっきからなんなんなん、これ」
ありもしないメモを書くふりをして首をかしげる白本さんに言う。
「知らないのに好きにはなれないかも」
「はあ」
「知ったら好きになるかも」
「ほあ」
「だからいっぱい知ることは、いいこと。今日は白本さんのこと、たくさん知りたい」
なるほど、と白本さんは神妙そうにつぶやいて「でも知ることで嫌いになることもあるかもよ」といった。
「人間はいつか死ぬ……」
「し、知ってるよ」
「知ってるけど知らないはず。だって私たちはまだ生きているし。こういう、中途半端に知っていると怖くなったり嫌になったりする、と思う」
「だから、いっぱい知る?」
「たぶん、たくさん知って嫌いになるものなんて、きっと一つもないよ」
いつの間にか私と白本さんは頭を小さく横に揺らしていた。でも途中で止めることはむずかしくて、そのまま揺らし続けた。
私たちの住む近くでいちばん大きな街。でも並ぶビルの低い街。空港が近いから高くしてはいけないらしい。そんなちっぽけなタウン。私は少しだけ大きくなった気分で歩く。
「白本さんは裏長屋って見たことあります?」
「あるかもしんないけど、その言葉とは結びつかん。なんで」
「つい最近に読んだ小説であったの。うらながや。そうしたら、かなしくなってしまって」
「なんでい」
そんな街の中心、駅の近くに広い公園があってさらに神社があるなんて、なんだかふしぎな気持ちになる。
「これはあれだという意味で、裏長屋とはずっと縁がないでしょう。走馬燈のように思い出すなかにもなくて。ほんとうはあるはずのもなのに、私と白本さんの中には一生ないの」
「あ、俺も入れちゃうの?」
映画が始まるまでにはまだ時間があった。私たちは木陰に並んで座って、地面を見た。茶色と薄茶色のチェック模様に幹、木の枝、葉の影がはっきりと落ちていて、風に合わせてゆわゆわと揺れた。
「谷地さん、けっこう話すのな」
「言ってもいい? 白本さんが話さないからです」
「答えるまえに傷つくこと言われた! いや、ごめん……ちょっとさ」
「ほんのすこし」
「そう、ほんのすこし……映画のネタバレを見ちゃって」
白本さんの靴は、ぴかぴかのスニーカーで、靴紐がパキッと硬そうに見えた。私よりとても大きい足。素敵な靴に一目ぼれしても、まずは箱を見なければいけない彼の買い物。今の白本さんの表情はまさに良いサイズの在庫がなかったときと同じ顔。
「人と一緒に映画を観るのってさ、対等じゃないとだめなんだよ。俺だけが少し知っていて、隣にいる子が知らないで、次はどうなるんだろうとわくわくしている横で、ああこういう流れでそうなるんだなあとヒエヒエしていたら、手をつなぎたくてもつなぐタイミングがわからねー」
つまり、白本さんは暗闇のなかで女の子のからだに触れる機会を永遠にうしなったことを嘆いている。
きれいなスニーカー、よごれた白本さん。
「はじめての共同作業で、ひとりだけリハーサル済みで、ひとりだけぶっつけ本番みたいな感じ?」
「そうそう、それそれ。どういう状況かわかんないけど」
「そっか。ちょびっとわかるような。ほんとうに一緒に驚けるのって、二人して何も知らないときだもんね」
「谷地さん、わかる。すごいわかる人」
でも、それなら座席を取る前に教えてくれればよかったのに。そうしたら、違う映画のチケットにしたのに。なんて聞いて、萎縮されるかどうかもわからないので、聞けない。それと同じ理由で、白本さんも私に言わなかったのだろうと思った。
映画館を出た私たちはふたたび公園に戻ってきた。同じ場所に腰を下ろしてから「ごめんな」と白本さんは頭をかいた。
「また公園かよって思ったでしょ」
「でも雑貨屋さんでお弁当を食べるわけにもいかないし」
「段取りわるいんだよな、俺。今回のデートだってさあ……」
弁当のふたを開けた白本さんは続きの言葉も浮かばないようで、そのまま黙々と食べはじめた。
「弟が手塩にかけて作ったんだよ」
すこしむせた白木さんは肘で私を小突いた。
「手塩の意味が違うでしょ、これ」
「たしかに、今日の味付けはちょっと濃いね。しょっぱあ」
「お店の袋みたいになってるじゃん」
「おふくろの味?」
「夫を生活習慣病で殺す悪妻弁当だよ」
塩からあげを口に運んで、たまに白米だけを食べてみる。塩むすびのような味がする。
「もしかして、ひょっとすると、ふつうなのかも」
「こんなの、十人いたら九人はしょっぱいよ」
「だけど一人の感覚が正しいときもあるかもしれなくて、弟はそのひとりで、私たちの目を覚ますために夜な夜な塩をふっているのかも」
「しおしおだ」
白本さんがこちらを見て首をかしげた。
「さっき体育の成績を聞いたことを思い出して」
「え、俺の成績、あとになってじわじわくるほど笑える?」
「そうではなくて。相手にひとつ尋ねたら、ひとつしか返ってこなくて。でも話をはじめたら、たくさん返ってくるから。もし完全にプロフィールを移植したロボットを作っても、その人は再現できないんだろうなと思ったの」
「いつもそんなマッドサイエンティストみたいなことを考えているの?」
「人間は情報だけではないんだね」
しゃらしゃらしゃらしゃら。坂道を歩くご老人にはつらい風が、ここでは葉と葉を再会させる。出会った彼らはお別れの歌をくちずさみながら、また違う方向に歩き出してしまう。私たちはその足音だけを知っていて、あとのことは何も見ないし聞かない。
見ないし聞かないから、見られるし聞ける。
「俺さ、谷地さんに質問されたら答えようと思っていたことがあって」
ごくっと白本さんはつばを飲んだ。私が残っていた塩からあげを白本さんの弁当箱に置くと、彼はへなへなと肩をすくめた。
「どうして好きになったのって、聞いてくれないから」
「えっ、それって私から確かめることなの」
「ときどきド直球だよね。違うけど、違うけどさあ。すこしはちょっと気にならない?」
彼の横顔はゆびで輪郭をなぞりたくなるような、きれいな形をしていた。わずかに足を浮かして履いてきた今日の靴の先っぽを見る。
「私のなかで話題の交換法では」
「交換法?」
「もし形が違ったらどうなのか、色が、触り心地が、硬さが、味が、においが、値段が、由縁が、変わっても好きでいられるのかを考えるの。それで導き出した結論が」
「うん」
「人は見た目が九割」
座っているのに、ずっこけた。
白本さんは座りなおして「それはないんじゃないの」と口をとがらせた。
「一割の九割は由縁かも」
「好きな人にはその一割で好かれていると知ってほしいね」
「じわじわと浸透してくるみたいにわかることってあると思う。ああだから好きと伝えて、伝えられてすべて納得できる想いしかないなら、おしゃべりもデートも無縁です」
「おう……でも言いたいなと思って練習してきから言わせて」
「どうぞ」
ひざ頭が少しだけこちらを向いた。
「文化祭の打ち上げでさ、話してくれことがあったろ」
ぱち、ぱち、ぱち。まばたきだけ交わして、白本さんは左手で顔を覆った。
「忘れてるかあ、いや、いいんだけどさ、いいけどさあ」
「たぶんいつもの日常会話だったんだね」
「いや、ふつうの話ではなかったな。むしろ風変りで、なんでいきなりそんなことを言い出したんだろうと思ったよ。俺しか聞いてなかったからツッコまなかったけど」
なじむように溶ける雲のさきっぽ、いつまでも視界から消えることのない悠久の時。
「うーん、覚えてないです」
「ちぇっ」
白本さんが立った。それからくるりとこちらを向いて「次の場所に行こう」と手をさしだしたが、その前に私も立ち上がっていた。
パックが白本さんのゴールに入って、試合終了となった。これで彼は「一回だけ、ワンチャンス、ワンチャンください」と言って三回やったのに三回とも負けた。
近くにあったベンチに座る。ふたり座るだけでも窮屈になる狭さ。白本さんはベンチの隣で立っている。とても泣きたくなる。
「谷地さん、誤解しないでほしいんだけど」
「はい」
「俺はエアホッケー愛好家でも負けず嫌いでもなくて、谷地さんと遊ぶのが楽しくて何回もやったんだからね」
「スロット……クレーンゲーム……」
「プライドが高いわけじゃないから。全然、謙虚なキャラだから」
「プライドが高い白本さん、私の耳が遠いです」
彼はちらりとこちらを一瞥して端に半分だけ座った。
「聞こえてたでしょ」
「がやがやしていたので」
小さな声で「油断ならねえ」とつぶやいた白本さんは、そういえばと首だけ後ろを向いた。
「プリントするやつ、プリントしませんか」
「写真シール機なら白本さんが見ている逆に」
「ほんと、油断ならねえ」
ぐいぐい。手を引っ張られるかたちで、赤い看板のアミューズメント施設を出てすぐにあるクレープ屋のかげに隠れる。車が通ることなんてまったく考えていない、五人ぐらい横に並べそうな歩道を見知った顔が歩いてきて、それを追うようにまたもや見知った顔が走ってきた。
「はあ、信じらんねえ。もう人間不信だわ。人と出会うたびに手切れ金を渡す日々が始まるわ」
「そりゃ小遣い稼ぎにぴったりだ。これがうわさの出会い系」
「うまいこと言ってないかんね」
と後ろを振り向いて怒鳴ったサリーと偶然に目があった私は、クレープ屋の陰から飛び出して、おずおずと手を差し出した。
「手切れ金」
「あたしはかなしいよ純ちゃんや。休日にひとりでゲーセンに行くなんて」
「俺も一緒だって」
しぶしぶと出てきた白本さんにサリーは頭を振って、私の肩をぽんぽんと叩いた。
「付き合ってもない男子と二人で密会だなんて、いったい最近の若いもんは。ママは許しませんぞ」
「ママァ」
「おまえが誘導したんだろうが。つーか、そういう吉水は奈谷と付き合ってんのかよ」
名前の出た佳功くんは「卓球に付き合っただけよ」と答えてから大きな欠伸をした。
「勝てなかったから沙理絵がキレた」
「違うでしょ。あんたが勝つまで延長してやったんでしょ。一人千円とかアホか。レディースデーなら映画が一本観られますですわよ」
「おれはレディースデーでも割引ないもん」
「何がもんだもんじゃ」
甘いクレープのにおいが穏やかでない私たちのあいだに広がった。「クレープを半分おごってやる」白い歯を見せる佳功くん。「わかった。カスタードといちごと生クリームはあたしの分ね」強欲なサリー。「半分にできないものを半分にしようとするから問題が生じるんだ」これが白本さん。「食べてみたいな半分のクレープ」そして私。
四人で買った四個のクレープがもくもくと消えてから、佳功くんが時計を見た。
「良い時間だし、ボルダリングでも行くか?」
「純ちゃんのこのひらひらが目に入らぬか?」
「ボルダリングに良い時間なんてあるの?」
「ボルダリングって何?」
白本さんは私たちの顔を見て頭を掻いた。
「そんな。信じらないみたいな反応をされても」
「さながら海を知らないわかめのよう」
「コンビニで募金される立場の人間」
「文化資本の格差がふとした瞬間に子どもの自尊心を傷つけるんだね」
「なんでい」
Ⅱ
ときどき笑いたくなる。
融資募集。吉水沙理絵は五段階のにらめっこの末に。
「文化祭のステージってそんな金が掛かんの?」
鼻の下を縮めてタコの口を作る。私は胸をなんどか叩いてなんとか生き返った。
「心あるご支援をお待ちしているのかも」
「ふうん。ノルマが達成できなかったら文化祭実行委員が払うとかあんのかな」
「ブラステ」
「昨今はやりのブラステねぇ」
くっつけている私と沙理絵の机のもっとも長い辺にごつごつとした手が乗せられた。その手にさらにごつごつと黒い手が重ねられ「おおい」の悲鳴で下からはじけてふっとんだ。
「気持ち悪ィことするな!」
「藪から棒にひどいことを」
「それはこっちのセリフだっつうの」
今日はなんとメバルのからあげ。ひんやりとしたごはんに乗り上げる大迫力で、何やら申し訳なさそうにグリーンアスパラガスとパプリカが隙間に添えられている。華やかとは言えないものの、匠の技が光っている。たとえばそう、室内灯を受けてきらきらと輝く塩。ドレッシングやマヨネーズに頼らない、自然な味を活かした一品。ぱくぱくぱくと噛んでいるだけで目がしおしお。
「って聞いてよ谷地さん。週末、とてつもない快晴らしいよ」
「うっわ、こいつ五日後の天気予報を信じてやんよ」
「明日には明日の雨が降るんだぞ」
白本さんは沙理絵と佳功くんのあいだを割るように私に顔を近づけて、軽く握った両こぶしで机をどんと叩いた。お箸入れがかちゃりと鳴った。
「アスファルトに雲の影がひとかけらも落ちないらしいよ」
「なんだなんだこの小っ恥ずかしい茶番は」
「リア充木っ端みじんこ」
「私、日焼けしそうだからいやです」
あんぐりと開いた口にお弁当箱の底にたまった塩をすりこんだグリーンアスパラガスをつっこむ。「しょんなあ」もぐもぐと食べながらどんどん浮かぶ白本さんの目にも涙。ずるずると膝から落ちてゆく彼の頭と肩を手と肘の置き場にする沙理絵と佳功くんはいつのまにかラーメンの話で盛り上がっている。
「そういやあの店、ついこの前に卒業したとよ」
「どうせどっかで店舗だすんでしょ。卒業という言葉で宣伝して知名度をアゲアゲしてソロ活動になっても応援してくださって魂胆よ。アイドルと同じだわな。はいはい、人生を卒業してから卒業って言えや」
「どうやって言うんだ?」
「そりゃもう手紙よ。違法建築の隙間に挟んでね。『この手紙を読んだのはあなたで五人目です』」
「けっこう遅かったんやね」
「そしてしんみりと活動をふりかえるわけ。『こんなに売れないなら初めからやらなければよかった』」
「重いな」
「だけどこうやって結ぶのよ。『店を始めたから売れず、売れなかったからあんたに手紙を書けて、手紙を書けたから卒業できた。もしも店を始めなければ……』」
「泣ける論理展開だなあ」
「『店を始めなければ、今ごろマンション経営で遊んで暮らして屋台のそばにある夜のお店でエロエロちゃんねーを札束で叩いていたのに』」
「未練たらたらやん」
ラーメンの話では盛り上がっていなかった。
いきなり立ち上がった白本さんのせいで二人の手と肘はあらぬ方向に投げられた。
「よっしゃあ、ラーメンを食べに行くでぇ」
ひとり、ラーメンの話で盛り上がる白本さん。
なぜか私を見つめて外さない白本さん。
オフィス街と繁華街のそのあいだ。川のすぐ近くにそびえたつ、というより、低くどっかりと構えている巨大施設。流れる運河と広場の噴水がいかにも涼しそうで、汗ばんだ足の裏がうずうずとサンダルのストラップの弾ける瞬間を待っている。白本さんといえば電車での弾け具合から一転して、膝をふるわせている。
「俺、じつはインドア派なんだよ」
「駅から十分程度の徒歩……」
「インドア派は夏の外出に慣れていない」
体育の成績が三の白本さんは水辺のベンチにひとりで座って手招きをした。その隣にぴったりと座ると横にずれた白本さんが転げ落ちそうになる。笑いたくなる。
「ラーメンさあ、たぶん並ぶよな。ネットに書いてあった。おいしい人気店ほど並ぶんだって。そりゃそうだよな、解説されなくたって自然の節理だ」
「世は資本主義なんだね」
「自由な時間ってさ、性格が出るよな」
白本さんは携帯電話で私に動画を見せた。ふわふわな子猫がねずみのおもちゃを前に高く上げたおしりをふって狙いを定めている。
「この猫、可愛くない?」
「かわいいです」
「まあ、谷地さんのほうが可愛いけどね」
「ホーム画面で読書のアプリが見えたけれど、白本さんは本がお好き?」
「まあ、谷地さんのほうがす……誘導尋問ひどくない?」
そんなつもりはなかったのに。白本さんはありもしない衝撃で吹きとばされていよいよベンチからずっこける。道ゆくおしゃれなサンダルの視線がじゅっ。
「新品の書籍って基本的に安くならないでしょ。でも電子書籍はセールがあるから、つい買っちゃうんだよな。それで暇つぶしで読んでる」
「出会いが増えていいね」
「それがむしろ前々から知っているようなタイトルばかり手を出しちゃって。あとセールをする作家や出版社ってだいたい決まっているから、だんだん同じようなものしか読まなくなるんだよな」
「むずかしいですねえ」
「つくづく思う。世界ってそう簡単に広がらない」
ほくほくの音が芯から出ていて冬なら無敵なのに今は夏。白本さんはハンカチで汗をぱたぱたと拭きながら「もう動きたくない」と店を出てすぐにあるベンチに腰をおろす。
「せっかくだから食べ比べてみようと言い出したのはだれだよ、俺だよ」
「多くのことは自問自答によって見つかるものだね」
白本さんは手をうちわにして風を作る。見ているとこちらに寄せてあおいできた。私の目前で上下に軌跡をつくる地味に長い白本さんの爪。ぶるりとくる。
「人間の限界に対するものの種類が多すぎるよな」
「時間もお腹もかぎりがあるからね」
手を止めて白本さんは腕時計を起こすように腕をあげた。すこし近づいてのぞきこむと白本さんがすこし退く。ちょっぴり塗装のはげたアナログ時計は昼食とおやつの間隙にねらいを定めている。
「休憩してから回ってみる? 駅に戻って遊ぶのもいいけど」
「ラーメンに再チャレンジするのもいいし」
「それはよくない」
ああだこうだと話しているあいだにも刻々と長針は回ってゆく。一時間前と変わらない速度で、一日前と変わらない角度で。まったくそうではないのに、目を回しそうになる。
「時計があるのっていいね」
「まあいらないんだけどな、いらないんだけど、ポケットやカバンから取り出す時間が惜しい瞬間もあるから」
「どういう時?」
「言わないもん」
「え?」
「言わない」
私にも白本さんに言わなかったことがあった。
ときどき聞き取りづらい校長のあいさつについて話しながらキャラクターショップに入る。子どもから大人まで愛されるゲームのキャラクターがぬいぐるみとなって棚にすきまなく陳列してある。短い毛に埋まった縫い目を眺めていると「こういうショップの商品ってさ」と白本さんが割り込んできた。
「ちゃんと袋がかかっていればいいけど、むきだしだと汚い感じがするよな。子どもが何を触ったかもわからない手で頬ずりしているかもしれなくて」
「頬ずりなら手は関係ないのでは?」
「わりとどうでもいいところ突っこむよね、谷地さん」
白本さんは頭を掻きながら周りではしゃぐ少年たちをちらちらとみる。
「昔はなんでも触って確かめてたでしょ」
「なめくじとか」
「たぶん分かるようになったからだろうな。表面に光沢があればつるつるしているし、粒が集まっているならざらざらしている」
そもそも知る必要なんてなかったよなナメクジの肌触りなんてさ、と白本さんはぬいぐるみについた値札をひっくりかえして、さらにひっくりかえした。
「谷地さんの話を思い出したんだけど」
「私の弟がなぜか塩の種類に日に日に詳しくなってゆくこと?」
「関係ないし初耳だし。ほら、見えないのに見えたって話」
ふらりと近くの雑貨屋に入った私たちは、棚にかざられている音叉のような形のアクセサリースタンドの前に立った。
今日となんら変わりのない休日、私はふさがった両手をぴりぴりとさせながら、おしゃれなウインドウの前を歩いていた。服は直前に控えていた春に着るもので、靴はそれに合わせて履けるもので、文房具は明日にでも使うもので、本は今日にでも読みはじめるものにしても、ひとりで買う量ではなかった。それと比べて前を歩く親子のつつましさといったら。ゲームの景品袋を抱きかかえた娘が車道にでると母親は場所をいれかわって「落としちゃうかもよ。のぞきながら歩いたら」と笑い、小さな女の子は「お楽しみだね」といって袋のヒモをひっぱってぎゅっとしぼる。大きなぬいぐるみでもゲットしたのかな。だけどぬいぐるみでなにがお楽しみなんだろう。なにに使うのかな。ぬいぐるみで楽しいこと、ぬいぐるみ、楽しいこと、ぬいぐるみっていったい。私の疑問に答えるように、だれかの声が聞こえた。
が、何を言っているのかわからなかった。
なにかにぶつかった拍子に吹きとばされるように倒れて頭をぶつけて転がった。手で顔をおさえると長い悲鳴と乱れる足音のなかでも響くぐらいの水音がした。だれかが駆けつけて私の肩を叩いた。「わかりますか」こちらを見下ろしている人のまわりに複数人が立っていた。きっと私のことを心配そうな顔をして見ているに違いなかった。が、わからなかった。「もう呼んでるんで、だいじょうぶ。がんばって」「やっっっべーめっちゃ出てるじゃん。これ拭くかおさえたほうがいいんじゃないの」「しゃーしーな。素人が勝手に動かすのはよくないって、だいたいティッシュってはりつくからバカアホマヌケ」「そこまで言わんでも」「あ、そうだ。指、これ何本かわかりますか?」たぶん、私の目の前でかたちをつくるだれかの指。「三本」「ならこれは」「一本」「よかった、はっきりわかってる」ところが、私にはなにも見えていなかった。
すべて見えていて、なのにすべてがわからなくて、もちろん人の顔すら認識できなくて、手が本当にそこにあるかも断言できないのに、指の本数を答えることができた。
病院に運ばれて、額を縫って、いつのまにかいつものように見えるようになっていて、一日入院して、夜に頭痛で何度も吐きながら思った。私たちがなにかを見るとき、つねになにかを見まいとしている。ピントを合わせる。集中する。ふちどる。輪郭を意識する。形を認識して名前や種類と結びつける。こうして初めてなにかを見ることができる。機能が壊れていないかぎり。そして、壊れていても、私たちは意識の外でわかる。わかってしまう。見たと思ったこと、見て感じたこと、その両方を裏切るように答えを先行して知っている――ポテトの早食い勝負をしていた沙理絵の横でもてあましていた私は、あの日、ちょうど前に座っていた白本さんに話せることだけ話した。
その白本さんは「思うに経験が答えたんだ」とアクセサリースタンドを土台からひっくりかえして、底に貼られた値段シールを確認したのち、ひっくりかえした。
「指は五本で、だけど確認するのにいきなり一本と五本はなんだか滑稽だし、とっさに作れる指を考えたときに一回目に四本はないだろ」
「親指を折るだけだから一番かんたんなのでは?」
「……だから二本と三本の二択で、二本はピースみたいで不謹慎だから三本でしょ」
「緊急時にピースだから不謹慎だと考えているほうが不謹慎かも」
「三本指から変えるときに二本や四本じゃ差がなくて試す意味がない。それで二回目は一本だと導けたんじゃないかって。見えないものは見えなかったんだよ。あてずっぽうで正解しただけで」
この人はそんなことを考えて何が楽しいのだろう。
私の顔を見て、白本さんは「ちぇっ」とわざわざ声に出してそっぽを向いた。
思うだけでよいのなら思いたい。すべて私のあてずっぽうでありますように。見えなかったとき、そもそも何も起きていませんように。たとえば、たとえば……見えない白本さんの顔が完全な無でありますように。
Ⅲ
やっぱり泣きたくなる。
私の塩唐揚げをぱくっと食べながら「このピック、旗みたいで可愛いな」と褒めてごまかす沙理絵のたこウインナーは本日も格別。こほんと咳払いをして、少しだけ胸をはる。
「つまようじにマスキングテープを巻いて作ったの」
「へー、面倒なことやんね」
「弟が」
「だったらなんだったんだねそのしぐさは」
文化祭も片付いたことだしあとは試験だけか、それと夏休みだね、夏休み開始までのイベントの話に決まっとるわい頭ポップコーンか、とんでもない罵倒のほとぼりもさめやらぬうちに沙理絵はとつぜん目を輝かせて「そういえばホワイトブックとどうなった?」と机越しに迫ってくる。頭ポップコーンなのでそんなことはわからない。
「毎週どっか行ってない? というか、下手したらあたしよりあいつと遊んでない?」
「ううん、指折りで数えられるぐらい」
「一回も九回も誤差のツワモノ」
「二か月には一日が六十一回もあるからね」
話していると見知った顔が見知った動きでこちらに近づいてきた。私たちの机に手をのせて、少し鼻息のあらい白本さんは。
「お祭りがあるそうですよ」
と囁いたのだけれど、ほぼ同時に彼の反対側からやってきた佳功くんが「祭り行こうぜー」と大きな声で言ったので、沙理絵はそちらを向いて「どの祭りだよ夏は祭りだらけなんだよ頭フェスティバルか」と怒鳴った。
「シーデイのやつだよ」
「マリンデイでしょ」
「ただのボケにツッコミをいれて常識的なことで博学ぶらんでもらおう」
「なんのひねりもないただの直訳でボケを気取らんでもらおう」
わあわあ言い合う二人を見ながら「何、俺の言葉キャンセルされたの?」と白本さんはぼやいて、ぎこちなく動かした首で私をむりやり目を合わせた。
「わたあめ食べたくない?」
「弟が飴からわたあめを作るおもちゃを持っていて。けっこうです」
「うっわ、断ると思った! 最初に絶対断るもんね! 学習したよ俺」
ほんとうに断りたくなる。
白本さんは私の顔を覗きこんで「浴衣も着ていこうと思う」とおずおず。アピールポイントのように言われても、さらに断りたくなる。
「おまえらさ、あたしと純ちゃんの仲を切り裂こうとしたってダメだかんね。二人の友情は永久に不滅!」
「おれはたびたびいっしょだもん」
「じゃ、ホワイトブックが悪いのか」
「な、なんのひねりもないただの直訳で人を呼ばないでもらおう!」
「じゃ、白本が悪いのか」
「谷地さーん」
「困ったときの谷地さんは、端的にいって役立たずなんだね」
「三人いて一人も味方がいないとかありえる?」
わんわんとウソ泣きをする白本さんを横目に「浴衣って地味に暑いよな」「おまえが暑がりなだけでしょ」「少しわかる。見た目のわりには涼しくないかも」「おまえらが暑がりなだけでしょ」と雑談をしていたところで、バーンと叩かれる机。
「何ならねじり鉢巻をつけてサンキュッパ!」
「あわれだから手討ちしてやんなさい」
「助太刀しよう」
「はっはっは、テウチはテウチでも殺るほうの手討ちだったりして!」
「ハハハ」
「アハハ」
「フフフ」
打ち上げられる花火の数だけ夜空で爆発が起きている。弟は現実的なポエムを唱えて、満足気な様子で私の腰を叩いた。「これでよし!」くるくると回りながら、姿見まで移動する。白地に咲く朝顔の生首がいたるところに散らされている。
「姉ちゃんはおとなしそうなのが似合うね」
「沙理絵が黒に牡丹だからちょうどいいんだね」
「だけど、浴衣の白は黒よりデンジャラスだよ」
ためしに着物をぴったりと体にまきつけてみる。ベージュの下着をつけたおかげか、まったく色が目立たない。
「大丈夫。白本さんをドキドキさせてはいけないからね」
「いけないの?」
弟はいたずらっぽく笑う。
「何も変わらず、いつもどおりがいちばん」
私はいたずらに笑う。
それでも、この日は例年どおりいつもどおりとはかけ離れている。道路は大混雑、地下鉄には臨時の電車がやってきて、屋台が並び、つめよせる浴衣。わたがしぱくぱく。
「同じ目的をもったまったく関係のない人たちと居合わせているってすごいね」
「なに言ってんだおまえ」
「それ、白本も似たようなことを言ってた。『好きな人がいると思いだし笑いが増えるよな』って」
「まったく似てないです」
「ただ白本の恥をさらしただけだわな」
「すまん、白本」
「もうこの感じやだー」
だけど、私たちはこの大勢とすこし違う高さから花火を見る。
「しっかし、白本。最初からマンションから見たほうがいいぞ。不法侵入して敷地内に入ってくるやつで通路が埋まるから」
「そんな不届き者には謝りながら横を通してもらう」
「わざわざそんなことしなくても、お得意の思いだし笑いをしておけば相手から引いてくれるわ」
「引くの意味が違うだろ!」
白本さんは口をとがらせながら「谷地さんは嫌なの?」と怒り気味にいう。私はなにもいってないのに。
「下から見たあとで上から見たら、立体感がでるかも」
「純ちゃんも難儀なやねえ、こんなサイコに目をつけられたばっかりに」
「谷地さん、そろそろフォローして!」
「人と人との出会いは事故みたいなものだからね」
「恋の流れ弾」
二人の背を見届けようと思ったのに、あっという間に消えた。仕方がないと振りかえれば白本さんもいなかった。
周囲にはたくさんの人が歩いていて、姿やかたちの違いはわかるのに、だれがだれなのか、なんなのか、なにをしているのか、なにを話しているのか、なにが楽しいのか、なにが悲しいのか、わからない。
人混みのなかでぽつんと立っていると、肘をひっぱられた。「谷地さん」ここで私を呼ぶ人のことは、ネタバレをされなくても知っていた。
「もうちょっと手前に行こうよ」
「マンションに向かうときに抜けづらくなるのでは?」
「思いだし笑いをすればいいんでしょ! 俺が!」
沙理絵ですらそんなことを頼んでいないのに。白本さんは私の顔をのぞきこんで「人が多いところは苦手?」とたずねた。
「顔色が悪いような気がする」
「将棋倒しになったらどうしようと思うことがあって」
「あっ、それ分かる。あとミサイルが飛んでくるとかね」
「それはよくわからない」
「に、似たようなことでしょ」
「よくわからない」
もう、と白本さんは地団駄を踏むつもりでだれかの足を踏んで平謝りした。
この人、いつも怒っているな。
「白本さんは大丈夫ですか」
「んー、全然。まったく大丈夫じゃないよ」
アナウンスが流れた。みながざわざわとし始めて、聞こえるのに聞こえないのに知っている。そろそろ、爆発する。白本さんは上向くあごで線を描く勢いで空をあおいだ。
「こんなにうるさいのに、谷地さんのことしか考えられねー」
最初の花火が打ちあがった。
子どものころから何度も見た花火。
二人の男女がそれぞれ違う携帯電話でカメラ機能を立ち上げている。
いつか思い出話に花が咲いて燃え上がるのだろうか。
彼はわくわくしているだろうか、私もわくわくできているだろうか。
先に知ってはいないだろうか。どうせ物質だということ、意味がないということ、それぐらい簡単に日々は奪われてしまうということ。
どこからか聞こえてきた「たまや~」の声に、横の白本さんを見た。
「私たちも言いますか?」
はいといいえのどちらでも退屈な質問で、何かを思い出したように笑い。
白本さんは手でメガホンを作って、大きな声で叫んだ。
「うーーーーらなーーがやーーーーーーー」
何もかも知ってしまうぐらい繰りかえされて、なのにやってきた、初めての夜。
私は何を知らないのか知っていると思っていた。
いつもと同じ午後、ショッピングの帰り道、車道側を歩く女の子に母親が笑いながら注意して場所を変わった、私は鉄骨にはぶつからなかった、あの日、大きな音と悲鳴と衝撃と痛みが同時にやってきたその日、見えているのに何も見えなくなった瞬間、私はぶつかってきたものがなんであるのか見えないのに知っていた。
暗闇からぱっとあらわれて消える白本さんは、宙でいきなり爆発が起きたみたいに、その破片を目で追おうと忙しく、しかし静止して没頭している。
「奇跡みたいだ」
彼の爪が一度、私の手首に刺さって、それから元の位置に戻るように自然な調子で手の甲にわずかにくいこんだ。
人間には心がある。しかし私にはその心がよくわからない。すべてが突飛に思える。言葉と言葉がなぜ繋がって会話になるのか理解できない。だってそこにいる二人はそれぞれ異なる夢をもって違う感想を抱いて大切にしているものだって同じではないのに。
「ほんとうに、奇跡みたい」
話が続くこと。ふいに終わること。何もかもが、あらゆることが私を驚かせる。きっと私だってたくさんの人をびっくりとさせてきた。それでもだれも、あまり怒らず、私もそこまで怒らず、抑止力のように脅かしあいあって、平衡を保ってきた。
この世に当然のことなんてない美しさのもとで、同じ理由でだれかが死んだ。
どうせ驚かせるなら、いきなり生き返ってくれればいいのに。それだけは絶対に起こらないから、いつも泣きたくなる。