解決済ゴースト
男子中学生がスパムメールで可能性の幽霊を解決するオンライン小説です。
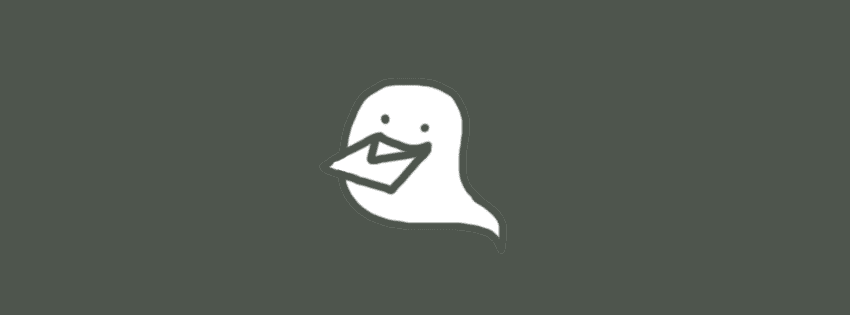
幽霊の足音を知っているかと聞かれたとき、目前の男がむだに電源を入れた多くのパソコンから聞こえてくるファンの音と、冷房と、時計の針、回転椅子に座ってくるくると回っている永川部長の口笛がたえまなく場を温めていたので、少なくともここにゴーストは現れないと答えた。四方原有は使いもしないディスプレイの電源ボタンを指でぽちぽちと押し歩きながら「手紙を投函した男は何足歩行をしているか?」と言った。
「二足歩行だね。なぜなら四足だとポストに手が届かない」永川部長は短い腕を大きく広げてえっへんと口に出した。
「永ちゃんはバカだな。こんなに愚かで高校受験はどうなることやら。身長制限があるのは遊園地のアトラクションだけではないというのに」四方原の言葉に永川部長こと永遠の小学五年生こと永川尚樹こと略して永ちゃんは「一年生に心配されたくない!」と怒鳴って、その勢いで椅子から転げて机の陰に消えた。
「正解は四足歩行。手紙を投函した瞬間に、届いたかもしれない届いた、届いたかもしれない届かなかった、届かなかったかもしれない届いた、届かなかったかもしれない届かなかったの四つの可能性を地につけて成立するから」
コンピュータ室のすべてのパソコンが動作をはじめ、すべてのディスプレイがログオン画面を映し出す中、四方原はふたたび僕の前にやってきて近くにあった椅子に腰を掛けた。
「なるほど、まったく分からん。それがいったい文化祭の出し物にどう関係するんだ?」
僕の質問に「そうだよそうだよ」と永ちゃんが立ち上がってとてとてと近づいてきた。彼は僕の椅子の背もたれを愛おしそうに撫でて、対面の四方原を睨みつけた。
「ここはポエム部でもクイズ研究会でもなくてパソコン部だからね。いくら他の部よりも何でもやれる幅が広いからといって、そんな、そんなの、そんなのだめ」
「確かに。パソコン部ならブロック崩しゲームやジャンケンゲームを制作したり、文化祭当日に撮った写真を加工してプリントしてあげたり、ペイントソフトで描いたイラストを展示したり、ムービーを作って発表したりできるかもしれない」
「できたよ、してきたよ、前の代もその前の代もそうしてきたよ」
「みなが均してきた道を進めば転びやしない。四足で歩けばだれも転ばない。だが、安全に安心すると通り雨にやられる。人生には水たまりを越えるための足の長さが必要」
「助けて羚くん!」
泣きついてきた永川部長を「うるせえ」と肘で突き飛ばして、僕は四方原の表情を窺おうとしたが、彼はあいにく天井を見ていたので顎先しか分からなかった。
「幽霊に足がないと聞いたことがある。なら切り捨てられた二足は結果だったのか、はたして仮定だったのか。心踊る」
「踊らないよ。踊り場と聞いて踊り出すタイプでしょ。あそこは踊る場所じゃないんだよ」
ぱさっと四方原の前髪が額に落ちたとき、僕はやっと彼の顔を観察できた。眉は緩く垂れ、長い睫毛が重なりあって、唇はやすらかに笑みを作っていた。ありもしないやわらかな風を受け、聴こえもしない美しい音楽に癒されているかのようだった。
「今年の文化祭は高度なスパムメールを作ろう」
スパムメールにとって電子メールフィルタリングに阻まれることなく誰かのメールボックスに届けられることは、普通に進学して普通に就職して普通に結婚するという人間の夢と同じく切実な問題とされている。と、四方原はスパムメールの気持ちを代弁しながらペンのお尻でホワイトボードを叩く。こん、こん、と響く先には“ベイジアンフィルタ”や“自然言語処理”、“マルコフ連鎖”などの単語が書き殴られており、僕の一つ前の席で説明を聞いていた永川部長の頭はがくがくと上下に揺れている。襟首をつついて起こしてやると彼は背筋をぴんと伸ばして、ぽりぽりと脇腹を掻いた。
「送信メールボックスには確かに残っているのに、実際には届いていない。こうした歪さが幽霊を許す」
「でもスパムメールが受信ボックスに届くのを許したらだめだよ」
「もちろん、実際にスパムメールを作成して送信しようものなら、当然足がつくし、先生に怒られるし、謹慎を言い渡されるし、部長の貰える見込みもない推薦が永遠に取り消される」
「おそろしい」
「そういうわけで、自動生成したスパムメールを手紙に書いて下駄箱に投函しよう」
永川部長は椅子の力でくるりと僕の方に向き「そんなことありえる?」と呟いてからそのまま回転を続けて前を向いた。
「しかしメールのフィルタリングと違って、下駄箱はどんなものでも受け入れるぞ」
「今年のバレンタイン、ぼくの下駄箱には赤と白のしましま靴下が入っていたよ」
「人間の判断がメールのフィルタリングをつねに超越しているなら? 人の心を動かす手紙は、フィルタリングを突破しうるスパムメールといえる」
「だけど今どき手紙なんて珍しいだろ。読まずに食べてしまうかもしれん」
「この前、牧場に行ってヤギさんのおなかを触ったよ」
「その点はすでに解決済みだ」
四方原有は親指と人差し指だけでペンの頭を持って、ぶらぶらと、底にたまった少量の液体をゆらす素振りでこう言った。
「毒を塗る」
まだ少し暗さの残る朝だった。入ってもいない部活の朝練に行く時間帯に、石巻小次郎は自分の下駄箱を開けて、閉めた。
「おい、閉めたぞ」
「案ずるな。上履きを取り出すには現実に直面するしかない」
「ちょっと二人とも、押さないでよ。は、はみ出る。下駄箱の陰からはみでる!」
閉ざされた扉がまた開かれたとき、石巻小次郎の横顔は硬直して、赤くなり、青ざめて、見回し、押し出されてずっこけた永川部長に向けられた。
「ぉ、ぉはょぅ」
「お・は・よ・う。今日はいつもより早いなあ」
「き、昨日までに先生に提出しないといけないプリントがあってね。今日、先生が来る前に職員室にしのびこんで机にこっそりと置いてきたんだよ」
「卑怯だなあ」
永川部長は隠れる僕たちに視線だけを送って口に出してもいない「えっへん」を物語っていたが、立ち上がる前に石巻小次郎が去ろうとしたので、すがりつくように彼の足をひっぱった。
「それで! コジーはどうしたのさ。ちょっと挙動不審だったよ」
「じつは、靴箱のなかに何かがあって」
「何かが?」
「でも生まれてきて何一ついいことのなかった俺に何かがあるなんてありえないから、きっと見間違いだと思うんだ」
「そ、そっか。だったら開けてみなよ」
「だけど見間違いでなかったとしたら?」
「したら?」
「俺はパニックだ!」
「確かめる前からパニックだ!」
「だから今日は靴下で過ごそうと決めたんだ」
晴れやかな顔をして靴下で闊歩する石巻小次郎の背を見送ったあとで、僕たちは永川部長を囲んだ。彼は振りほどかれた腕を伸ばしたままうつ伏せになって、上目でうるうるとこちらを見つめていた。
「おい、読まずに食べられもせずになかったことにされたじゃねーか」
「目撃者の存在で怖じ気づいたのかもしれない。永ちゃんの口は体重と同じぐらい軽い」
四方原は石巻の靴箱から取り出したハート柄の封筒をつまんでぴらぴらと空気にさらした。軽い衝撃にはびくともしないその姿に、折りたたまれて固くなった手紙を認めた。
「せっかく姉のリップクリームで封をしたというのに」
「それの何が毒なんだ?」
「舐めたらファースト間接キスを奪われて死ぬ」
「石巻だって女の子と間接キスぐらいしたことあるだろうよ」
「さっき彼も言っていた。青春は羽ばたけない人の時間」
「幻聴だぞ」
「ぼくはいつ起き上がればいいの?」
自教室に向かって歩きながら、僕は四方原から渡された封筒から便せんを取り出した。ナチュラルなコットンペーパーに、薄茶色の罫線が並んでいて、右下にねこの絵が描かれていた。太い、鉛筆のような掠れた線でねこは丸くなってZの文字をぷかぷかと浮かべながら目を閉じていた。肝心の本文は、三つ折りでできた線の上から二つ目にも届かない短いもので、三人のなかではもっとも字のうまい四方原によって紙のへこみが気になるぐらいの筆圧で書かれていた。教室についたとき、僕はふたたび手紙を封筒に入れて、ズボンのポケットに押し込めた。すでに着席していた四方原は電子辞書を開こうとしていたところだった。が、彼の席の前に座っていた家島那々花が急に立ち上がって振り向いたので、手を止めたらしい。二人の顔つきは真剣で、僕が彼の斜め前にある席につくころには、はっきりと会話を聞き取れた。
「小次郎のヤロー、どうしてあっしに相談してくれないと思う?」
「保守的な男は女に助けてもらおうとは考えないものだ」
「ならあんたが聞けよ。男同士だろ」
「保守的な男は男に助けてもらおうとは考えないものだ」
「保守的な男ってサイッテーだな! ひとりで死んじまえっ!」
ぷいと前を向いた家島と目があい「聞いてんのか統原」と聞かされてもないのに怒られて、僕はしぶしぶと首を横に振った。
「なんとだ、小次郎の上履きが盗まれた」
「本人がそう言っていたのか?」
「言わなくてもわかるさ。なぜならあいつの靴下にあっしの上履きの痕がついているからね」
「偉そうに言わんでいい」
家島は顔を両手で覆ってから「このディジタル社会に靴を隠すいじめなんて」と嘆いたが、指と指のあいだからふひふひと空気のような笑い声が漏れていた。
「案ずるな。その点はすでに解決済みだ」
「なにがいったい解決済みなんだって?」
開いた手を顔の横でぱたぱたと動かして挑発する家島を前に「悩む人だけが現実に直面しなくて済む」と四方原はあくびをしながら電子辞書を開いた。
「可能性がないとき、現実には何かがあった」
「なあ、統原。四方原なぐっていい?」
「めいっぱい殴れ」
猛攻を避けながら四方原は何も言わずに僕を指さした。一発食らわせて満足したらしい家島に睨まれてしおしおと手紙を取り出そうとしたところで、つるつるとした袋布だけが指にからみつく。待ちきれない家島の拳がすぐ目前にまで迫っている中で、反対側のポケット、胸ポケットをひっくりかえして、引っ張りだすようなそぶりを解いて、こう言った。
「なくした」
たまごを挟んだコッペパンを食べながら四方原は眉間にしわを寄せていた。外はやけにムシムシしていて、やたらと密生している雑草のせいで、中庭のベンチはちょっとした拷問器具と化していた。ここからは教室に面した廊下が見えた。頭だけしか見えなくても足や腕があって相応の運動をしていることが当然のように想像できた。隣からぽつぽつと聞こえるとりとめのないポエムが電子掲示板に書き込みをする人工無脳の話になったとき、僕はようやく口を挟んだ。
「なぜ人工無脳だとわかったんだ?」
「『目玉焼きには塩が最高』という書き込みがあったとして、人間はこれを目玉焼きに何の調味料が合うかの文脈にあると判断して『醤油が好き』『いや、ソイソースがいい』『せうゆしかありえない』と答える。人工無脳は文章の意味を理解できないから『目玉焼き』という単語だけに反応して『今日の朝食は目玉焼きだった』『友達が目玉焼きになった』と答える。このとき、掲示板で学習した単語を織り交ぜているので、その書き込みは浮いていないように見える。が、きちんと読まなくても、レスポンスが不自然でやりとりが成り立っていないとわかる」
スパムメールのアイディアは人工無脳から着想したのかと聞けば、四方原はコーヒー飲料をがぶがぶと飲んで「話せば怖い話になる」とつぶやいた。
「発売されたばかりのゲームについて調べていると、あらゆるゲームの批評を投稿できるサイトを見つけた。そこで誰かもわからないレビュアーの一人が何千字も使って作者宛の感想を書いていた。『もう少し誤字脱字等に気をつけて、プレイヤーのことを考えて作ったほうがよいと思います』そのサイトは非公式で、ゲーム作者の家でも庭でも職場でもなかった。そのレビュアーは一般人で、ゲーム作者の友人でも先輩でも師匠でも恋人でも家族でもなかった」
「どこが怖いんだよ」
「彼は、彼らは、ないことを想定していない。あるかもしれないとすら思っていない。ないかもしれないことの上に生きていることを知らない」
家島に押しつけられたぞうきんの水をしぼっていたところで、開いていた廊下側の窓からぴょこっと永川部長の顔が飛び出した。
「有くんは?」
「いないですけど、どこかにいるでしょう」
「そっかあ。ならあとで伝えてほしいんだけど、ぼくたちの手紙がすっごく話題になってるんだよ」
「ああ、拾われたんですか?」
「拾われたって? あのね、靴下でいるところを先生に見咎められたコジーがしぶしぶと先生をつれて下駄箱を開けたら、あるはずの手紙がないってことで大騒ぎしたんだよ。『初恋チャンスが夢の跡!』『ハートがないハートがないハートがない!』って。だから手紙はこっそり処分して、三人で口裏を合わせようね」
「手紙なら僕が紛失しました」
ぱち、ぱち、ぱち。永川部長は大きなまばたきを繰り返したあと、僕の頬にまで手を伸ばしてぺちっと叩いた。
「端的に暴行だ」
「ご、ごめん。なんかつい叩きたくなって……そ、そっかあ。なくしちゃったかあ、ああ、ああ……ぼくの推薦が取り消されたらどうしよう?」
項垂れる永川部長の後ろに立っていた四方原は、彼の両肩にぽんと手を置いて左右に軽く揺すぶった。
「そんなものはどこにもない」
「ゆゆゆゆ有くん、ぼくたちの仕業だとわかったら一大事だよ」
「案ずるな。その点はすでに解決済みだ」
「おまえの解決済みはあてにならん」
ぐったりとする永川部長の髪をくしゃくしゃとしながら、四方原は「すでに事切れているのだから手の施しようがない」と言った。
「手紙には宛名もなければ、差出人を特定できる情報もない。筆跡はいつもと変えている。何よりまだテスト段階のワードサラダだ。勘のよい教師が『これは永ちゃん率いるパソコン部の仕業だな』と気付いて永ちゃんの内申点を下げることはあっても、大事にはならない」
「そりゃよかった」
「よくない、全然よくないよ。ぼくの人生の一大事だよ!」
騒ぐ永川部長を二人でくすぐっていたところで「号外だよ、号外だよ」と小さな声が聞こえた。窓から身を乗りだして廊下を見れば、新聞部の変態が紙を窓に貼り付けている。彼は僕たちの視線に気付くと、そそくさと逃げ出してしまった。廊下に出て、三人で紙の前に立つ。新聞と呼ぶにもおこがましい出来で、文書作成ソフトウェアにテキストを流し込んでそのまま印刷したような作りだった。横書きで、発行日、題字、主見出し、袖見出しと、リードが続き、細かな字がずらずらと並んでいる。主見出しには「ウブ男 ついに春か」、袖見出しには「二人からの真剣告白」、リードには「石巻小次郎氏は本日、二人の女子生徒から告白を受けた。一人目の告白は手紙で行われたが、差出人不明で石巻氏は『朝に下駄箱で見つけたきり手紙は消えていた』と説明している。二人目の告白は口頭で行われた。お相手は家島那々花さん。手紙の話を聞きつけた家島さんが掃除時間中に石巻氏を呼び出して告白したとみられる。」とあった。
「ありもしない恋文でありえないカップルが誕生した!」
天を仰いだ永川部長の首の後ろをむにむにと触りながら四方原は「題名さえあれば、語りたいことを好きなだけ語れる人がいる」と言った。
「大きな見出しの最後に『か』がついているときはまだ何も判明していない」
促されるかたちで本文を読めば、確かに家島は石巻を呼び出したようだが、そこでどのような会話があったのかはまだ分かっていないとされていた。
「それにありえないというのもないな。案外、石巻と家島はお似合いだろ。近所だし、付き合い長いし」
帰りのホームルームが終わって四方原と廊下を出ると、家島が石巻を殴っていた。生徒らは二人に視線を合わせないように端を歩いていたが、僕たちは家島に見つかってしまい「新聞を見たか?」と聞かれたので「見ていない」と四方原が先に答えた。
「なら見るな。もし見そうになったら目を潰せ。怖いなら私が手伝ってやる」
「石巻は新聞を見たから制裁されているのか?」
僕の問いに家島は少し落ちついた様子で「ううん」と言った。
「殴りたかったから殴っただけだ」
「そうか、お大事に」
「ご大切に」
コンピュータ室に向かう途中で、僕たちは足を止めた。今、まさに上ろうとしていた階段の踊り場で男子生徒が踊っていたからだった。彼は僕たちに気付いていない様子で、四方原が声を掛けてもニコニコとしながら傷だらけの鞄を振り回していた。僕たちは目で交わし合ってその場を去ったが、彼の陽気な足音がどこまでも聞こえた。迂回路である廊下はどこか薄暗く、何かが出てきそうな予感があったので、僕は口を開くしかなかった。
「小さい女の子の胸を触ったことがあると話したとき、おまえは何も言わないですぐに調べてくれただろ」
「ああ。結局、それは女の子の格好をさせられていた永ちゃんで問題にならなかった」
「僕は宛名がだれであろうと、書いたことは変わらないと思っている」
階段を上っている間、僕たちは何一つ話さなかった。三階に出て少し歩きだしたところで四方原は「その点はすでに解決済みだ」と言った。
「被害者がいると思って苦悩した。しかし相手は何も思っていないどころか、楽しい時間を過ごしたと喜んでいた。それを正そうとしても、お前が清々とするだけだ」
「なら四方原はどうだ。きちんと僕を軽蔑しているか?」
明かりのついたコンピュータ室の少し手前で彼は立ち止まった。ありもしない煙草を咥えて、ありもしない煙を吐くようなポーズをとって、四方原はぷいと横を向いた。
「怖い話の続きだ。ある作家がブログでエゴサーチに関する記事を投稿した。彼女は自分宛に届いたファンレターやメールしか読まないと言い、個人のサイトや匿名掲示板で何を書かれてもどうとも思わないと言った。『ない。ない。ないったらない。届かない。君の想いは届かない。当然のように読んでもらえると思ったら大間違いだ。君は私の世界にいないし、そもそも君が生存していることすら私は知らない。』彼女の言葉に少しだけ安らいだ。たとえ特定のだれかに宛てた文章でなくても、届かなくても届いた。しかしそれは彼女の届けたかったことではない。届いた手紙は、まさしく自分で書いた」
手紙によって手紙を書かせることは善であると四方原は付け足して、僕の顔を見ることもなくコンピュータ室の扉を開けて先に入った。彼は僕の問いに答えたくないのであり、なぜかといえばどう答えても彼の誇りを傷つけるからだと僕は書いて読んだ。室内ではすでに冷房が効いていて、永川部長はホワイトボードに猫の落書きをしていた。
「遅いよ二人とも。待ちくたびれてつよい猫を創造したよ」
「そんな真似をしている暇はないぞ、永ちゃん。スパムメール計画が頓挫した今、文化祭に向けて新しい企画を立ち上げなければならない」
「うーん。せっかくここまで頑張ったのに、すべて無に帰するなんて。どうにかならないのかな」
「無理だろ。落とした手紙が誰に拾われているか分からん。騒ぎになっている今、続けるのは危険だ。僕のせいだけど」
「そうだよ、羚くんのせいだよ! ……だけど、あの手紙が真剣に読まれていたとしたら?」
声を上げたのは四方原だった。永川部長はふしぎそうに首をかしげて続けた。
「人の心を動かす手紙は、ええと、フィルタリングを突破できるスパムメールなんでしょう? もしかしたら成功しているかもしれないよ」
「永ちゃん、あれは未完成だ。あんな文面を信じる人なんていない。自分のせいだが」
「そうだよ、有くんのせいだよ! ……だけど、もしかしたら、もしかするかもしれないし。待ち合わせ場所に行ってみようよ」
僕たちのやったことは極めて単純なことだった。現代ではどんなやり方もアフィリエイトブログに記されており、それはラブレターの書き方についても例外ではなかった。僕たちは例文を集めて、面白半分で持ち寄った小説や漫画を用意した。あとは可能性の問題だ。「私は本屋に行き、彼は映画館に行った」の「私」は「彼」に「本屋」は「映画館」になりうるが、「行った」は「私」や「に行った」にはならない。名詞のあとに名詞は続かない。連体詞と助詞も連接しない。そうやって次を現時点での起こりうる可能性に照らして決定してゆく。だから「彼は映画館に行き、私は本屋に行った」は生成されても「に本館行き彼は、映画に屋は行き私」は生成されない。
ただし僕たちは一文だけ付け加えた。「屋上近くの非常階段で待っています」そんな可能性はないと少なくとも四方原は思っていた。彼は石巻小次郎が手紙を読まないこと、あるいは先生がいたずらだと考えて破棄する可能性を信じていた。だから、投函した。
永川部長が非常階段につながる扉を開けようとしたとき、だれもいないように思えた。が、すぐに足音が聞こえてきた。ぱたぱた、ぱたぱたと、上履きの薄い底がコンクリートに打ち付けられて鳴っていた。三人で見上げたとき、彼は踊り場で踊っていて、右手にはしわくちゃになったハートの封筒があった。固まる僕と四方原を置いて、永川部長は段を上り「何かいいことがあったの?」と聞いた。彼は動きを止めて「お手紙!」と言った。
「机の引き出しに、お手紙、ありました。書いた、引き出しに、お手紙、好きと、ありました」
四方原、なぜ人工無脳だとわかったんだ? どうして「今日の朝食は目玉焼きだった」と書いたら非人間的なんだ? おまえは相手の文脈をすべて理解した上で応答しているのか? フィルタリングに掛けて迷惑フォルダーに振り分けられたら一様に迷惑か? 何事も再考する必要もないほど解決されているのか? あると思い込んでないのに応えようとする者を恐れるのは近親憎悪か? 好きと書かれて自分がだれかに好かれている可能性を素直に信じることはそんなにありえないことなのか?
しどろもどろになった永川部長を退けて、四方原は男子生徒の前に立った。僕には彼の背しか見えなかったが、その表情がありありとわかった。四方原はまず、おそるおそると男子生徒に向かって手を伸ばした。自分より小柄な彼をこわごわと抱きしめた四方原は、彼の左肩に顔を押しつけて、そのまま、はっきりと叫んだ。
「おれは、君のことが大好きだよ!」
可能性があるとき、現実には何もない。
四方原、今なら僕はこう答える。手紙を出した男には足がなかった。もはや歩くことを放棄して、自ら幽霊になったのだ。ありもしない幽霊の足音を僕は知らない。そして、僕たちが無邪気に踊って温めるこの場所にゴーストはきっと現れない。だから、案ずるな。その点はすでに解決済みだ。