ゆきづまり殺し
男子高校生の恋人がとつぜん男になるオンライン小説です。
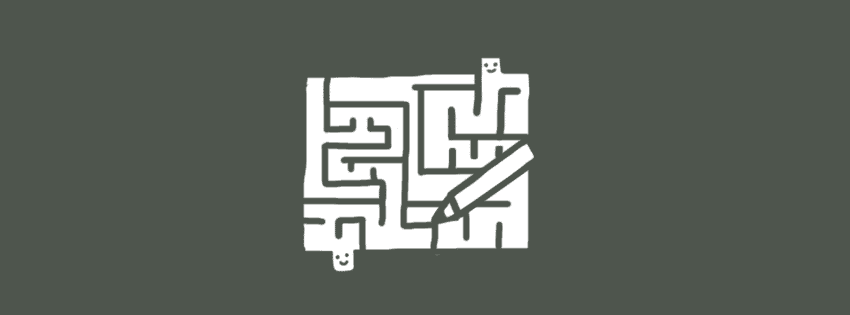
死人は、生きかえらない。奇跡でもないかぎり。そして奇跡は、起こらない。だからもしだれかが生きかえったとしたら、その人はもともと、ちっとも死んでいなくて、せいぜい仮死状態で、こちらで勝手に死んだと思い込んでいただけで、生きながら火葬しようとしていただけで、ドンドンと内側からノックされたので気づいただけで、実際には生きたままだった。そういうケースが多いんじゃないかと、思う。少なくとも今回のケースは、そういう、たぐいだ。
死んだと思った恋人が帰ってきた。長くて綺麗だった髪を短くして。手術のために切り落としたらしい。それでも美しいままで。六月なのに長袖のシャツを着ていた。からだのいたるところに小さな傷があるらしい。丁寧で整っていた字が崩れるようになっていた。半身に軽いしびれが残って以前のようには動かせないらしい。だけど指のしなやかさはかわらずに。そのように、いろいろな部分が欠け落ちて、だめになって、変わっていたけれど、一応は帰ってきた。そう安堵していた僕に、彼女は、彼女の部屋で、辺りを、彼女の趣味で飾りつけた部屋を、不安げに見回しながらこう言った。
「おれ、女の子になっちゃった!」
いつも温厚だったおじいさんが突如として怒りっぽくなるとき、頭に腫瘍ができているかもしれない。人の心は簡単に変わる。物質だから。損なわれるだけで気が狂う。正常とされるはたらきが鈍る。実際にありもしないものを見る。考える。思考が滅裂になる。サンマの話をしているかと思ったらトイレットペーパーの芯に着地してしまう。頭を構成している物質が、ちょっと少なくなったり変わったりするだけで。信念とか、理性とか、今までの努力も、功績も、そんなものは何の役にも立たず。物質どおりの生き物になる。
町居ユキは高校二年生で、三角比の問題を解くことができる。記すのに時間をかけながらも教育漢字を書くことができるし、漢文も読める。発声に問題なし。リスニングも。自分の名前を知っている。家族構成も分かっている。人の顔の見分けがつく。でも元から女性であること、僕の彼女だったこと、現在進行形で、そうであってほしいと僕が願っていることを最初から知らないみたいに覚えていない。さながら、そんな設定のパラレルワールドに来たみたいに。彼氏を招くのではなく、同性の友達を招いたみたいな調子で、彼女は僕をベッドに座らせて、自分はといえば勉強机の回転椅子でくるくると回りながら「なんかこの部屋、すごい雌っぽくない?」と言う。他人事のように。でもそれが君の趣味だったんだよ、とか、それで僕も君にうさぎのぬいぐるみをプレゼントしたんだよ、とか、そもそも僕は君の彼氏なんだよ、とは言えなかった。彼女のお母さんが、一度そう、説明して「そんなわけあるか」で一蹴されたと聞いて、僕の口からそれを告げる勇気がなかった。だって「そんなわけあるか」って、そんなわけあるか?
ユキは、そう、以前からそう呼んでいた。それもすごく前から。幼稚園のころから、あるいはそれよりも前から。ユキはスカートを嫌がった。それはもう嫌がって、一緒に登校しようとした僕を殴ろうとすらした。彼女の母親と父親はすでに一発をお見舞いされたらしく、娘のかわりように怯えてすらいた。だから僕が説得しなければならなくて、でもそのことは苦じゃなかった。
「だからさ、ユキ。スカート履きこそ男らしいんだよ」
ユキは玄関前の廊下で膝を抱えて、僕をひどく睨みつけていた。彼女のこんな顔を見たのは初めてだった。ユキはいつも穏やかで物静かで、自己主張の少ない、やさしい子だった。それが今では白いパンツを丸見えにしながら、こちらを見上げて唾を飛ばしてくる。こんな風に。
「意味分かんねえよ。じゃあなんでおまえはズボンなの!」
「僕は女々しいからさ。内面だけいうとどう見たって男らしくないから、格好まで女の子らしくするといよいよ男だと気づかれなくなる。そうすると男子トイレが使いづらい」
「うむむ」
「でもユキは僕と違って心から男だ。だからスカートを履いても問題ない。真の男だから。真の男はいくら髪が長かろうとスカートを履こうと胸があろうと女に見間違えられることはないから。そしてスカートはめくればすぐに下着にたどりつくから。男子トイレが使いやすい」
「ぐぬぬ」
そうやって連れ出したユキが、さっそく学校で男子トイレに入ろうとしたので、僕は急いで彼女の肩を掴んで「しびれがあるんだろ。ゆっくりできるし多目的トイレを使ったほうがいいよ」と言った。ユキは、少し不服そうに「おれのトイレ事情になんでそんなに必死なんだよ」と呟き、スカートのひだの一部を指ではじいた。
ユキの友達は僕の友達でもあったから、ひとりひとり、直接顔を合わせて、どうか彼氏と彼女の関係であることは教えないようにしてほしいと頼んだ。その一人である井本は、廊下をぐねぐねと蛇行しながら切りすぎてぱっつんになった前髪をつまんで「なして?」と聞いた。
「今はその、ショックを与えてはいけないような気がする」
「交際の事実でショックを受けられたらあんたの方がショックでしょ」
「だから言わないんだよ」
「あ、じゃあさ、あんたとあたしが付き合ってることにする?」
「なんでそうなるのかなあ」
「その方が自然でしょ」
「井本の前髪ぐらいにね」
蹴られた尻を擦りながら教室に戻ると、ユキは僕の机の上に購買で買ったらしきパンを重ねてタワーを作っていた。そのタワーは僕の着席と同時に崩れて、メロンパンにいたっては僕の上履きに落ちたのでつまんで拾ってユキの額に押しつけた。
「待たないで先に食べてよかったんだよ。というより、友達は?」
「だって女子に囲まれて食べるの、はずかしいじゃん」
「でも、友達だったろ」
「だった、わけよ」
ユキはそっぽを向き、教室の窓から見える少しの空に「何なのこの青さ。世界が滅亡するんじゃねえの」と驚嘆しながらパンを食んでいた。その日、世界は滅亡しなかったが放課後に雨が降った。天気予報も予測していない、ひどい雨だった。二人して傘をもってこなかったので、湿っぽい昇降口で待っていた。でも雨が上がる気配はなかったし、やさしい生徒会役員や職員が傘を貸してくれる機会も訪れそうになかったし、何を待っているのかよくわからなかった。雨を見ていると僕は不意にすごく悲しくなって、叫びだしたくなった。僕には、気づきたくないことがある。ユキは気づいていたのだろうか。こちらをじっと見つめて、少しのぞき込みさえして、でもユキは僕より背が小さかったから、ただふだんどおり、見ていただけなのかもしれないけど、雨の音にかき消されそうなぐらい小さい声で「おなかすいた」と言ったから、僕はユキの手をとって雨の中を駆け出し、はしゃぎ回り、ぐちょぐちょになった靴下をさらにわざと水たまりにひたして、道ばたの葉をはじいてどうせ全部雨で見えなくなるのに互いに水を掛け合ったりしてみたけれど、濡れたユキの長袖シャツが透けて下着の形が丸わかりになったので、ああ、僕はなんてバカなんだろうと誰にツッコまれるまでもなく、ひとりで笑って、泣いた。
日記を探そうと提案したとき、ユキは嫌がった。すごく嫌がった。プールの授業と同じぐらいに。あるいは生理で股から血が流れたときと同様に。そのころには、といっても、まだユキが帰ってきてから数週間しか経っていなかったけれど、僕はユキのそうした状況にある程度の理解があって、理解というより、一つの絶望的な推測があって、とにかく僕は動じないつもりでいた。枕を投げつけてきたユキの次の言葉を聞くまでは。
「他人の書いた日記なんて読めるか」
僕と付き合いはじめたとき、ちょっとした会話でユキが律儀に日記をつけていると知った。どんなことを書いているのか聞いたとき「絶対にひみつです」とユキはなぜか丁寧語で答えた。当時、彼女は背中の半分よりちょっと上ぐらいまで髪を伸ばしていて、僕と二人きりでいるときは、いつもポニーテールにしていた。僕は彼女の無防備なうなじにキスをしながら、つやつやとした髪を少し唇で咥えて、気づかれて、怒られたものだった。はにかみ屋で、秘密主義なユキ。それはすでに過去のもので、原型すら留めていないという以前に今のユキとまったく別物なんだろうか? 懇願するように、すがりつくように、日記を探そうと言った。「他人の日記かもしれなくても、読むんだ。何か、書いてあるかもしれない」
「何が?」
「楽しいことが。うっかり自分の思い出にしてしまいたくなるような、素敵な出来事が」
僕は立ち上がってユキを見下ろしていたが、ユキはあいかわらず回転椅子に座って、宙に伸ばした足をばたつかせていた。家に帰ってすぐに地味な部屋着に衣替えしていたのでパンツは見えなかった。それで、ユキは僕をじっと、少し嘲りの含んだ顔で、そんな表情も今まで見たことがなくてまるで別人のように、見つめて、手を差し出した。白く長い四本の指が波を作るように動く。ぎこちなく、こわごわと。
「そんなものが書いてあったとして、だったらおれは今、どうしてこうなっているんだ?」
僕はユキの手をとって今すぐ口のなかに入れて温めてやりたかった、けど、そんなことはできなくて「良い思い出はたくさんあっても少ないぐらいだから」としか言うことができなかった。
彼女の両親は僕より参っていたに違いなかった。だって、ユキはもはや以前のユキとはまったく違っていて、大股で歩き、大声を出し、大いびきをかく。スカートの中が見えることなんてまったく気にせずに、爪もガジガジと噛んで、ときどき四足歩行になり、それはもちろんふざけているだけだけど、でもユキはそんな変な真似はしない子だった。少なくとも、僕たちはそうだと思っていた。夏休みが近づいていると野生の勘か暦で気づいたユキは日に日に気分が高まってきているらしくて、口調はクリアになり、本当に、透明な物言いで、すれ違った他のクラスの女の子の膝の裏を目で追いながら「すけべしたいなあ」と口笛を吹くようになった。僕はそれに乗っかるべきか咎めるべきか笑うべきか泣くべきかもう分からなくなって、ユキがいない場所でも何が言いたいのか、何を思っているのか、めちゃくちゃになってきて、ユキが壊れているという診断を下されるより前に僕が壊れてしまうという気がして、それでも、離れられなかった。だってユキは、以前の大人しくて繊細だったユキより、ある意味で危なっかしくて、きちんと見てやらないといけなくて、手を引いてやらないといけなくて、叱ってやらないといけなくて、手が掛かったから、僕はあの頃のユキのことを考えるより、深く、ずっと、ユキを見て、ユキを想像し、ユキを愛していた。しかし彼女はそんなこともつゆ知らず「今の子、ブラジャーが透けてた」と嬉しそうに言うから、僕の心は傷つかないように、もう傷つかないようにと、どんどん閉ざして冷たくなっていった。
女友達と疎遠になったユキだったが、井本だけは別だった。というより、むしろ熱心なぐらいで「めっちゃカワイイ。すき」ときらきらした目で語るので、でも井本にはめちゃくちゃカッコいい彼氏がいるんだぜ、しかも僕とユキがキューピッドになってくっつけたんだぜ、と言いたくなって、そんな自分の心が本当にイヤになって、ユキみたいに、頭を強く打って、血を流して、その血はすごく汚い血で、それを全部捨てて、綺麗にまっさらになりたかった。井本といえば軽い調子で「でも仕方ないじゃん」という。ユキの居ない場所、中庭、また雨が降りそうな天気の下、汚れることも厭わずに上履きで二人、歩いていて、井本は大きなくしゃみをする。
「ユキがあたしを可愛いと思うのは仕方ない。なぜならあたしは本当に可愛いから」
「でも、ユキの言葉はそれだけの意味じゃないと思うんだよ」
「どんな人の、どんな時の、どんな言葉にもどれだけの意味があるんだろうって、考えることができるんじゃないの」
僕までくしゃみをしそうになって、それぐらい埃っぽくて、なのに湿って重たくて、夏休みが来る前に大雨ですべて流されて何もかもなくなってしまいそうで、そう願っているだけかもしれなくて、いつも明るい井本まで少しすねた調子で言う。
「意味を考えたくなるのは、それだけ好きだってことで、それだけ好きなら、もうどれだけ考えても足りないでしょ。だから打ち切らないと。途中で、決着をつけないと。永遠に生きられるわけでもないしね」
ところが僕とユキは昔、永遠の愛を誓っていた。名も知らぬ雑草の茎で互いの薬指を結びつけて、このコウソクはあまりにもゼイジャクですぐに壊れてしまうものだけれど、それは形が失われたり変わったりするだけで、意味が変わるわけではないというような話をしていた。それも、ユキの日記に書かれているだろうか。美しい、おとぎ話のように。あるいは封印されているのだろうか。いったんは忘れるために残すメモのように、記されているのだろうか。永遠のことを。そんなにも簡単になくしてしまえるんだろうか。物質が、壊れてしまったがために?
ユキは「生きなければ」と言った。今まで散々生きていながら何を言うのかと思えば、パジャマを買いに行きたいらしい。「自分の好きな柄のパジャマを着て眠らなければ、自分の人生を生きたと言えない」電車に乗って、ズボンで完全に見えなくなったユキの白い膝を想像しながら、バカじゃねえのと、何なんだよおまえは、赤の他人だったらとっくに殺してるぞ、死ねよ、なんで死ななかったんだよ、と、僕は不意に嗚咽をもらしそうになって、恋人の膝が見えないぐらいで苦しんでいる自分の頭に苦しんで、その隣でユキは窓の外を見ていて、まるで子どものように、無邪気に感嘆の声を上げていて、何度も見た景色のくせに、何度もそうしたくせに「乗り物にのって出かけるとなんかわくわくするよな」なんてしみじみと言うから、鼻水が出そうになる。そうしているうちにも時間は過ぎていって、電車は目的地に辿りつくし、僕たちも店に辿りつくし、ユキはお目当ての品に辿りつくし、その品というのがデフォルメされた飛行機がプリントされたいかにも子どもっぽいパジャマだしで、早くこいつを殺さないといけないという念が強くなる僕の前で、ユキは本当に、飛び跳ねるみたいに、買ったパジャマを抱きしめて、喜んでいた。
内省ばかりしている自分に気づいて、かつての僕はこんなにも考えることはなかったのにと思い、恨めしい思いで、脳天気そうに欠伸をするユキの首を絞めてやりたくなって、でも一緒にパンをかじっている井本が「夏休みはどうするの」とこれまた脳天気な話を振ってきたので、僕は肩をすくめた。
「受験勉強かな」
「それは当然やるものとして、他にすることあるでしょ」
「その、みんなが他にすることをしているあいだに、さらに勉強をして差をつける予定だよ」
「つまんねーやつだね、あんた。彼女とデートぐらいしなさいよ」
井本の言葉にユキが「あれ、彼女いたんだ」と不思議そうに言うので、僕は「いたんだけどね」と返した。「別れたの?」と聞かれたので「自然消滅かな。自然、ではなかったけど。むしろ不自然消滅といってもいい」と謎めかしたので食いついてきて「何があったんだよ」と聞いたので「それは僕が聞きたいよ」と答えたら、いろいろと不憫に思ったらしい井本が話題を変えようとして「あたしは彼氏とプチ旅行に行く予定だよん」と言ったので「えっ、彼氏いるんだ」とユキが意気消沈した。
髪の短くなったユキは、それでも女にしか見えない風貌で、実際に女で、月に一回、生理になって、わめいて、胸もあって、頬の線がやわらかくて、元男と言い張るのに苦しいぐらい声がやさしくて、それをユキも薄々と気づいているようで、だから僕の友達の前では「オホホ」とか「ウフフ」とかわざとらしい態度を取っていて、それが僕の神経を逆なでしていた。なんだって、そのようなふるまいをするんだろう。脳が、脳にある物質がそうしろと命令しているからだろうか。その物質のせいで何もかも間違えてしまったのだろうか。僕はだれもいない自分の部屋でひとり、いつも祈っていた。部屋の中央で、冷たい床に膝をついて。僕をもう解放してください、ユキから逃げさせてください、すべて、許してください、そう願っていた。僕はかつて、ユキとこんな遊びをしたことがある。チラシの裏、真っ白で、つるつるで、ボールペンのよく滑るあの広大な白に線を引く。最初に長方形のなりそこないを書く。何がなりそこないかといえば、辺の上下、二箇所だけ線が途切れている。スタートとゴール。ジャンケンで守備と攻撃を決める。勝ったユキが攻撃側となり、スタートから線を引く。僕はその線がゴールに辿りつかないように、また違う線を引いて、彼女を迷路にいざなう。線と線がぶつからないように、しかし僕たちの腕は自然と交差しながら、互いに体を押しやって、進んでは咎め、進路を変えさせ、やがて、僕たちの線は壁に当たる。そこからは引き返すこともできず、進むこともできず、ただ手を離して放棄することしかできない。ユキは、覚えているだろうか?
そもそもユキの日記はどうして簡単に見つからないのだろうか、とベッドの下をのぞき込みながら考えているうちに、そもそも紙に書いていたとは言っていないと思い出す。もしかしたらパソコンで書いているのかもしれない。だから僕はパソコンを見せてほしいと言ったが、ユキはかたくなに背中でかばう。これは怪しいぞと思って腕力でユキを引きはがしてみると、アダルトな広告が画面に表示されている。
「お金を払わないと消えないらしいんだよ。どうしよう」
「下着でも売れば?」
名案だ! と顔を輝かせるユキに「絶対にやめとけ」と忠告した僕は広告を無視してフォルダの中身を調べようとしたが、すべてのファイルが暗号化されていて開けなかった。
「それもお金を払わないと使えないらしい」
「内蔵でも売るか?」
名案だ! と顔を輝かせるユキに、僕は何一つ言ってやることはできなかった。日記らしいファイル名はなかったし、ファイルサイズから見ても、もちろん暗号化されているので実際のサイズはもう少し大きいのだろうけれど、長文が残されているとは思えなかった。パソコンのデータをすべて消去して新しくやり直したほうがいいとユキに提案したが、ユキは「でもせっかく集めたえっちな画像が」とぐずついたので初めて彼女の肩を殴った。
女友達との付き合いがぐっと減ったユキは、かわりに僕や瀬谷とよく話すようになった。彼は井本の彼氏であり、僕たちの中学のときからの友人であり、真っ当な人間であると思っていたけれど、ガードの緩くなったユキに対して化けの皮がはがれたらしく男同士のスキンシップと言わんばかりにボディータッチを繰り出すようになったので井本に告げ口して教育してもらった。それからというもの瀬谷は僕の失敗を手を叩いて喜ぶようになり僕が躓いて転びそうになったものなら「神様ありがとう!」とどうせ信じてもいないなにかに礼を言うようになった。ユキといえば瀬谷からもらったらしいアダルト画像を僕にも共有しようとしてきて「おまえもそろそろ大人になったほうがいい」と囁いてくる。僕たちはそういう意味ではもう大人で、取り返せないぐらいに大人で、だけどそれを知っているユキはもうこの世のどこにもいなくて、精子と卵子は出会わず、月経ですべて水に流れたか捨てられて、あの瞬間はもうどこにも見当たらないから、本当に、子どもみたいに、その場に座り込んで泣き出してやりたかった。
手のしびれで早く字を書けなくなったユキは、自分でも何を書いたかよくわからないと言って僕に泣きついてくる。ノートを見せてやっても、それを写す手が震えていて、僕は彼女のペンを奪い取って、何もかもしてやりたいと、頼ってほしいと、助けてあげると、守ってあげると、そのときを待っている。だけどユキは僕の視線にまったくの無関心で、一生懸命に書こう、書こうとするから、心の中で、頑張れ、頑張れ、と言いながら、これ以上、頑張らないでほしい、これ以上、僕が存在する価値を失わせないでほしいと苛まれている。今日も僕のノートを写したいということで、彼女の部屋に行って、僕の家よりユキの家の方が学校から近かったから、それで僕はユキがノートを写しているあいだに日記を探していて、もはや真相を知りたいという気持ちは失せていて、ただユキより早く日記を見つけてやりたいという気になっていた。だって、その日記は隠されたもの、あるいは、処分されたかもしれないもので、僕はそういう気持ちになったことがないから分からないけれど、でも想像できる。隠したのは見せたくなかったから、そして隠したものを暴こうとする人だけに見せたかったから、って。
それにしても僕は男子高校生で、ただの、ふつうの男で、だからユキがいくら女の子になってしまったと叫んだところで、僕は彼女を抱きしめたり噛みついたり舐めたり吸ったり何もかも奪い征服したいと思っていた。たとえば僕の頭を切り開いて、どこかを、ぷちんと切ったりぐちゃぐちゃにしたりしたら、そういう気持ちもなくなって、消えて、さっぱりするかもしれないけど、逆を言えばそうでもしないと抑制できない想いなんだって、開き直って発作のように襲いたくなるけど、ユキが「夏休みになったら冷房をガンガンときかせた部屋で毛布一枚にくるまってスイカの形をしたアイスを食べながら高校野球を見るんだ」と言うので、僕は縮こまって、おさえて、深呼吸をする。
「ずっと家にいるのか。せっかくの夏を」
「母さんが、いろいろとうるさいから」
「どういう風に?」
「おれのこと、あんまり人前に出したくないみたいなんだ。変になったから」
ユキはペンを投げ出して、回転椅子をぐるりと回転させて、床に這いつくばって日記を探している僕を見下ろして、履いていた靴下のうちの片方を足の指で不器用に脱がした。
「おまえはおれとずっと一緒にいたんだろ」
「そこまで忘れたの?」
「覚えてるよ。でも、結局、おれの頭はおかしいんだから、その記憶だってあてにならないんじゃないかって気がして」
すごくイヤな予感がして、僕は何か口を挟もうとしたけれど、その前にユキが続けた。
「おれも、日記を探そうかなって思った。そもそもおまえが必死になって探している状況も変だし。だいたい何なの? おまえはおれのただの友達だろ。どうしてそんなに親切なんだ?」
ユキはまっすぐと僕を見ていた。何も隠さずにすべてをあらわにしているかのように。あいかわらずセンスのない部屋着を着ているくせに、僕には彼女が全裸に見えた。それは煩悩のせいかもしれないけれど、とにかく、ユキはすべてをさらけだすような覚悟で、しかしそれは子どもじみた決意で、僕にすべてを委ねようとしていて、僕はというとそんな重みには耐えられなくて、たとえ一瞬のことだとしても無理で、今すぐに死んだほうがマシで、何なら生きたまま火葬されたいぐらいで、火に放り込む前にだれかがドンドンと外側からノックしても絶対に僕は返事をせずに、気づかれないように悲鳴すらあげずに、ただ黙って焼かれたいと願うのだったが、流れ星に三回願ったってそんなことは叶いっこなかった。
「好き、だからだよ。大好き、だからだよ」
「ええー、そんなに好きなの?」
「うん」
「なら、ならさ。おれも一回だけしか言わないけど、おまえのこと好きだよ、いっぱい大好きだよ」
僕たちは告白した。小さな子どもたちが何のためらいもなしに互いの頬や唇にキスをして喜びを分かち合うかのように。ユキは笑っていた。僕も笑ったが、笑いたくなかった。もう、たった一回しか言ってくれない。僕もこれでもう何も言えない。本当は毎月毎週毎日毎時間毎分毎秒、言っても足りないぐらいだったのに。愛してるなんて、もう二度と言えない。
二人が協力すれば、案外と早くに見つかるものだった。僕たちは日記を、分厚いノートを、表紙と背表紙を貼り合わせて一つの形にした、その証を、庭の中央にぽんと投げ捨てた。倉庫から持ってきたバケツに水を汲んで、非効率的なバケツリレーの末に、日記のそばに置いた。その水面がぴたりと静止するころには、勉強机の引き出しにあった、なぜか消しゴムの隣で眠っていた、安っぽい、おもちゃのようなライターに火がついた。その色でユキの瞳がいっぱいに満たされていて、僕の手が動いて熱い軌跡ができるたびに、ユキの黒目がせわしなく追った。数時間前、あんなに照っていた日はもう落ちかけようとしていた。ふっくらとしたごはんに卵と鶏肉が乗っているような匂いが漂っていた。「ずっとこうしてるとふとももの裏に汗をかくよな」なんて茶化していたユキも、やがて口を閉ざした。が、開いた。
「あーあ。芋を用意すればよかったな」
「ひどい点数のテストもね」
「そんなものはもはやこの世のどこにもない」
そしてユキはもはやこの世のどこにもいない。
点火する。激しく、燃えない。じわじわと端からむしばみ、焦げて、消えてゆく。ユキのいた証が。僕たちが殺した、ユキの亡骸が。
「なんかさ、もっとぱあっと燃やしたい」
「ユキの部屋にある、気にくわないの。全部燃やそうか」
「おまえにしては大胆発言だな」
「他人の遺品を減らそう。ぽっかりと空いた場所に、ユキのものを増やそう。いっぱい。たくさん」
「いっぱいとたくさんって同じじゃないの?」
僕の手からライターを奪ったユキは、死んだはずのユキは、まだ自由に動かない体で、震える手で、まだ半分以上も残っている日記を火にさらした。すると、今までじりじりと進んでいた証拠隠滅が、途端に勢いよく捗りはじめ、というより燃え上がり、炎上し、ついにすべて黒くもろくなって、指でこすれば、少し熱くも元の土と混じりあった。
ユキ。乱暴でがさつでお調子者で、可愛い女の子を見るとそれだけで人生が楽しそうなユキ。僕の幼なじみ。僕の親友。僕の大好きな人は、僕や、両親や、友人たちや、周囲の人々によって、少しずつ毀され、ぼろぼろになって、変わっていって、跡形もなくなって、自殺してしまった。死人は、生きかえらない。奇跡でもないかぎり。そして奇跡は、起こった。
「次はあのフリル枕を灰にしてやる!」
生きながら燃やされた、死んだと思った変人が帰ってきた。すべての人に惜しまれながら、あのころと同じままの天真爛漫さでよみがえった。さっそく次の獲物をとりに駆け出すユキのあとを追おうとしてバケツに足をひっかけてひっくりかえす。ユキが振りかえって腹を抱えて笑う。それはもう下品に。歯を見せて。舌まで出して。
迷路に閉じ込めて作り出した、僕の恋人はもういない。
「おい、早く来いよ! 部屋ごと全部燃やしちゃうよ」
完全犯罪の、その犯人は、内側から響くノックを忘れられない。ぺちんという音。夏の日。汗と汗のにじんだ腕がぶつかる。壁を作りながら、追いつめながら、あどけない顔をして愛をうたった筋違いの日々。そのすべてを押し殺して、殺して、殺して、殺す。
「ああ、先に行ってよ。水をかけてから、完全に火を消してから」
もう君を追いかけないから。
僕の青春を、君のゆきづまり殺しに捧げる。