切っても切れない斧
女子中学生が友のために空想を振りかざすオンライン小説です。
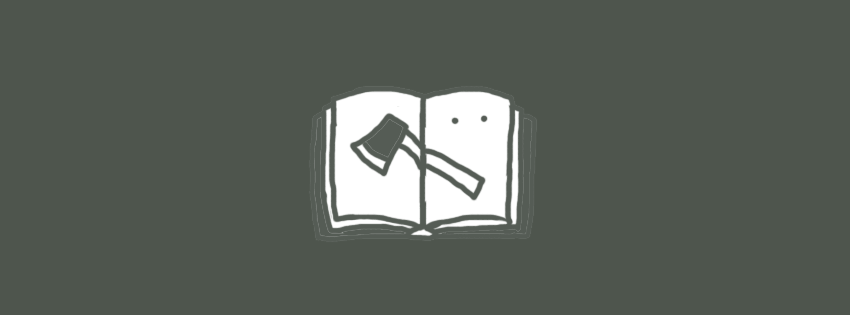
悪魔に百日を売って切っても切れない斧を手に入れた。中学二年生の春および夏はんぶんの重みを両手に感じながら、部屋の中央で斧をぶんぶんと振る。終業式には、学校に、行くぞ。すっぽ抜けた斧がわたしの本棚に直撃した。横に広めの本棚は中身といっしょに斜めにすぱーっと切れた。人生初の袈裟切りに興奮しながら二つに分かれてしまったお気に入りの一冊を片手ずつ持ち、慎重にくっつける。すると、先ほどまで個々別々の状態にあった本が元通りになる。
切っても切れない斧は、切れるけど切れない。作用するけど作用しない。生き物を切っても死なない。ばらばらにしたら前のかたちのようには動けなくなるけど動く。くっつけても動く。切らなかったときと同じようになる。だから、切っていないことと同じになる。
愛おしいわたしの百日、もとい斧を膝において刃の部分を撫でる。ベッドはわたしたちの重量だけへこみ、それも立ち上がれば以前と変わらない姿になる。そういうわけで、ベッドはわたしたちに怒ることはできない。だって、何も奪われていないのだから。何もされていないのだから。この斧だってそうだ。本質的にだれかを傷つけることはできないから、もしわたしがこの斧をだれかに振るっても罪にはならない。ばらばらになるけど、くっつくし。きれいな見た目のままだし。なおるし。
というわけで、わたしは一学期の終業式に出席して一年のときから持ち上がりの先生とクラスメイトたちをバッサバサに一刀両断してめっちゃくちゃにくっつけなおしてやるつもりだ。まず、男子と女子の腕と腕を入れ替える。とってもおもしろいことになる。次に、背の高い男子と背の低い女子の足を交換する。すっごく楽しいことになる。最後に、頭と足を逆にくっつける。今は夜だからわはわはと控えめに笑ったけど、本当はベッドで跳ねた反動でお月様のところまでぶっ飛んでしまいそうなぐらい、うれしい。これがわたしの百日の成果だ、あっはっはっ、みてろよ、おぼえてろよ、ぎったぎたのばっきばきのばっらばらにしてやるからな。でも、最後には最初と同じようにくっつけてあげる。それで、両成敗。それで、おしまい。
本物の斧を振り回そうとは思わない。流れた血はけっして元の管に戻すことはできないし、切ったものは縫わないとくっつかない。ぬいぬいしてもくっつかないかもしれない。これを不可逆と言う。やり直せない。取りかえしがつかない。わたしの切られた髪はじっくりと待っていたら以前の長さに戻った。殴られたときのあざも消えた。だから、これぐらいで許してあげる。斧に取りかえた百日は戻ってこないけど、それでも許してあげる。
斧といっしょにベッドで眠りながら、わたしは計画のことを考えた。本番当日、斧で人を切ってくっつかなかったらどうしよう。つまり、斧はものを切れるようで切れないけど、人を切ると切れてしまうというような。ありうるかもしれないな、みんなみんな嘘つきだし、斧の効果だって嘘かもしれない。どうせ嘘だと思っているくせに、都合のいいことは本当だなんて信じているから、だまされる。始まりが嘘ならどこまでも嘘。ぜんぶ、すべて、何もかも、嘘。
横で寝ている斧が寝息を立てていないことを確認する。わたしはだまされてやらないぞ、と心のなかで斧に闘志を燃やす。斧で人を切ったときにどうなるかを確かめよう。まずは、小さく。次は、大きく。大なり小なり最後にはくっつく。
わたしは窓から顔をひっこめて鍵を閉めた。ママは冷房で長い時間からだを冷やしたらだめだからと換気の重要性を説いてくるけど、本当に言いたいことは「長い時間」なんだろう。大丈夫だよ、ママ。パパとママがお仕事に行っているうちに、きちんと斧の使いかたを覚えて、学校に行って、成敗して、ちゃんとちゃんと勉強するから。だから今だけは冷房をつける。両手の力を抜いて、しばらくエアコンの下に立つ。何もしていないのに火照るようになったわたしのからだを冷却する。手足の先端からひんやりとしてきて、やがて中心につめたさが集まってくる。凍りつくわたしの心のかわりに頭に血がのぼる図が見える。よし、斧を振るぞ。かぶせていた枕を取り払い、片手で斧を持ち上げてみる。重いのですぐにもう片方の手を添える。ゆるゆるとからだごと回転して目の前に棚も机もないところを見る。まっさらな壁ににっくきクラスメイトたちの顔を浮かべて斧を振る。ザク、ザク、ザクッ。これはナイフの音か。ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン。何を割ったんだろう。ドゴ、ドゴ、ドゴ。よい音が決まった。ドゴ、ドゴ、ドゴ、ドゴ、ドゴ……ドゴドゴしているうちに疲れてきた。壁の時計を見るともう放課後だ。みんなはこれから部活に行く。塾に行く。映画館に行く。ゲームセンターに行く。学生限定のやっすいでっかいパフェを食べに行く。わいわいする。わくわくする。わたしは斧を振ってへとへとになっている。しかも、これから、いやなことをする。
ベッドに腰を下ろして、わたしは左手の小指を見つめる。なぜ、左手の小指かと言うと、そんなことを言ったらなぜわたしだったんだろう、世の中には答えのないこと、あったとしても納得しがたいこと、割り切れないことがたくさんあるけど、今回については実際に切断して接着できなかった場合に不便そうでない部位をチョイスした。片足を切って戻らなかったらずっとケンケンになる。小指だったら日常生活はへっちゃらだろうし「なんか掟でも破ったのかな」って思われる気がする。
わたしの小指、手のひらについた小指、くるりとひっくりかえして甲についている小指、意外と指ってまっすぐじゃないんだな、指、短く切りすぎた爪、かじかじしたことを隠すためにパチンとやりすぎたのだ、爪、のついた指、の上に載せる斧、切っても切れない斧、ほかの指まで切ってしまいそうだ、手のひらを胸の高さに、付け根から斜めに切ろう、薬指と小指のあいだに斧の刃を差しこむ、切れる、切れる、絶対に切れる、でも切れない、切れない、絶対に切れない。
指が落ちる前に、斧が落ちた。わたしははあはあはあはあはあはあははははと笑いすぎて呼吸困難になるみたいにあえいだ。なんだ、わたしだってみんなと同じぐらい楽しんでいる、楽しまされている、おまえに相応の娯楽はこれだけだと制限されている、わたしはばかであほでまぬけなのでよろこんで自分のからだを切り落とそうとしている、わははははははあはあはあはあ。
床に落ちた斧を眺めているうちに、チャイムがぽんぴんぽんぴん鳴っていることに気づいた。ずっと、ずっと、もしかしたらわたしが小指と向き合っているときも、きっと。どたばたと階段を下りる途中でスリッパの片方がぬげる、廊下を走っていてもう片方もぬげる、玄関の床はひんやりしている、開ける。
そこには小野ちゃんが立っている。
小野ちゃん、クラスで唯一のわたしの友だち。物わかりがよくていつもわかるわかると言っている。クラスメイトたちに冷笑されてもわたしに話しかけてくれる。わたしが避けても話しかけてくれる。わかるわかると言うくせにわたしの意図はわかってくれない。こっそりつけた蔑称、わかる小野ちゃん。
わけがわからないほど優しい小野ちゃん。
外はまだ明るかった。ちりんちりんと自転車が小野ちゃんの後ろを通り過ぎていった。小野ちゃんが先に口を開いた。
「電話、何度もかけてなー」
「き、気づかなかった」
「シナプス可塑性の可能性に賭けるゲームをやろうぜってメッセージを送ってな、何の反応もなくてな」
「ずっと寝てたの、あの、ほら、わたし、病人だから、あは、ははは」
小野ちゃんは笑わなかった。むすっとした顔で横を向き、からだの側面でぐいぐいとわたしの背を押しながら家に侵入していった。客用のスリッパには目もくれず、廊下と階段に落ちていたわたしのスリッパを強奪する。ズドドドドド。むだに激しく駆け上がって部屋に到着するころにはおなじみの笑顔になっていた。
「心配したぞおまえー」
部屋の扉をバタンと閉めて、小野ちゃんはわたしに頬擦りをした。ぺろぺろと舐めてもきた。わたしはほっぺたが必要以上に赤くなっているかもって意識したら意識しているみたいで恥ずかしいかもって意識したら血の巡りがよくなってきたって意識したらほっぺたが……羞恥心がぐるぐる増幅して爆発する前にベッドに背中から飛びこみ、小野ちゃんもエヘエヘと笑いながらついてきて、発見した。
「なにこれ」
斧。
小野ちゃんは、斧を持った小野ちゃんは……ベッドに四肢を放り投げていたわたしのことを見下ろしていた。
「なあなあー、なにこれ」
「えっあ、あの、斧、斧なんだけど、でも」
「斧で自分のことをぶった切ろうと夢中だったから連絡とれなかったんだ」
「ちが、違わないけど」
斧の柄を曲げた膝に押しあてた小野ちゃんはふんぬと力を入れて割ろうとしたみたいだったけど、割れるはずがないのでひとり悶えた。
「うっうっう、こんな、おまえ、そんなのないじゃんな。あたしといっしょにいるより斧で叩き割られるほうが幸せなんてな、なんだったんだ、なんだったんだ今まで……」
わたしは立ち上がって、えーんえーんと嘘泣きをする小野ちゃんから斧を奪おうとした。小野ちゃんは片手でひょいと斧を天に掲げた。手を伸ばしてぴょんぴょんと跳ぶと、親友の顔をした敵は腕をぷるぷるとさせながら「残像だ」と斧を振った。
「い、いじわるしないで」
「なあにがいじわるだー。あのな、つらいにしても、し、し、ひとりでいなくなっちゃだめだあ。ひとりで、そんな、いやだいやだこわいこわいと思いながら、そんなのなあ、つらいよりつらいぞ」
「だ、だから誤解なの」
「斧の殺傷能力に誤解も誤報もあるかあ」
わたしは切っても切れない斧の説明をした。この斧は切っても切れないから殺傷能力もゼロ。小野ちゃんは斧を床にそっと置いて酷使したほうの二の腕をもみもみしながら「なんでも話を聞いてみるもんだな」と納得してくれた、と思ったら口をとがらせた。
「でも本当に切っても切れないのか試してたんだろ。自分のからだで」
「き、切ろうとしたけど、切れなかっ、いや、切らなかったから」
「切ってないだけで切っていいと思ったらもう切ってるじゃんか」
わたしは首をかしげた。小野ちゃんも首をかしげた。ふたりで左右に首をかしげた。
「とにかくこわい思いをしたんだろうがー」
頷く。頷くと途端にこわくなってきた。次の言葉を発声しようと思ったとき、からだが勝手にぶるぶると震えた。
「自分で自分のからだを切るのって、こわい」
「わかる」
よしよし。小野ちゃんはわたしの頭を人差し指で撫でた。でもいったい小野ちゃんに何がわかるんだろう。
ぎゅっと抱きついてみる。無防備な胴体に巻きつく。しがみつく。これはわたしのものだ。わたしのもので、わたしの本体だ。
わたしなんていなくても小野ちゃんは存在できる。でも、小野ちゃんがいなかったらわたしはいられない。
「好きぃ、小野ちゃんのことが好きぃ」
「吊り橋ドキドキすきすき効果だー」
「今だけの話じゃないの。いつも毎日ずっと小野ちゃんが好きぃ」
「ほんとかなあ」
「もう家に帰らないで。学校に行かないで。ずっとずっとわたしといっしょにいて」
小野ちゃんはわたしを抱きしめかえした。お天道さまの下ですくすくと育った骨太い抱擁だった。
「わかる」
「だ、だからね。わたしは切っても切れない斧で自分を切らなきゃだめなの」
「うっうっ、おまえは接続詞の使いかたも忘れたのかあ」
窓の向こう側が暗くなってきている。わたしのからだは現在進行形で上下に真っ二つにされそうになっている。
「小野ちゃんには小野ちゃんの人生設計がある。家に帰らないと家族が心配するし、学校に行かないと進路とか就職とか将来がめちゃくちゃになる。だから、わたしは小野ちゃんを引き留められない。わたしが小野ちゃんに合わせて進まないといけないの」
もう大丈夫だという意味で小野ちゃんの背中を叩く。でも、本当は、もう大丈夫だというより、息苦しかった。
わたしの合図に、小野ちゃんは静かに離れた。
「学校なんて行かなくていいんじゃね」
「現実的に考えると、そうはいかないと思う」
いつもの笑顔に戻った小野ちゃんは両手を背中に隠して「現実なー」とつぶやく。わたしは床に落ちている切っても切れない斧を拾う。
「小指がなくなっても、これまでどおり社会の一員として認めてほしい」
「それ、あたしじゃだめかー」
「いくらなんでも斧に嫉妬しちゃだめだよ」
「そうじゃなくてよお。本番ではスパスパ切るんだろー。だったら小指よりもっと大きな部位で試したらどうだね」
小野ちゃんは床に足を伸ばして座った。ギコギコと声に出しながら緩慢に背中を床にくっつける。最後に祈るように手を胸の前で組み、おまけにわたしをじっと見上げた。
「だ、だめだよ。本当に切れちゃったらどうするの」
「おまえに殺されるなら本望かもよ」
「小野ちゃんを傷つけちゃったら、わたし生きてられない」
「わかる」
わかっていないわかるの魔法が斧を軽くする。二年生なのに新品みたいにパリパリとしている制服のシャツが呼吸で上下に動いている。わたしは両手で斧を持つ。
「反撃するんだろー。だったら人を傷つけることに慣れなきゃな」
「わたしのこと、本当に信じているの」
「おう。だから首を狙って」
膝をついて立つ。小野ちゃんは目をつむって唇を突きだしている。わたしは誤って斧を落としそうになり、なんとか握りしめなおす。
「小野ちゃんが死んじゃったら絶対にあとを追うから」
「早う死なせてくれ」
頭上に持ち上げた斧を勢いよく振り下ろす、ナイフで常温のバターを切るなめらかさで小野ちゃんの頭が胴体から離れてわずかに傾く、床だけが悲鳴を上げてわたしから斧を奪いとる、頭と胴体のあいだで床に突き刺さる斧が、すべて、ぜんぶ、みんな切り離してしまったことを教えてくれる……自分の小指を切り落とすことにはあんなに躊躇したくせに、友だちの首を切り落とすことにはまったく躊躇しなかった。
「なんかへんな気分だなー」
「ごめん、ごめんね、小野ちゃん」
「謝るならこっちを見て言えー」
邪魔な斧は取り払い、できるかぎり小野ちゃんに顔を近づける。傍から見たら押し倒しているみたいに、でも、実際に第三者から見たら凄惨な事件現場に違いなかった。
「切っちゃった、小野ちゃんのこと切っちゃった、ごめんね」
「くっつけたら切ったことにならない理論!」
わたしは小野ちゃんの頭のてっぺんをぐいぐいと押して、切り離された首にくっつけた。小野ちゃんは瞬きを三回したあとでくしゅんとくしゃみをして、全身を一瞬だけ床から浮き上がらせた。
「ほら切られてない。だから切ってない」
でも、だけど、仮にくっつけなおすことができても、自分を守るために小野ちゃんを犠牲にした事実は残る。わたしの記憶にも、小野ちゃんの記憶にも。
「でたらめにつけなおして元に戻るかも試せ試せー」
「そ、それは、わたしのからだでやる。小野ちゃんはもう帰って」
完全体の小野ちゃんはまだ起き上がらない。もう一度、何度でも切り刻まれることを待っているみたいに、祈るように、無抵抗で、わたしを見上げている。
「もっとおまえに切断されたいなあ」
「こわい」
「おまえがあたしを切るときのな、緊張を見ているとほっとする。すごく大事にされている気がして」
小野ちゃんは横目で斧を見る。邪魔だからひとまず床に刺しておいた斧。床のきずは指で擦ったら消える。くっついてなくなる。なかったことになる。
大事だから切れない葛藤は残るのだろうか、大事なのに切った事実だけが残りはしないか。目を閉じた小野ちゃんは「ん」と固めた左の拳で床を叩く。緊張を見たいんじゃなかったの、小野ちゃん。
左腕、右腕、左足、右足と切断していって息をついたときに気づいた。わたしはまだ胴体にくっついている小野ちゃんの首の横に膝をつき、彼女の眉間の皺を指でぐっと伸ばした。
「い、痛かったんじゃ」
「日課の小顔トレーニングだあ」
「でもちょっと苦しそうな顔だった」
寝息のような微かさで小野ちゃんは笑いだした。そのうち「ちょ」や「ちょっと」が聞こえてきて「ちょっとってそりゃ」といつもの声量に変わった。
「生きながら四肢を切断されてちょっとで済むなら痛くないのと変わりないだろうがー」
左腕を切り離したときから思っていた、わたしは小野ちゃんをちょっとずつ物質にしている、右足を終えたときには気づいていた、左腕を切ろうとした時点で物質として見ていた、だから切れた、だからいくら小野ちゃんの痛覚について気にかけても、これから小野ちゃんの胴体を切り刻んで八等分にしても、残忍さが変わることはない。だって、残忍か残忍でないかの二択しかないから。
「ほらほら、早く手足をくっつける」
前例のないかけ声に促されつつ、わたしは小野ちゃんの手足を無秩序にくっつけた。左腕のあるべきところに左足、右腕のあるべきところに上下を反対にした右腕、左足のあるべきところに右足、右足のあるべきところに左腕。小野ちゃんはうなりながら床に左足をついて右足と左腕で立とうとしたが、何度かお尻を浮かせただけで首を横に降って、ゆっくりと背中から倒れた。
「足という名の腕がボキンといきそうな予感があった」
「す、すぐに元に戻すから」
元通りにするには小野ちゃんのからだを切断する必要があった。今は間違えているから。間違えているから切って貼りなおさないといけない。ドゴンドゴンドゴンドゴン。小野ちゃんの手足が胴体から離れる。くっつけなおす前に、わたしは膝をついて小野ちゃんの胴体を抱き起こした。
「なになに」
「あ、あのね、わたしが小野ちゃんをすべて貰い受けることは、小野ちゃんの今後を考えると、だめ、だけど、あの、わたしたちの生活の多くって手足がやるものでしょう。ノートをとったり持久走をやったり」
「それは手足だけの功績じゃないけどなー」
「だ、だからね、小野ちゃんの手足だけ家でごはんを食べて、学校で授業を受けて、残りの小野ちゃんがここにいたらいいなって思ったの」
まつげとまつげがぶつかる近さで見合う。小野ちゃんの目はきらきらとしている。濡れてかがやいている。生気に満ちている――手足をもがれているのに。
「わかる」
「でも現実的に、手足だけでは学校に通えない」
「まあ、まあ」
「それでもほしい。目の前にいなくてもいるって感じられるように。小野ちゃんの一部分、小野ちゃんのいちばん大事なところがほしい」
「どうしよっかなあ」
「ほしい」
「あっ、待て。もしかしてうんって言わないと手足くっつけてもらえないやつじゃんか。ずるいぞー」
「ほしい」
小野ちゃんは「うーん」と軽く頷いた。わたしはシャツ同様にピッカピカで皺ひとつないスカートをめくって小野ちゃんの大事なところを切り取った。寝ている小野ちゃんに見えるように横を掴んで持ち上げる。指を添えていないのに切り取られた布が前後にくっついたままだ。風を吹きかけても落ちそうにない。
「ふーふーするなあっ」
「もし、もしね。これから小野ちゃんが泥道で転んじゃったとしても、小野ちゃんはきれいなままだよ。だってここに本当があるから。大事なところはわたしが大事にしているから、小野ちゃんは汚れない」
玄関の扉が開く音がした。わたしは小野ちゃんの大事なところをベッドに置いて、迅速に小野ちゃんの手足を胴体にくっつけて立たせた。こうして見てみると大事なところがぽっかりと失われていることはわからなかった。小野ちゃんはベッドの上に沈んでいる自分の大事なところを見ていた。雨が降りだしそうなあの空気と同じように、小野ちゃんは何かを言いだしそうだった、けど、部屋にママがやってきて雲が散らされてしまったので雨は降らなかった。
お風呂の時間、小野ちゃんの大事なところを持って浴室に行った。大事なところを片手に乗せて、上から温かいシャワーを浴びせると下着の色が濃くなった。布に覆われていない肌の部分をふわふわに育てた泡で優しく洗ってあげる。布に覆われている部分には泡をつけた指で上から擦る。くぼんでいるところを指でふかふかと押して布にやわらかに抵抗される。シャワーを再開して泡を流す。鼻先に近づけて、よいにおい、わたしが使っている石けんの清潔なにおいがすることを確かめる。そして湯船にいっしょに入って、小野ちゃんの大事なところがぷかぷかと浮くか試してみる。わたしの手の支えを失った小野ちゃんの大事なところは空気をぷくぷくと吐いたあと、ゆっくりと浴槽の底に沈んでいった。
わたしは足の指で海底に眠る宝箱を探り当てる。あまり切っていなくてちょっと長くなった親指の爪で破って侵入できるか、力をこめて、離れて、こめて、離れて、確かめるけど、最終的に膝を腕で抱えて浴槽の端っこに縮こまり、自分のつま先を、だれかを傷つけてしまったときに道具をまじまじと見るように、見る。
このとき、わたしの足は手のようだった。水のなかに小野ちゃんを押さえつけて窒息させようとしている手。
もふもふのタオルで小野ちゃんの大事なところについた水滴をぬぐったあと、片手でドライヤーを持って上から熱風をかけてあげる。湿って黒っぽくなった布地をめがけて、大事なところを持っているわたしの手のひらが熱くなるぐらいまで。でもなかなか乾かなかったから、小さなミニタオルにつつんで部屋にもっていった。わたしは小野ちゃんの大事なところをほとんど使っていない学習机の上に置いて、デスクライトをつけた。椅子に座って頬杖をつく。ミニタオルをレジャーシートみたいに下敷きにして存在している小野ちゃんの大事なところ。むきだしで、でも布に覆い隠されている秘部。頬杖をしたまま片手で小野ちゃんの大事なところをつつく。つんつんつんつん。そして撫でる。優しく。這うように。いきなり抓る。引っ張る。ねじる。小野ちゃんの大事なところがびくびくとしている。首を絞められて痙攣するわたしのからだみたいに。もがいている。苦しんでいる。わたしは手で小野ちゃんの大事なところを掴んで握り潰そうとする。
どう、わかる、わかる、小野ちゃん。わたしのこと、本当にわかってた?
ぷるぷる……ぷるぷるぷる……となりで眠っていた小野ちゃんの大事なところの振動で起こされたわたしは急いでトイレに駆けこんだ。トイレのふたを開けて、小野ちゃんの大事なところを水のなかに落とさないように便器の奥に近づける。昨夜はあんなに頑なだった布が今ではぺらっと剥がせる。激しさを増すぷるぷるはわたしの腕をつたって胸から足までを震わせる。
大丈夫だよ小野ちゃん、ここはトイレだから大丈夫だよ。
声をかけてもぷるぷるはしばらく続いた。伸ばした腕がつらくなってきたところで、ぷるぷるが弾けた。
しゃあああああああああああああ……。
腕を振って、小野ちゃんの大事なところの水気を切ってあげる。重ねたトイレットペーパーでふわふわと覆ってあげる。湿って張り付いた紙を取り払ってあげる。きれいにした小野ちゃんの大事なところを片手に持ちながら、洗浄レバーに手をかける。トイレのなかにたまった黄色の水を見る。レバーを回す。黄色の水はまたたく間に消えて、かわりにきれいな水で満たされる。こうしてすべて水に流れる。
わたしは学習机に置いた小野ちゃんの大事なところを横目に斧を振るう。空を切る。でも本番は切れる。切れない。切っても切れない斧は切れないけど切れる。断ち切れる。わたしは小野ちゃんと制服デートをする。きらきらとした人たちがきらきらとしながら飲んでいるきらきらとした飲み物をふたりで飲む。おしゃれなカフェで勉強もする。ファミリーレストランでも勉強をする。いっしょにいい高校に行く。ずっとずっと遊ぶ。勉強もする。いっしょにいい大学にも行く。大人になっても遊ぶ。ずっとずっといっしょにいる。断ち切らない。わたしと小野ちゃんは切っても切れない。切っても切れなくても断ち切らない。わたしは小野ちゃんが好きだ。だから切っても切れない斧で切る。みんな切って切って切れない切れない過去を断ち切る。
ぷるぷる……ぷるぷるぷる……お昼休みのまんなかだ。わたしは小野ちゃんの大事なところを持って、ふたたびトイレに入った。指にずっちりとした生命の重さを感じつつ、朝と同様にわたしは待っていた。でもぷるぷる、ぷるぷるぷるぷると震えるばかりで一向に始まらなくて、終わらない。
大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。
上下に揺らしてあやしながら思った。今、この瞬間、わたしと小野ちゃんは別の場所で同時にトイレに入っている。それが事実としてわかることはすごいことだ。たとえば、あるふたりが片手に電話を持ちながらトイレに入って「トイレに入ったよ」と報告しあうとする。だけど片方は嘘をついているかもしれない。本当は押し入れのなかで丸くなっている。もう片方も嘘つきかもしれない。本当は事前に用意した録音を再生している。見えないときは信じるしかなくて、信じているだけのときは事実でも事実じゃない。嘘をつかれているかもしれない葛藤が付きまとう。でも、今だけは本当だ。今だけは絶対だ。だから、小野ちゃん。こういうときだけ「わかる」って言えばいいんだよ。
ぷるぷるがいよいよ最高潮に達した。ぴゅっぴゅっと息をし、じわじわと流れてくる。それから泣いているみたいに、しとしと、しとしと。耐えきれなくなったように決壊して、じょぼじょぼぼぼぼぼ……。すべて終わったときにはわたしの手も少し濡れていた。トイレットペーパーで拭く。拭いてあげる。小野ちゃんの大事なところはまだひくひくとしている。しゃくり上げているようだった。わたしは小野ちゃんの大事なところに口をつけた。舌を突きだして舐める。小野ちゃんの大事なところ、しょっぱいところ、泣いているところ。
大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。
わたしは水を流して、水に流した。
でも、流れなかった。
小野ちゃんは学校からまっすぐにわたしのところにやってきた。無言の小野ちゃんを部屋に迎え入れると、彼女はすぐさま勉強机に置いてある自分の大事なところを見つけて手にとった。そのまま前屈みになる。もごもご。パチン。なめらかな動作の完了で、大事なところがあるべきところに収まったことがわかった。朝に剥いだ布の一部をそっと差し出してみると、小野ちゃんはわたしの顔も見ずに受け取って、戻して、一言。
「舐めたでしょ」
「あ、う、うん。でも、えっと」
両肩を掴まれる。前後に激しく揺さぶられる。爪が食いこむぐらいの強さで、こわい顔で、小野ちゃんは、わたしのことを。
「汚れているんだよ! そんなことをするな!」
怒っている。怒られている。当然だよ、だって大事なところを勝手に舐めるなんて最低だよ、それにほかにもひどいことをした、小野ちゃんが抵抗できないからって、最悪だよ、いじめっ子たちと同じだ、自分の安全が確保されているときはいくらでも人にひどいことができて、想像して、実現するんだ。
性格が悪いから、性格のいい人にまで嫌われる。
わたしは帰ろうとした小野ちゃんの前に立って、膝をつき、頭を床につけた。
涙が無限に床にこぼれた。
「ごめんなさい、本当に、本当にごめんなさい……許してください、わ、わたし、小野ちゃんしかいないの、小野ちゃんだけなの、小野ちゃんがいないと人生じゃないの、わたしのこと、ぶっていいから、いっぱい殴っていいから、なんでも、いやなこと、ひどいこと、たくさんしていいから、嫌いにならないで」
シャツやスカートが擦れる、動く音がした。熱のこもった息を近くに感じた。頭をぽんぽんと叩かれた。でも「顔を上げて」と言われても上げられなくて、三回ぐらい言われても無視していたら髪の毛をぐいぐいと引っ張られて、上げた。
「なんでもしていいならなー」
背に天井の照明を受けて、後光が差しているようだった、一方で顔の陰影が薄くなっていて、表情の意味がぼんやりとぼやけていた。でも、小野ちゃんがわたしを抱き寄せたときには、そこに穏やかな明るさしか認められなかった。
「おまえと仲直りさせてくれい」
「うん、うん、ごめんね。ごめんね」
「こっちこそ怒鳴ってごめんなあ」
わたしの背中を小野ちゃんが何度も撫でてくれる。その小野ちゃんの大事なところが先ほどまでわたしの手のなかにあった。でも、だけど、小野ちゃんの大事なところは小野ちゃんの大事なところではあるけど小野ちゃんの大事なところではなかった。
たとえ小野ちゃんの大事なところを間違えてトイレに流してしまっても、小野ちゃんは失われない。この人のよさ、この優しさが小野ちゃんなんだ。たとえ小野ちゃんの大事なところが下水道にぷかぷか流れても、小野ちゃんは汚れない。
「あ、あのね、でもね。ひとつだけ言わせてほしいの」
「だめ」
「汚れてなかった。汚れていても汚れてなかったよ」
わたしの顔をじっと見てから「あたしもひとつだけ」と小野ちゃんは平坦な声で続けた。
「おまえの言ったこと、わかるよ」
それで、小野ちゃんが「だめ」って制止した理由がわかった。
どうしようもなくムカついたのだ。
悪魔に百日を売って切っても切れない斧を手に入れた。中学二年生の春および夏はんぶんの重みを両手に感じながら、部屋の中央で斧をぶんぶんと振る。今日は、今日の一時間目には、今日の二時間目には、今日の三時間目には、今日の四時間目には、今日の昼休みには学校に、行くぞ。
すれ違うすべての視線がわたしを追っている。雲に隠されることなくギンラギラにかがやく太陽によってアスファルトもわたしも焦がされているはず、なのに、ずっと寒気がして、震えて、一回でも転んだらそのまま二度と立ち上がれない気がしてくる。斧を交互に持ちかえながら、知っているはずなのに知らない道を歩く。
長く感じた道を振りかえり、前を向き、校門を忍び足で通過する。運動場からがやがやと声が聞こえてくる。一方で玄関はとても静かだ。だれとも会わずに階段を上る。教室前の廊下には生徒たちがのびのびと歩いたり立ち止まったりしていた……お昼休みのまんなかだ。終業式の前日にしてよかった。あやうく空っぽの教室で斧を振り回すところだった。
息を整える。わたしは斧を持ったまま、本来わたしが通ってもよいはずの教室を目指す。急いで、駆け足で、だけど廊下を走らないで。ここで立ち止まったら、わたしは永久に折れてしまう。教室に近づくと、閉ざされた窓や扉を突き抜ける異様な騒がしさに全身がひりひりしてくる。細工するために近づいた後ろの扉は暴風雨に曝されているみたいに揺れていた。たぶん扉に上体を預けている人が手を叩きながら大袈裟に笑っているんだ。きっとまただれかをいじめている。自分たち以外のことを話しているとき、みんなはいつも楽しそうだ。みんなで指をさした先には炎がある。あの人たちは燃えさかる炎を中心に取り囲んで踊っているだけ。踊っているのは楽しい。何も考えなくて済むから。でも鏡張りの部屋やステージの上では踊りたくない。だって指をさされる対象になるから、批判されたくないから、自分自身を見つめたくないから、だから鏡なんて見ないし表舞台には立たない。だめだ、考えごとで目の前の現実から逃げるな。前方にある扉の正面に立つ。わたしは闘う、わたしは闘える、わたしには切っても切れない斧がある、わたしには未来がある、ないなら作る、あるようにする、わたしは絶対に負けないんだ。
扉を開けた。見知ったクラスメイトたちがよく知っている表情で教室の中心を見ていた。その中心にはぽつんと孤立している椅子があった。一対であるはずの机は端に寄せられ、周囲の机も椅子から離されていた。だから教室にいる者にはどこからでもよく見えたし、聞こえた。
教室の中央、椅子に裸で縛りつけられた小野ちゃんが泣き声でその音をかき消そうとしていた。
わたしは教室の入り口近くにいた男子生徒の首を斧で叩き折った。
「死んじゃえ」
無い頭を抱えながら痛い痛いとうずくまる男子生徒を前に、だれもが最初は無反応だった。まるで自分は当事者ではないし、これからも当事者にはならないという顔だった。わたしは切っても切れない斧を振り回した。スポンスポンスポーン。本当はもっと肉が床に落ちる音の重さだったけど、とにかく人体は気持ちのよいリズムでばらばらになっていった。後ろの扉から逃げられなくて、わたしに突進してくる人たちを刎ねる、すり抜けようとした人を叩く、投げられた机を割る、逃げ惑う人を切る、こうしてみんな切れる。切れていないけど、切れる。自由に動けなくなる。切り離された自分の部位を見つめることになる。でも己のかたちにこれまで無関心だったから、本当に自分のものか半信半疑でいる。
悲痛な声の中心に小野ちゃんがいた。彼女は無傷で、でも無傷じゃなかった。
「どうして嘘をついたの、小野ちゃん」
「あたしのキャラでいじめられてるってキツいからなー」
「痛かったのに、どうして痛くないふりをしたの」
切っても切れない斧で、小野ちゃんに巻きつく縄を切ってあげる。わたしは茫然としている彼女を立たせて抱きしめる。足下は水浸しだし、目にうつる世界は手や足や胴体やその他いろいろなところが散乱していて醜いから、もう何も見ない。目をつぶる。見えないけど、わかる。
「汚いぞ」
「うん、すごく汚いかも」
「言うじゃねえか」
「でもそこは大事じゃないの」
「大事だろうがー」
わかる、わかる、わかる小野ちゃん。わたし、ようやくわかった。小野ちゃんが本当の本当にわかってくれていたこと、だけどわたしは小野ちゃんのことをわかっていなかったこと、そのせいで小野ちゃんを助けられなかったこと。
「小野ちゃんの大事なところはいらない。だって小野ちゃんはぜんぶ大事だから。きれいなところも汚いところも。ぜんぶがぜんぶ小野ちゃんだけど、小野ちゃんの一部は小野ちゃんじゃないから。自由に持ち運べて便利な小野ちゃんの一部より、不自由で不便な小野ちゃんのぜんぶがほしい」
今のわたしには切っても切れない斧がある。切っても切れない斧があるから小野ちゃんのことを救える。小野ちゃんとわかりあえる。
「もう傷つかないで。傷つこうとしないで。ずっとずっとわたしといっしょに生きて」
「おう」
だれかの腕がびちびちと跳ねる音にはっとして、次の授業が始まる前に元に戻さなきゃと慌てたら、小野ちゃんは美術の自習にしようぜって笑って、時間がないよ、担任もやっつけるんだろ次はあいつの科目だから、そっかならもっと時間があるね、それどころかあたしたちにはもっと時間がある、そうだねわたしたちには未来があってこれからなんでもできる、できる、できるよね、できる、そう、ふたりで泣きながら頷きあい、いつまでもお互いに「わかる」を捧げる。
大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。わたしたちは元通りになるどころか山盛りになる。くっついて大きくなって無敵になる。へこんだ深さの倍も膨らむ。生きてさえいれば、きっとどうにかなる。
でも、だけど、現実に悪魔なんていないから、夏休みの最終日、二学期が始まる一日前、小野ちゃんは、夜の公園で、ひとり、自分のからだを何度も刃物で切って、急所を避けて、何度も、ひとりで、取りかえしがつかなくなるまで、何度も、切って、死んでしまった。